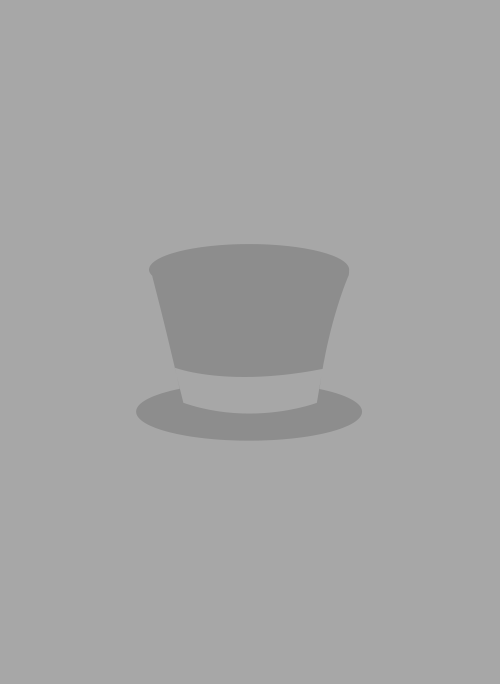深青が好きだった男の子が家の都合で転校してしまって、すぐのことだった。
優奈も少しは気を使わなくてはとめずらしく気を使っていて深青ともしばらく会っていなかった。
気など使わずに会っていればよかったと優奈は何度も後悔した。
久しぶりに会った時、これがあの深青かと思うほどだった。
明るく、いつも笑っていた深青の面影など1つもない。
まるで笑うことを忘れてしまったのかという感じで、それよりも表情を失ってしまったようだった。
「深青?」
声をかけても俯いていた深青が動くことはなかった。
ただ、一点だけをじっと見つめている状態で、首からかかった鈴だけをじっと握りしめていた。
小学生だった優奈はどう深青に接したらいいのかわからず戸惑っていた。
父から深青が目の前でお父さんを失ったのを聞いて、ますます接し方がわからなくなっていた。
ただ、ずっと傍にいようと。
それだけを思い、傍にいた。
すると、何にも反応しない深青が鈴の音色にだけ反応することに気づく。
(私じゃ駄目なんだ)
その時ほど痛感に感じたことはない。
こんな状態の深青を救えるのは彼だけなのだと………。
それから、優奈はいろいろな場所へ深青を連れ出した。
幼いながら一生懸命に調べて深青の好きだった男の子がいる学校まで調べた。
そこは優奈たちの家からは電車で2時間ほどかかるところにあった。
今でこそなんでもない距離だが、小学生の優奈たちにはそれは大冒険だった。