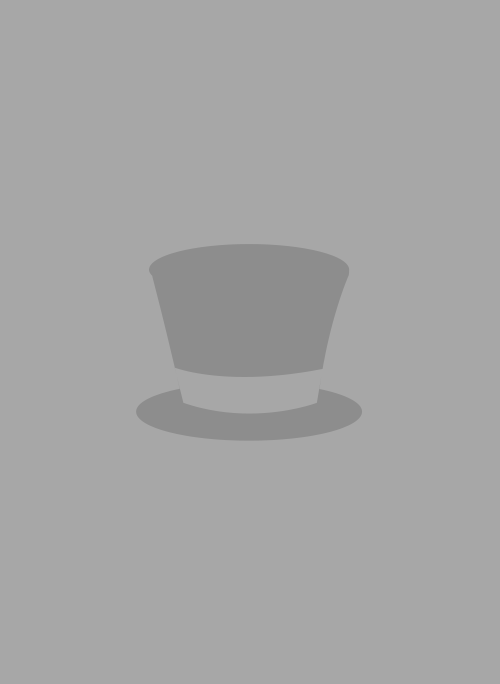「え? なにが?」
突然、大也が謝りだしたことに驚く深青。
「いや、ごめん。なんか根堀葉堀聞いちゃって」
「なんだ、そんなこと気にしなくていいのに。話したくないことだったら、私もこんなにぽんぽんと話さないよ」
「そっか。そう言ってくれると安心するよ」
(本当に、こんな風に気を使ってくれるところとか良い人だと思うのになあ)
深青はときどき大也の気遣いを感じ、そのたびに自分の中にある大也への疑いに罪悪感を覚えてしまう。
本当はそんな大也を見て、もっと打ち解けて本当の友達になりたい。
そう何度も強く思った。
「それにしてもさ、俺、今まで夏川やみゆきがいてこうやって如月と2人だけで話すことってなかったから如月のことおとなしい感じの人だなって思ってた。それに、入学式のこともあって、俺の印象悪いんじゃないかな、って。本当はまだ怒ってるんじゃないか、とか」
頭をかきながら、はずかしそうに言う大也に深青はなんとも言えない表情をする。
「全然、ないよ」
そう言いながらも内心、深青の胸は痛む。
もちろん怒ってはいないが大也が深青のことを見たと知ってからは大也のことを疑っているのだから。
それは、気にかけてくれる大也には申し訳ないことだから。
「確かに入学式の時は、変な人とか思ったけど。今はそんなことないよ。いいお友達」
深青の言葉を聞き、明らかに安心した表情をする。
だけど、深青はますます罪悪感が募る。
自分はいつからこんなに嘘がうまくなったんだろう。
胸に刺すような痛みを感じながらも、自分が決めたことだと深青はぎゅっと手に力を入れ、前を向いて、校門をくぐった。