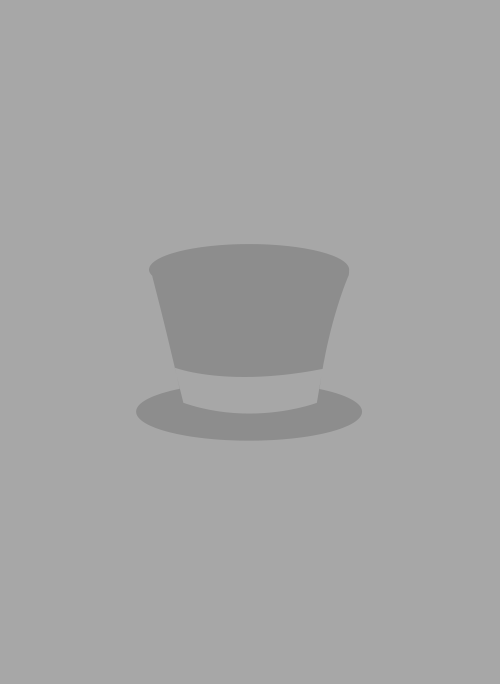「ちょっとそこ! 和んでる場合じゃないでしょ! 早く、教師の名前を言いなさい!」
2人のまったりとした雰囲気に優奈は痺れを切らす。
もともとは話をこじらせたのは自分なのだが、女王様のような性格の彼女がいつまでも自分のせいだとうじうじと考えているはずはなく、1人で先を見つめていた。
「はいはい。…………でも、俺、その教師の名前は知らないぜ」
「はぁ? ちょっと、待て。あんた知ってるって言ってたじゃない。あんなに私たちに言ってたのに、やっぱり違いましたなんて許されないわよ」
優奈は鬼のような形相で大也に詰め寄る。
「いや、名前は知らないけど顔は覚えてるってこと。だから、誰かははっきり言えるぜ。それに、お前たちだって1回会ってるって」
「そりゃ、そうでしょうよ。学校の教師ならね。あんたね、確実じゃないのにあんなえらそうなこと言ってたわけ? これじゃ、知らないのとかわりないじゃない!」
優奈の怒りの声とは反対に涼やかな深青の声が冷静に大也に確信を問う。
「私たちにも面識がある教師ということだよね、それって。どこで私たちと会ったの?」
深青の言葉の中に何か重要なことが含まれているとは思わない。
だけど、あまりにも切羽詰った深青の表情から優奈は大也への追求を止めた。
「え…………、あ、えと。化学室の爆発事故があった日に避難する時に声をかけてきた教師がいるだろ? そいつ………」
「化学室の爆発………」
深青は顎に手を置き、呟きながら考え込む。
優奈もその日のことを思い出そうと記憶を探った。