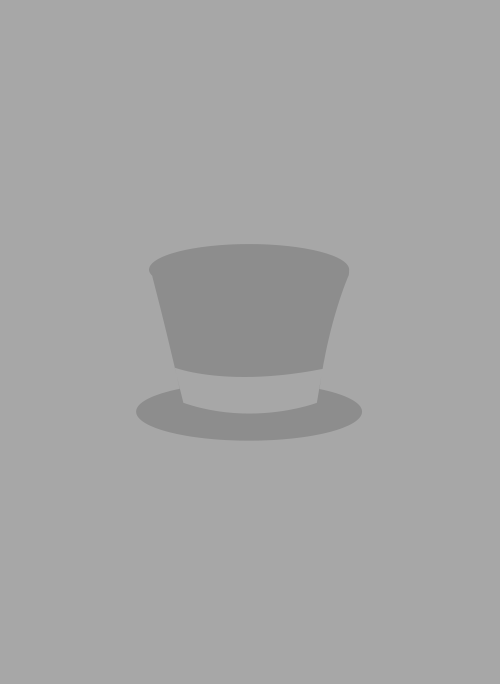「一条さん。本当に見覚えない?」
グラウンドでサッカーをしている一条香織を指差しながら深青は大也に問う。
だが、大也は腕を組み、考え込むが記憶の端にも彼女の顔に見覚えがない。
見る限り、かわいいと大也は思った。
だから、こんなにかわいい子なら1度見たなら絶対に覚えているはずだ。
だが、大也には全く覚えがない。
と、いうことは自信を持って見覚えがないと言い切れる。
「絶対、ない。印象に残りそうな顔じゃん。でも、覚えがないんだ。絶対ないと言い切れるね」
大也はかわいい子とは直接には言わず、オブラートに印象に残りそうな顔という表現で包んでなんとかかわす。
「そっか………。何か、手がかりが掴めそうだと思ったんだけど。そう簡単にはいかないか」
深青の声には落胆の色がでていた。
そんな深青の姿を見ると悪いことはしていないのだが、なぜか罪悪感が大也を襲う。
そして、自分が何の役にも立たないことに少し苛立った。
彼の中では自分だけが彼女に守られているのが男のプライドとしても許せないのかもしれない。
だけど、現実には自分が逆の立場に立つことなんてできないのだ。
わかっているだけに大也は余計に自分に腹が立つ。
見覚えがないと答えたものの大也はもう1度、一条香織を見た。