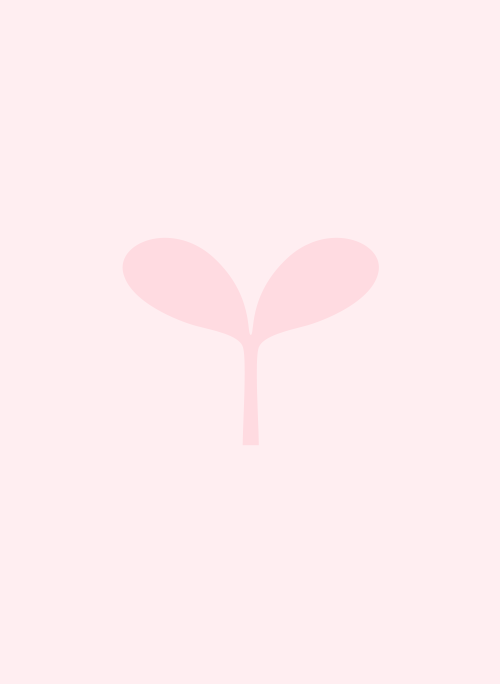あの日から
何度もニーは、ドーターに会いに来ていた。
ドーターが海に魚を採りに潜ると、決まって岩陰から姿をあらわすし、
ドーターが海に潜らなくて、海辺で貝しか拾わない日には、沖の方で波間に頭だけ出して、ドーターに向かって
「キッキッキッ」
と声を出して、浮かんだりしていた。
「他の人に見つかったら、捕まってしまうわよ」
ドーターは、ニーの姿を見るたびに心配して、そう言うが、言葉は通じないので、ドーターの心配はニーには伝わらない。
初めて足を掴まれた時には、かなり驚いていたドーターであったが、今では見慣れたせいか、何とも思わなくなってしまった。
それどころか、ニーの姿が自分に近い者に見え、親近感すら覚えるのだった。
村の人の中にも、ドーターと同年齢の子ども達がいるが、彼らは、いつも風をまとっている、自分たちと違う髪と瞳を持ったドーターを、自分たちとは違う種の生き物を見るように、神聖化して見るので、彼女は友だちと呼べる人間をつくらなかった。
別に、それが孤独だとも感じていなかった。元々、生まれた時から、ほとんどの時間をひとりで過ごしてきたドーターは、寂しいという感情に欠けていた。
何度もニーは、ドーターに会いに来ていた。
ドーターが海に魚を採りに潜ると、決まって岩陰から姿をあらわすし、
ドーターが海に潜らなくて、海辺で貝しか拾わない日には、沖の方で波間に頭だけ出して、ドーターに向かって
「キッキッキッ」
と声を出して、浮かんだりしていた。
「他の人に見つかったら、捕まってしまうわよ」
ドーターは、ニーの姿を見るたびに心配して、そう言うが、言葉は通じないので、ドーターの心配はニーには伝わらない。
初めて足を掴まれた時には、かなり驚いていたドーターであったが、今では見慣れたせいか、何とも思わなくなってしまった。
それどころか、ニーの姿が自分に近い者に見え、親近感すら覚えるのだった。
村の人の中にも、ドーターと同年齢の子ども達がいるが、彼らは、いつも風をまとっている、自分たちと違う髪と瞳を持ったドーターを、自分たちとは違う種の生き物を見るように、神聖化して見るので、彼女は友だちと呼べる人間をつくらなかった。
別に、それが孤独だとも感じていなかった。元々、生まれた時から、ほとんどの時間をひとりで過ごしてきたドーターは、寂しいという感情に欠けていた。