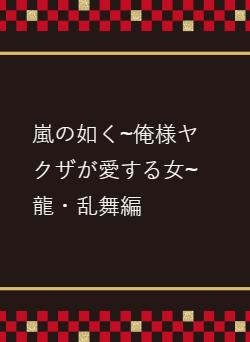俺は父上の邸宅に結婚の報告に。それを聞きつけて、馬を走らせて、滋貴がやって来た。
廊を歩くヤツの足音は急ぎ足。
俺と父上の間に無粋に割って入ってきた。
結い上げた髪を乱し、普段は沈着冷静な滋貴の慌てた形相に父上は目を見開き驚く。
「どうしたのじゃ?…滋貴」
父上の問いかけも存在も無視して俺だけを見つめて、目の前に歩み寄る。
「兄上…一体どう言うことですか?私のキモチを知ってて」
「俺も彼女を見初めただけだ」
本当に恋焦がれてるなら、俺よりも早く逢瀬をすれば良いこと。
罪の意識等俺は滋貴に全く感じていなかった。
廊を歩くヤツの足音は急ぎ足。
俺と父上の間に無粋に割って入ってきた。
結い上げた髪を乱し、普段は沈着冷静な滋貴の慌てた形相に父上は目を見開き驚く。
「どうしたのじゃ?…滋貴」
父上の問いかけも存在も無視して俺だけを見つめて、目の前に歩み寄る。
「兄上…一体どう言うことですか?私のキモチを知ってて」
「俺も彼女を見初めただけだ」
本当に恋焦がれてるなら、俺よりも早く逢瀬をすれば良いこと。
罪の意識等俺は滋貴に全く感じていなかった。