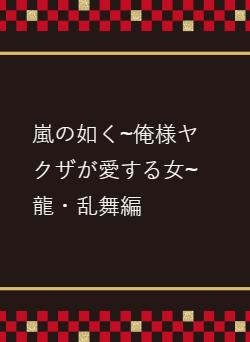「芍薬のように風情があり、牡丹のように華麗で、百合の花のように清楚…女性の美しさの形容だ」
「へぇ~っ」
「まぁー全てがお前に当てはまってるワケじゃないが」
「ひどい~ッ!!」
見慣れた花奏のふくれっ面が俺の顔に笑いを浮かばせた。
「そう言われたくなければ、もっと、いい女になれ」
俺は花奏の耳元で囁く。
「いい女って言われても…」
「一人でできないか…なら、俺が手伝ってやる」
「手伝うって…」
花奏は言葉尻を濁し、白い頬は淡い桜色に染め、顔を俯かせた。
芍薬のような大輪の花の笑顔を浮かべ、
『妃女神』としての華麗な姿を見せ、
清らかで汚れない心を持つ、
お前はもう、言葉通り、女性の美しさを兼ね備えている。
柄にもなく照れ臭い自分を隠すための演技だった。
「へぇ~っ」
「まぁー全てがお前に当てはまってるワケじゃないが」
「ひどい~ッ!!」
見慣れた花奏のふくれっ面が俺の顔に笑いを浮かばせた。
「そう言われたくなければ、もっと、いい女になれ」
俺は花奏の耳元で囁く。
「いい女って言われても…」
「一人でできないか…なら、俺が手伝ってやる」
「手伝うって…」
花奏は言葉尻を濁し、白い頬は淡い桜色に染め、顔を俯かせた。
芍薬のような大輪の花の笑顔を浮かべ、
『妃女神』としての華麗な姿を見せ、
清らかで汚れない心を持つ、
お前はもう、言葉通り、女性の美しさを兼ね備えている。
柄にもなく照れ臭い自分を隠すための演技だった。