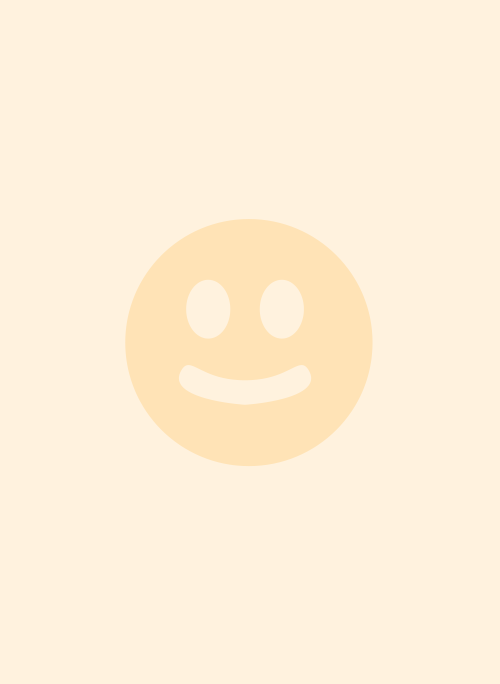いつも笑ってて
いつも明るい彼が
…泣いていた。
あたしを抱きしめるよりは、しがみつくように。
一人にしないで…と言うように、あたしを離してくれない。
「光梨…?」
ああ…あたしも同じだ。
心配するときに相手の名前を呼ぶことしか出来ないなんて。
気の利く言葉の一つもかけてやれないなんて。
「俺の話も……聞いて………」
小さく呟くその声の心理が知りたくて、静かに頷いた。
そこに、あたしの知らない事実があるような気がした。
□■□■□
「……ぅ…そ……………」
絶句。
これが今のあたしの現状だった。
光梨はあたしと違って幸せに親に愛されている。
そう思っていた。
何の苦労も知らずに呑気に生きているのだと思っていた。
でも…、…違った。
彼の人生はあまりにも壮絶たるものだった。
幼なじみとして知る、隣の幸せな家庭は、いつの間にかボロボロに崩れ去っていたのだ。