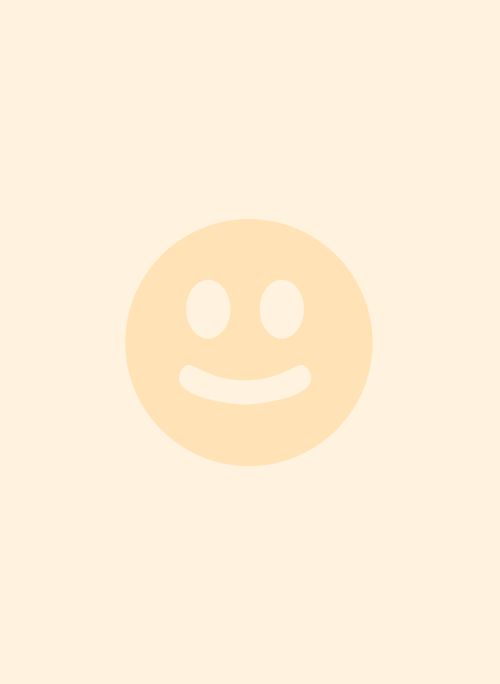噂には聞いていたが、まさか自分が猫タクシーに乗ることになるとは夢にも思っていなかった。
「お客さん、ついてますぜ」
とハンドルを握った三毛猫が言う。名札には『田中』とだけ書いてあるので田中という名の猫なのだろう。
「今日はもうお開きにしようと思ってたとこなんでさ。一日中街を走っても誰にも止められない。タクシーなんて仕事やってるとたまにこんな日があるんでさ。誰にも求められない日が。そんな日はキーを抜いてさっさと寝ちまうに限る。だけどギリギリであんたが止めてくだすった。いやあ、嬉しかったなあ。さあ、どこへなりとも行きやしょう。で、どこに向かいます?」
ぼくが自宅の住所を告げると田中はヒゲを二回震わせ乱暴にタクシーを発進させた。
どのタクシーもそうなように、猫タクシーもまたどこかこちらを落ち着かせない雰囲気を持っている。
「ねえ?」
「はい?」
田中はバックミラーをちらりとも見ない。そもそも背丈が足りていないのだからバックミラーなんて見る必要がないのだ。
「どうしてタクシーの中って落ち着かないんだろう?」
「落ち着きませんか?」
「まあ。」
わりと。
答えが返ってこないのでこの話題は流れてしまったのだと思い黙っていると、田中の尻尾がパタパタとせわしなく動く音が聞こえてきた。どうやら真剣に考えてくれているらしい。
赤信号で車が止まる。猫タクシーをみた人たちが携帯のカメラをこちらに向けて写真を撮るのでぼくはなんとなく俯いて爪の甘皮をいじる。
「思うに」
と、田中が切り出したのは随分時間がたってからだった。
「タクシー運転手ってのは人生の大半をタクシーの中で過ごしやす。タクシーの中で生まれタクシーの中で飯を食いタクシーの中で眠りタクシーの中で死ぬ。トイレくらいでさ、外でするのは。だからタクシーってのはタクシー運転手にとっては家みたいなもんでさ。誰だって他人の家にお邪魔するのは多少は緊張しますでしょう?そういうことなんじゃないかなあ」
ぼくは「ふうん」と感心する。
だけど一般的なタクシー運転手は別にタクシーから生まれるわけじゃないしタクシーで死んだりはしない。殆どは。
ぼく達の殆どが家で生まれ家で死ぬことがないように。
「お客さん、ついてますぜ」
とハンドルを握った三毛猫が言う。名札には『田中』とだけ書いてあるので田中という名の猫なのだろう。
「今日はもうお開きにしようと思ってたとこなんでさ。一日中街を走っても誰にも止められない。タクシーなんて仕事やってるとたまにこんな日があるんでさ。誰にも求められない日が。そんな日はキーを抜いてさっさと寝ちまうに限る。だけどギリギリであんたが止めてくだすった。いやあ、嬉しかったなあ。さあ、どこへなりとも行きやしょう。で、どこに向かいます?」
ぼくが自宅の住所を告げると田中はヒゲを二回震わせ乱暴にタクシーを発進させた。
どのタクシーもそうなように、猫タクシーもまたどこかこちらを落ち着かせない雰囲気を持っている。
「ねえ?」
「はい?」
田中はバックミラーをちらりとも見ない。そもそも背丈が足りていないのだからバックミラーなんて見る必要がないのだ。
「どうしてタクシーの中って落ち着かないんだろう?」
「落ち着きませんか?」
「まあ。」
わりと。
答えが返ってこないのでこの話題は流れてしまったのだと思い黙っていると、田中の尻尾がパタパタとせわしなく動く音が聞こえてきた。どうやら真剣に考えてくれているらしい。
赤信号で車が止まる。猫タクシーをみた人たちが携帯のカメラをこちらに向けて写真を撮るのでぼくはなんとなく俯いて爪の甘皮をいじる。
「思うに」
と、田中が切り出したのは随分時間がたってからだった。
「タクシー運転手ってのは人生の大半をタクシーの中で過ごしやす。タクシーの中で生まれタクシーの中で飯を食いタクシーの中で眠りタクシーの中で死ぬ。トイレくらいでさ、外でするのは。だからタクシーってのはタクシー運転手にとっては家みたいなもんでさ。誰だって他人の家にお邪魔するのは多少は緊張しますでしょう?そういうことなんじゃないかなあ」
ぼくは「ふうん」と感心する。
だけど一般的なタクシー運転手は別にタクシーから生まれるわけじゃないしタクシーで死んだりはしない。殆どは。
ぼく達の殆どが家で生まれ家で死ぬことがないように。