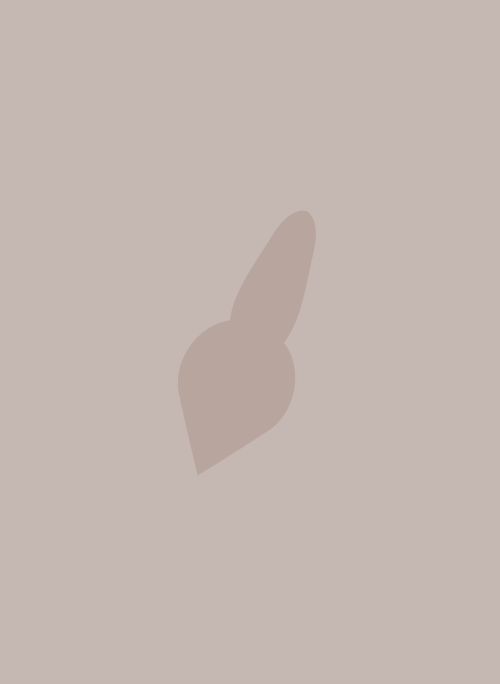──帰宅するとスミレの姿はなく、友紀ちゃんがいる様子もなかった。
とりあえず部屋に行き、ケータイを開いて秋にメールをしようか迷っていると、瓶に入ったしずく玉が目に止まった。
『……。』
ひとつ取りだし、悩んだ末口に中へ放り込んだ。
『ゆうきでるかな?』
アメで頬が膨らみ、舌の上でザラザラした砂糖をゆっくり溶かしながら制服を脱いだ。
一階に下りるとソファの上でクッションを抱えテレビを見るスミレを見つけた。
リビングに入ろうか迷い、勇気を出すために舐めた飴玉はトゲがなくなり、ツルツルになっていた。
『よし。』
小さく呟き一歩踏み入れた足は重たく、スミレを見るとテレビに釘付けだった。
『はぁー。』
タメ息を吐きタイミングを見計らってスミレに声をかけた。
『あのさ、友紀ちゃんは?』
こんな事が聞きたいんじゃないのに……
CMなのを確認し、切り出すと「買い物」とそっけない返事が帰ってきた。
『そう。……あのさ、朝の事なんだけど』
「始まった!」
本題に入ったと同時にCMが明けてしまった。
テレビが見たいから後にしてと言われた気がした。
『ごめん、邪魔して。
……また、声かける、から……』
最後の方は声になっていなかった。
ズキズキと締め付けられる痛みを堪え、
リビングを出てきてしまった。
『つまんないって、言ってたくせに……結局観るんじゃんか……』
──部屋で一人ボーッと教科書を開いたまま頬杖をついていた。
勇気を出せなかった。
そうだよな?飴玉舐めたくらいじゃ勇気なてでないよな。
『バカみたい。』
甘ったるい口の中は所々ふやけていた。
瓶の中のしずく玉を見つめていると、ケータイが震えた。
〈その後どう?〉秋からだった。
《ちゃんと話せてない。》〈そっか〉
ほんの些細な出来事でスミレと話せなくなるなら、なにもしないでいた方がいいのかな?
静かな朝食、静かなリビング、静かな部屋。
楽しくなる予定の日々は長く辛い退屈なあの日に戻ってしまった、それ以上かな?
あの頃の方がまだ楽しかった。
雨を眺め雨音を聴き、お風呂に入り眠るかたまに友紀ちゃんと話をするか。
近くにいるのに何も出来ない。
『このまま夏休みに入るのか。』
学校にいる方がまだましだ。
『はぁー………。
何に対して謝れば良いんだろう?
全っ然分かんない……』
とりあえず部屋に行き、ケータイを開いて秋にメールをしようか迷っていると、瓶に入ったしずく玉が目に止まった。
『……。』
ひとつ取りだし、悩んだ末口に中へ放り込んだ。
『ゆうきでるかな?』
アメで頬が膨らみ、舌の上でザラザラした砂糖をゆっくり溶かしながら制服を脱いだ。
一階に下りるとソファの上でクッションを抱えテレビを見るスミレを見つけた。
リビングに入ろうか迷い、勇気を出すために舐めた飴玉はトゲがなくなり、ツルツルになっていた。
『よし。』
小さく呟き一歩踏み入れた足は重たく、スミレを見るとテレビに釘付けだった。
『はぁー。』
タメ息を吐きタイミングを見計らってスミレに声をかけた。
『あのさ、友紀ちゃんは?』
こんな事が聞きたいんじゃないのに……
CMなのを確認し、切り出すと「買い物」とそっけない返事が帰ってきた。
『そう。……あのさ、朝の事なんだけど』
「始まった!」
本題に入ったと同時にCMが明けてしまった。
テレビが見たいから後にしてと言われた気がした。
『ごめん、邪魔して。
……また、声かける、から……』
最後の方は声になっていなかった。
ズキズキと締め付けられる痛みを堪え、
リビングを出てきてしまった。
『つまんないって、言ってたくせに……結局観るんじゃんか……』
──部屋で一人ボーッと教科書を開いたまま頬杖をついていた。
勇気を出せなかった。
そうだよな?飴玉舐めたくらいじゃ勇気なてでないよな。
『バカみたい。』
甘ったるい口の中は所々ふやけていた。
瓶の中のしずく玉を見つめていると、ケータイが震えた。
〈その後どう?〉秋からだった。
《ちゃんと話せてない。》〈そっか〉
ほんの些細な出来事でスミレと話せなくなるなら、なにもしないでいた方がいいのかな?
静かな朝食、静かなリビング、静かな部屋。
楽しくなる予定の日々は長く辛い退屈なあの日に戻ってしまった、それ以上かな?
あの頃の方がまだ楽しかった。
雨を眺め雨音を聴き、お風呂に入り眠るかたまに友紀ちゃんと話をするか。
近くにいるのに何も出来ない。
『このまま夏休みに入るのか。』
学校にいる方がまだましだ。
『はぁー………。
何に対して謝れば良いんだろう?
全っ然分かんない……』