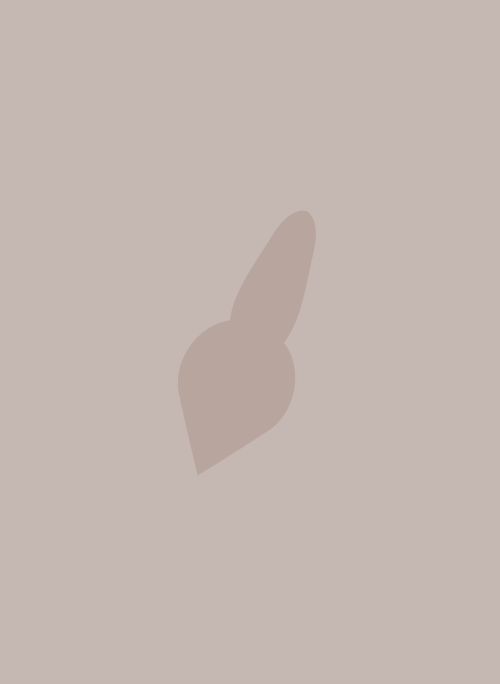俯き黙るスミレの髪がパラパラと崩れ、髪を耳にかけるとびっくりした顔で振り向いた。
「なに?」
『髪の毛柔らかいのな。猫触ってるみたい。気持ちいい……』
微笑み頭を撫でていると、顔を真っ赤にしながら目を伏せた。
本当に猫みたい。
『俺さ、今まで楽しいって思えたことなくて。スミレといる時は別だけど、いつも隣のは秋がいて、楽しい振りしてた。
ワクワクとかドキドキとかそんな感情自分の中にはもう無いと思ってた。
殻の中は安全だし、周りに合わせる必要もなくて、楽だったから。
そんな殻を突然壊されて、外に放り出されてめんどくさい事もあるし、すごく疲れるけど、初めて楽しいかもって。
……何でこんなこと話してるんだろう?』
「大人になったね?」
『そうかな?』
サラサラと指をすり抜ける髪を触っていると、心地よい眠気に襲われた。
『なんか、安心する。秋もこんな感じだったのかな?』
「え?」
『スミレの髪触ってたら、なんか眠くなってきちゃって……少しだけ、肩貸して……』
「え?」
返事を聞く前にポテと頭を肩にもたげると、懐かしい匂いが鼻をくすぐった。
『スミレの匂い……』
「……。」
『いい匂い……』
──目を覚ますとスミレも眠っていて、今度は俺の肩にスミレの頭が乗った。
つかの間の二人の時間。誰もいないヒンヤリとした階段で何してるんだろう?って思いながら、その寝顔を頭に焼き付けた。
「ハルト……」
『ん?』
見るとまだ眠っていた。
夢のなかでも俺と会ってるんだと考えたら嬉しくなった。
「た……ちゃダメ!」
『ん?』
いきなり大きな声を出すスミレは自分の声で目が覚めたらしく、寝ぼけた顔で俺を見た。
『おはよう』
「……おはよう。あれ?」
『どんな夢見てたの?』
「ん?晴斗が私のお菓子食べようとして、「食べちゃダメ!」って……」
『なるほど。』
素直に答えるスミレはまだ半分夢の中なのか、生アクビを繰り返した。
そんなスミレを部屋まで送り届け、自分の部屋へ戻った。
スミレの体温がまだ少し残ってる。
制服に着替え、カーテンを開け、窓越しに空を見上げた。
しばらくして目覚ましが鳴り、大きく伸びをすると、一階へ下りた。
『おはよう』
リビングに入ると友紀ちゃんの隣で笑うスミレが俺を見て顔を赤くし「おはよう」と小さな声で挨拶をした。
あれから起きたんだ。
『……スミレちょっといいかな?』
廊下に呼び出し、いきなり額に手を当てたからか、また驚かせてしまった。
「晴斗?」
『いきなりごめん、顔赤かったから風邪引かせちゃったかと思って。』
「大丈夫。晴斗の顔見たら今朝の事思い出しただけ。……もういいかな?」
『うん。』
リビングに戻るスミレを見送り、ため息を吐くと、「朝から仲がいいな」
振り向くと父さんがスーツ姿で立っていた。
『いつからいたの?』
「いま来たとこだよ。」
肩をポンッと叩き、リビングへ入っていった。
その後を追うように俺もリビングへ戻った。
『いただきます』
スミレが昨日より遠くなったのは気のせいなんだろうか?
朝食を食べながらチラチラスミレの様子を伺っていると、友紀ちゃんに「ケンカでもしたの?」と聞かれ、二人とも黙ってしまった。
『……ケンカはしてないけど』
「友紀ちゃんには言えない恥ずかしい事があって」
「恥ずかしいこと?」
パンをかじりながら小首をかしげた友紀ちゃんは、俺を見た。
『はは……』
スミレの言う恥ずかしい事は今朝の事だろうと検討はついていた。
「だいたい晴斗があんな事するから!」
『俺のせい?』
ムッとする顔すらかわいい。
にやける顔を必死に隠してもスミレにはバレバレで、余計に怒らせてしまった。
『ごめん』と謝るも許してくれそうにはなかった。
「ケンカするほど仲がいいって言うし」
ニコニコと俺たちを見る二人にタメ息を吐き、半分朝食を残し『ごちそうさま』をした。
ソファに置いた鞄を掴むと友紀ちゃんからお弁当を受け取った。
「今日のお弁当、スミレちゃんが作ったのよ」
こっそり耳打ちされた言葉に嬉しくてスミレを見ると、ウィンナーにフォークを突き刺し俺を睨んだ。
『いってきます……。』
友紀ちゃんにネクタイをキツく締められ、逃げるように家を出た。
「なに?」
『髪の毛柔らかいのな。猫触ってるみたい。気持ちいい……』
微笑み頭を撫でていると、顔を真っ赤にしながら目を伏せた。
本当に猫みたい。
『俺さ、今まで楽しいって思えたことなくて。スミレといる時は別だけど、いつも隣のは秋がいて、楽しい振りしてた。
ワクワクとかドキドキとかそんな感情自分の中にはもう無いと思ってた。
殻の中は安全だし、周りに合わせる必要もなくて、楽だったから。
そんな殻を突然壊されて、外に放り出されてめんどくさい事もあるし、すごく疲れるけど、初めて楽しいかもって。
……何でこんなこと話してるんだろう?』
「大人になったね?」
『そうかな?』
サラサラと指をすり抜ける髪を触っていると、心地よい眠気に襲われた。
『なんか、安心する。秋もこんな感じだったのかな?』
「え?」
『スミレの髪触ってたら、なんか眠くなってきちゃって……少しだけ、肩貸して……』
「え?」
返事を聞く前にポテと頭を肩にもたげると、懐かしい匂いが鼻をくすぐった。
『スミレの匂い……』
「……。」
『いい匂い……』
──目を覚ますとスミレも眠っていて、今度は俺の肩にスミレの頭が乗った。
つかの間の二人の時間。誰もいないヒンヤリとした階段で何してるんだろう?って思いながら、その寝顔を頭に焼き付けた。
「ハルト……」
『ん?』
見るとまだ眠っていた。
夢のなかでも俺と会ってるんだと考えたら嬉しくなった。
「た……ちゃダメ!」
『ん?』
いきなり大きな声を出すスミレは自分の声で目が覚めたらしく、寝ぼけた顔で俺を見た。
『おはよう』
「……おはよう。あれ?」
『どんな夢見てたの?』
「ん?晴斗が私のお菓子食べようとして、「食べちゃダメ!」って……」
『なるほど。』
素直に答えるスミレはまだ半分夢の中なのか、生アクビを繰り返した。
そんなスミレを部屋まで送り届け、自分の部屋へ戻った。
スミレの体温がまだ少し残ってる。
制服に着替え、カーテンを開け、窓越しに空を見上げた。
しばらくして目覚ましが鳴り、大きく伸びをすると、一階へ下りた。
『おはよう』
リビングに入ると友紀ちゃんの隣で笑うスミレが俺を見て顔を赤くし「おはよう」と小さな声で挨拶をした。
あれから起きたんだ。
『……スミレちょっといいかな?』
廊下に呼び出し、いきなり額に手を当てたからか、また驚かせてしまった。
「晴斗?」
『いきなりごめん、顔赤かったから風邪引かせちゃったかと思って。』
「大丈夫。晴斗の顔見たら今朝の事思い出しただけ。……もういいかな?」
『うん。』
リビングに戻るスミレを見送り、ため息を吐くと、「朝から仲がいいな」
振り向くと父さんがスーツ姿で立っていた。
『いつからいたの?』
「いま来たとこだよ。」
肩をポンッと叩き、リビングへ入っていった。
その後を追うように俺もリビングへ戻った。
『いただきます』
スミレが昨日より遠くなったのは気のせいなんだろうか?
朝食を食べながらチラチラスミレの様子を伺っていると、友紀ちゃんに「ケンカでもしたの?」と聞かれ、二人とも黙ってしまった。
『……ケンカはしてないけど』
「友紀ちゃんには言えない恥ずかしい事があって」
「恥ずかしいこと?」
パンをかじりながら小首をかしげた友紀ちゃんは、俺を見た。
『はは……』
スミレの言う恥ずかしい事は今朝の事だろうと検討はついていた。
「だいたい晴斗があんな事するから!」
『俺のせい?』
ムッとする顔すらかわいい。
にやける顔を必死に隠してもスミレにはバレバレで、余計に怒らせてしまった。
『ごめん』と謝るも許してくれそうにはなかった。
「ケンカするほど仲がいいって言うし」
ニコニコと俺たちを見る二人にタメ息を吐き、半分朝食を残し『ごちそうさま』をした。
ソファに置いた鞄を掴むと友紀ちゃんからお弁当を受け取った。
「今日のお弁当、スミレちゃんが作ったのよ」
こっそり耳打ちされた言葉に嬉しくてスミレを見ると、ウィンナーにフォークを突き刺し俺を睨んだ。
『いってきます……。』
友紀ちゃんにネクタイをキツく締められ、逃げるように家を出た。