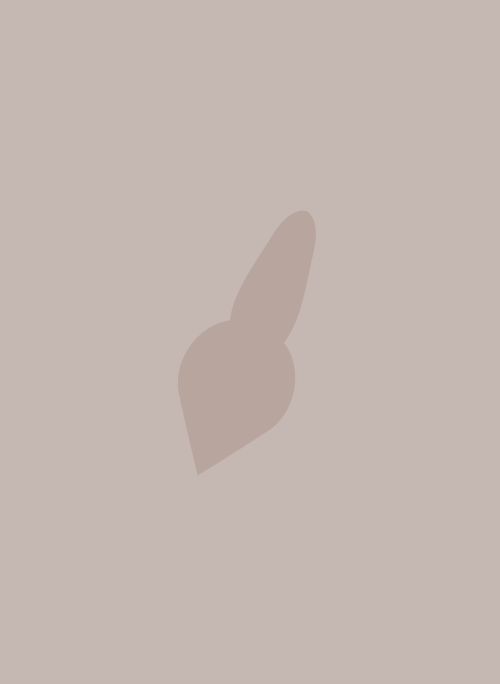「さて、友紀ちゃんの朝食を食べにいくか!!」
そう言い、部屋を出ていく秋の後を追った。
「───ん~!やっぱ日本の朝は納豆に味噌汁、卵焼きだよなぁ」
『お前が来た日は、いつも同じメニューだよな?』
「友紀ちゃんだって作るの楽じゃんか! 同じ朝食しか作らなくて良いんだからさ?!」
そんな会話を笑って聞いてる友紀ちゃんは、秋と違う朝ご飯を食べていた。
きっと、サンドイッチの方が作るのが楽なんだろう、優雅にコーヒーなんて飲んでるけど、そろそろこの朝食も限界なんじゃないかと思い始めてる。
秋は知らないけど、友紀ちゃんはいつも父さんに頼んで朝食の材料を買ってきてもらっている。
父さんは「慣れましたから」なんて言ってたけど、一度だけ見てしまった。
──その日いつもより帰りが遅く、急いで家路へ向かっている時だった。
父さんが買い物袋をカバンの後ろに隠し、俯き歩いているところを……。
正直情けないと思った。やましい事なんかしていないんだから、堂々と歩けばいいじゃないか!と、丁度反抗期と重なっていたのもあってか、そんな怒りにも似た感情が出た時もあった。
家に帰った時、何も知らない秋がテレビを観ながら笑っているのを見て、危うく掴みかかりそうになったのを今でもハッキリと覚えてる。
「ごちそうさまでした!」
パンッと手を合わせ、きれいに食べ終えた食器を自ら片付ける秋を目で追いながら、友紀ちゃんにも目を向けた。
窓の外を眺め、今にもため息を吐き出しそうな顔を見ていると、視線に気づいたのか目があった。
「今日はハズレるかも」
真顔でそんなことを言われ、なんの事か分からず『そう』と答えた。
そう言い、部屋を出ていく秋の後を追った。
「───ん~!やっぱ日本の朝は納豆に味噌汁、卵焼きだよなぁ」
『お前が来た日は、いつも同じメニューだよな?』
「友紀ちゃんだって作るの楽じゃんか! 同じ朝食しか作らなくて良いんだからさ?!」
そんな会話を笑って聞いてる友紀ちゃんは、秋と違う朝ご飯を食べていた。
きっと、サンドイッチの方が作るのが楽なんだろう、優雅にコーヒーなんて飲んでるけど、そろそろこの朝食も限界なんじゃないかと思い始めてる。
秋は知らないけど、友紀ちゃんはいつも父さんに頼んで朝食の材料を買ってきてもらっている。
父さんは「慣れましたから」なんて言ってたけど、一度だけ見てしまった。
──その日いつもより帰りが遅く、急いで家路へ向かっている時だった。
父さんが買い物袋をカバンの後ろに隠し、俯き歩いているところを……。
正直情けないと思った。やましい事なんかしていないんだから、堂々と歩けばいいじゃないか!と、丁度反抗期と重なっていたのもあってか、そんな怒りにも似た感情が出た時もあった。
家に帰った時、何も知らない秋がテレビを観ながら笑っているのを見て、危うく掴みかかりそうになったのを今でもハッキリと覚えてる。
「ごちそうさまでした!」
パンッと手を合わせ、きれいに食べ終えた食器を自ら片付ける秋を目で追いながら、友紀ちゃんにも目を向けた。
窓の外を眺め、今にもため息を吐き出しそうな顔を見ていると、視線に気づいたのか目があった。
「今日はハズレるかも」
真顔でそんなことを言われ、なんの事か分からず『そう』と答えた。