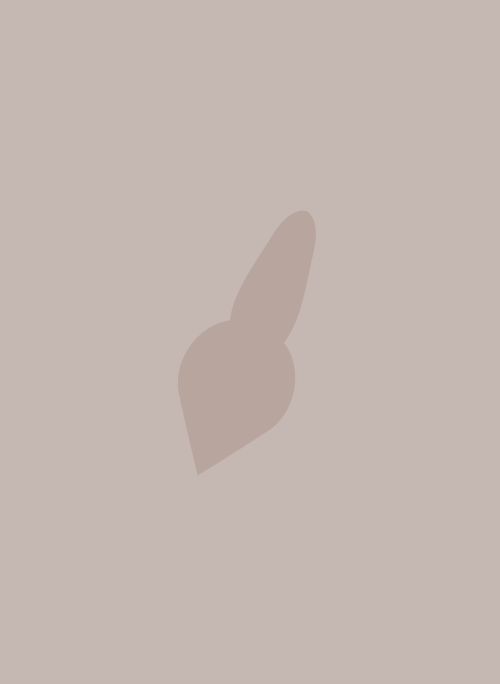それから二日後、赤いスーツケースを引きながらスミレが我が家にやってきた。
いつもより落ち着かないのは、あの電話があったからで『いらっしゃい……』の後が続かなかった。
スミレから視線を逸らし、黙ってスーツケースを客間に運んだ。
俺が倒れた事は友紀ちゃんや父さんには知らせなかった。心配してくれただろうけど、スミレ絡んでる分言いいにくい。
『ハァー……』
スーツケースを部屋の端に置き、タメ息をついた時、廊下が軋む音がした。
「大丈夫なの?」
『ぅわっ! いつから』
「タメ息ついたあたりから」
『そっか……』
なんか、気まずい。
こんな時、どんな言葉を掛けるのが正解なんだろう?
『俺はもう大丈夫だから、心配しないで?あと、友紀ちゃん達には言ってないから、出来れば言わないで欲しい。』
「うん、分かった」
スミレは普通に接してくれてるのに、1人で緊張して舞い上がってなんかバカみたいだ。
『ごめん。なんか、ダメだ』
小さく笑いスミレの横を抜けると、そのまま家を出て秋の家に向かった。
玄関でチャイムを鳴らし、少し待って出迎えた秋は俺の様子を見てなにも言わず家に入れてくれた。
『スミレが来ててさ……』
秋の部屋がある二階へと向かいながら切り出すと、「夏が終わる~」と意味の分からない事を叫び黙ってしまった。
いつもより落ち着かないのは、あの電話があったからで『いらっしゃい……』の後が続かなかった。
スミレから視線を逸らし、黙ってスーツケースを客間に運んだ。
俺が倒れた事は友紀ちゃんや父さんには知らせなかった。心配してくれただろうけど、スミレ絡んでる分言いいにくい。
『ハァー……』
スーツケースを部屋の端に置き、タメ息をついた時、廊下が軋む音がした。
「大丈夫なの?」
『ぅわっ! いつから』
「タメ息ついたあたりから」
『そっか……』
なんか、気まずい。
こんな時、どんな言葉を掛けるのが正解なんだろう?
『俺はもう大丈夫だから、心配しないで?あと、友紀ちゃん達には言ってないから、出来れば言わないで欲しい。』
「うん、分かった」
スミレは普通に接してくれてるのに、1人で緊張して舞い上がってなんかバカみたいだ。
『ごめん。なんか、ダメだ』
小さく笑いスミレの横を抜けると、そのまま家を出て秋の家に向かった。
玄関でチャイムを鳴らし、少し待って出迎えた秋は俺の様子を見てなにも言わず家に入れてくれた。
『スミレが来ててさ……』
秋の部屋がある二階へと向かいながら切り出すと、「夏が終わる~」と意味の分からない事を叫び黙ってしまった。