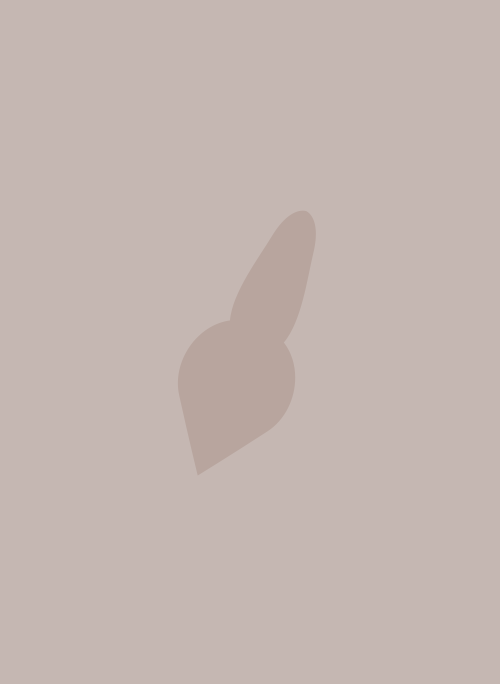『ハァッ、ハァッ、ハァッ……』
気づくと真っ暗闇の中を走っていた。
ここがどこなのか、なぜ走っているのかも分からぬままひたすら走っていた。
足下に転がる砂利が、裸足の足裏に食い込み感じないはずの痛みが幾度も襲った。
両手を伸ばすと届く壁は、岩のようにゴツゴツしている。
俺は走るのを止め、壁に手を這わせ歩く事にした。
これが夢なのか現実なのかも分からず、ただ暗い一本道を止まることなく歩いていると、遠くの方に丸い穴のような光が見えた。
──歩き続け暗闇と光の境目にたどり着いた。戸惑いなから後ろを振り向くと、光に照らされ見えるハズの道は石コロ一つ見えない暗闇だった。
前を向くと、目も開けられないほどの
光で満ちていた。
『どうなってんだこれ?』
眩しい光の中を歩き始めると、意識が現実へと戻っていくのが分かった。
ゆっくり瞼を開けると見覚えのある天井があった。
『保健室?なんで?』
ぼんやりする頭を動かすと、誰かが側で眠っていた。前髪が顔に掛かって顔は見えないけれど、名札に書かれた苗字でそれが秋だと分かった。
「あ、気づいた? 体調はどう?」
先生が俺に気づき、近寄ってきた。
『たぶん、大丈夫です。……俺どうなったんですか?』
「私にも分からないけど、下駄箱で急に倒れたとかで……勢いよく入ってきた時は何事かと思ったけど、この子の話しだけじゃよく分からないけど、貧血でも無さそうだし。
急激なストレスがかかって脳がショーとしちゃったのかな?」
『その診断大丈夫なんですか?』
「念のため病院で観てもらってね?」
『はい。』
「そういえば、何度か鳴ってたわよ?」
『え?』
ケータイを見ると着信が何件か来ていた。
『スミレからだ……』
「かけてあげれば?」
『あとでかけ直します。まだ少しフワフワするので』
「フワフワ……」
気づくと真っ暗闇の中を走っていた。
ここがどこなのか、なぜ走っているのかも分からぬままひたすら走っていた。
足下に転がる砂利が、裸足の足裏に食い込み感じないはずの痛みが幾度も襲った。
両手を伸ばすと届く壁は、岩のようにゴツゴツしている。
俺は走るのを止め、壁に手を這わせ歩く事にした。
これが夢なのか現実なのかも分からず、ただ暗い一本道を止まることなく歩いていると、遠くの方に丸い穴のような光が見えた。
──歩き続け暗闇と光の境目にたどり着いた。戸惑いなから後ろを振り向くと、光に照らされ見えるハズの道は石コロ一つ見えない暗闇だった。
前を向くと、目も開けられないほどの
光で満ちていた。
『どうなってんだこれ?』
眩しい光の中を歩き始めると、意識が現実へと戻っていくのが分かった。
ゆっくり瞼を開けると見覚えのある天井があった。
『保健室?なんで?』
ぼんやりする頭を動かすと、誰かが側で眠っていた。前髪が顔に掛かって顔は見えないけれど、名札に書かれた苗字でそれが秋だと分かった。
「あ、気づいた? 体調はどう?」
先生が俺に気づき、近寄ってきた。
『たぶん、大丈夫です。……俺どうなったんですか?』
「私にも分からないけど、下駄箱で急に倒れたとかで……勢いよく入ってきた時は何事かと思ったけど、この子の話しだけじゃよく分からないけど、貧血でも無さそうだし。
急激なストレスがかかって脳がショーとしちゃったのかな?」
『その診断大丈夫なんですか?』
「念のため病院で観てもらってね?」
『はい。』
「そういえば、何度か鳴ってたわよ?」
『え?』
ケータイを見ると着信が何件か来ていた。
『スミレからだ……』
「かけてあげれば?」
『あとでかけ直します。まだ少しフワフワするので』
「フワフワ……」