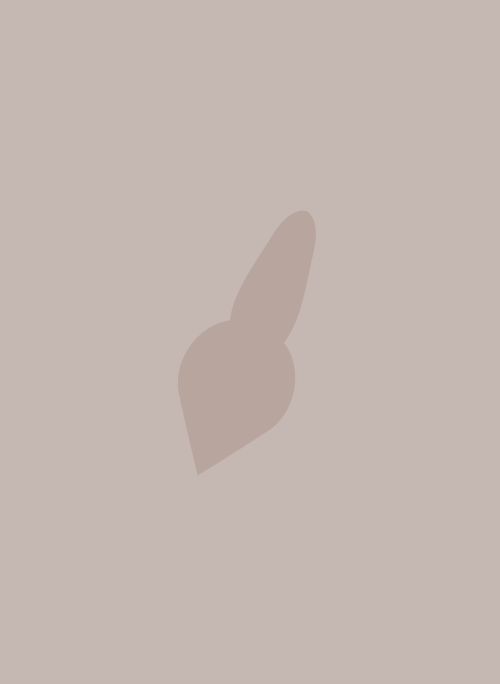『これで良くなるといいんだけど……』
「晴斗は、俺が寝たらまたどこか行くのの?」
不安なのか子供見たいな事を言う秋に、理由を聞くと「さっき起きたら居なくて、怖くなって……気づいたら電話してた。」
小さくごめんと謝る秋の頭を撫で笑った。
「電話して、怖いなんてカッコ悪くて言えないから、アイスで誤魔化した。」
『そっか。』
こんなこと、前にもあったっけ?
今の秋と同じように風邪を引き、悪夢を見て怯える俺を安心させようと、友紀ちゃんがしてくれた事を思いだし、不安がる秋の頭をクシャクシャにした後
『どこにも行かないから、心配すんな』そう声をかけた。
その時、幼い頃の記憶が一瞬にして蘇った。(怖い夢見るから、もう風邪引きたくない!)病み上がりの秋がほっぺたを赤くしながら言っていた言葉。
風邪を引く度(僕が眠ったら消えちゃうんでしょ?)と泣きながら俺の髪を掴んで離さなかった事。
そんなことすら忘れるなんて。
『ちゃんといるから』
「うん。」
秋が熱を出した日は、必ず髪の毛を掴まれていた。どこにも行くなと言ってるのか、ただ安心するからなのか。それは授業中であってもお構いなしで、先生や夏子さんを困らせるほど俺の名前を呼んでいたらしい。
秋にとって俺の髪の毛はクマのぬいぐるみのようなもので、無いと不安になる存在なんだろう。
『あ、眠れないなら髪の毛貸すけど?』
ベッド脇に膝を付き、枕元に頬杖をつき髪の毛を差し出した。
「髪の……っいるかそんなもん!!」
急に大声を出したせいで激しく咳込み、またくの字に身体を歪めていた。
『大丈夫か?』
「ハァー……晴斗」
『ん?』
落ち着いた秋がボソッと「やっぱりいる」と手を伸ばした。
『フッ 早く風邪治せよ、東雲が心配してたぞ?』
「東雲が!?」
起き上がろうとする秋を押さえつけ、東雲に会った時のことを話した。
しばらく他愛もない話をしながら、秋が眠るのを見ているうち、気づけば自分も夢の中に引き込まれていた……────
「晴斗は、俺が寝たらまたどこか行くのの?」
不安なのか子供見たいな事を言う秋に、理由を聞くと「さっき起きたら居なくて、怖くなって……気づいたら電話してた。」
小さくごめんと謝る秋の頭を撫で笑った。
「電話して、怖いなんてカッコ悪くて言えないから、アイスで誤魔化した。」
『そっか。』
こんなこと、前にもあったっけ?
今の秋と同じように風邪を引き、悪夢を見て怯える俺を安心させようと、友紀ちゃんがしてくれた事を思いだし、不安がる秋の頭をクシャクシャにした後
『どこにも行かないから、心配すんな』そう声をかけた。
その時、幼い頃の記憶が一瞬にして蘇った。(怖い夢見るから、もう風邪引きたくない!)病み上がりの秋がほっぺたを赤くしながら言っていた言葉。
風邪を引く度(僕が眠ったら消えちゃうんでしょ?)と泣きながら俺の髪を掴んで離さなかった事。
そんなことすら忘れるなんて。
『ちゃんといるから』
「うん。」
秋が熱を出した日は、必ず髪の毛を掴まれていた。どこにも行くなと言ってるのか、ただ安心するからなのか。それは授業中であってもお構いなしで、先生や夏子さんを困らせるほど俺の名前を呼んでいたらしい。
秋にとって俺の髪の毛はクマのぬいぐるみのようなもので、無いと不安になる存在なんだろう。
『あ、眠れないなら髪の毛貸すけど?』
ベッド脇に膝を付き、枕元に頬杖をつき髪の毛を差し出した。
「髪の……っいるかそんなもん!!」
急に大声を出したせいで激しく咳込み、またくの字に身体を歪めていた。
『大丈夫か?』
「ハァー……晴斗」
『ん?』
落ち着いた秋がボソッと「やっぱりいる」と手を伸ばした。
『フッ 早く風邪治せよ、東雲が心配してたぞ?』
「東雲が!?」
起き上がろうとする秋を押さえつけ、東雲に会った時のことを話した。
しばらく他愛もない話をしながら、秋が眠るのを見ているうち、気づけば自分も夢の中に引き込まれていた……────