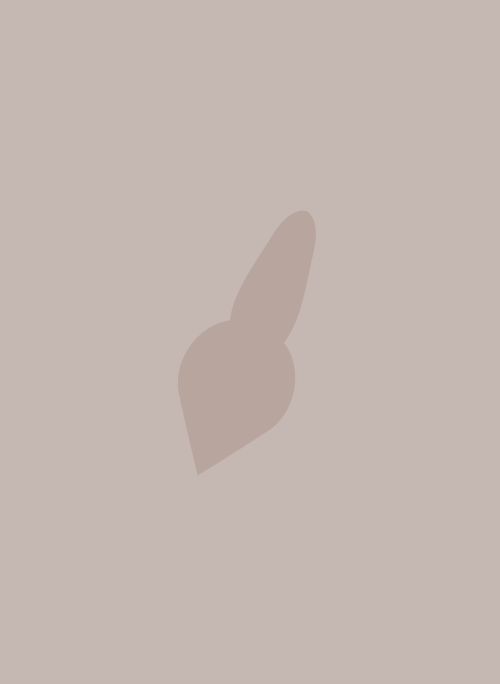──見慣れた通りに差し掛かっても尚、沈黙は続いていた。傘のせいか、東雲がさっきよりも遠くに感じる。
『なあ……』
この沈黙に堪えきれずそう切り出してはみたものの、その先が浮かばずまた沈黙がきた。
『──東雲って、下の名前なに?』
考えた末の質問がソレだった。
それでも東雲は黙ったままで、顔が隠れて表情も見えず、一人モヤモヤしたまま歩みを進めた。
『ハァー……。』
静かに吐いたタメ息は雨の中に消え、靴先に出来たシミを見ながら、憂鬱な日だ。と思った。
──その後も、何度か話しかけようと試みるも、口を開いてすぐ諦めた。返事が返ってこない相手に話しかけ続けるほどタフじゃない。
雨脚が弱まった頃、ポケットの中で何かが震える感覚がして、ポケットを触るとケータイのバイブが振動していた。
『秋だ……はい』
「もしもし?」
電話にでると鼻声の秋が息苦しそうに呼吸をしていた。
『どうした?』
「どうしたじゃねぇよ!今、どこっ……?」
咳をしながら怒る秋の問に、辺りを見渡しながら歩いた。
『どこだろ?もうすぐT字路に着くけど』
目印になるものを探していると、電話の向こうで「遅い……」と言った声が微かに聞こえ、「アイスは?」と今度はハッキリと聞こえ『買った』
「アイスが溶けてたらまた買いに行かせるからな……。」
『あっ……』
そこでアイスの存在を思い出し袋を覗きこむと、汗をかいたアイスにまだ少し氷の結晶が残っていた。
「さっき、友紀ちゃんに毛布もらった」
『そっか、ちゃんと暖かくしてろよ?』
「うんっ……ゴホッゲホッ」
『咳出るから切るぞ?』
「うん、なるべく早く……」
『なるべく早く帰るから、じゃあな?』
「うん」
寂しげな声を出す秋に電話越しに微笑した。
電話を切りケータイをポケットに入れると、コンビニ袋を目の高さまで持ち上げ、カップを押すと少し柔らかくなっていた。
『まだ、大丈夫だよな?』
『なあ……』
この沈黙に堪えきれずそう切り出してはみたものの、その先が浮かばずまた沈黙がきた。
『──東雲って、下の名前なに?』
考えた末の質問がソレだった。
それでも東雲は黙ったままで、顔が隠れて表情も見えず、一人モヤモヤしたまま歩みを進めた。
『ハァー……。』
静かに吐いたタメ息は雨の中に消え、靴先に出来たシミを見ながら、憂鬱な日だ。と思った。
──その後も、何度か話しかけようと試みるも、口を開いてすぐ諦めた。返事が返ってこない相手に話しかけ続けるほどタフじゃない。
雨脚が弱まった頃、ポケットの中で何かが震える感覚がして、ポケットを触るとケータイのバイブが振動していた。
『秋だ……はい』
「もしもし?」
電話にでると鼻声の秋が息苦しそうに呼吸をしていた。
『どうした?』
「どうしたじゃねぇよ!今、どこっ……?」
咳をしながら怒る秋の問に、辺りを見渡しながら歩いた。
『どこだろ?もうすぐT字路に着くけど』
目印になるものを探していると、電話の向こうで「遅い……」と言った声が微かに聞こえ、「アイスは?」と今度はハッキリと聞こえ『買った』
「アイスが溶けてたらまた買いに行かせるからな……。」
『あっ……』
そこでアイスの存在を思い出し袋を覗きこむと、汗をかいたアイスにまだ少し氷の結晶が残っていた。
「さっき、友紀ちゃんに毛布もらった」
『そっか、ちゃんと暖かくしてろよ?』
「うんっ……ゴホッゲホッ」
『咳出るから切るぞ?』
「うん、なるべく早く……」
『なるべく早く帰るから、じゃあな?』
「うん」
寂しげな声を出す秋に電話越しに微笑した。
電話を切りケータイをポケットに入れると、コンビニ袋を目の高さまで持ち上げ、カップを押すと少し柔らかくなっていた。
『まだ、大丈夫だよな?』