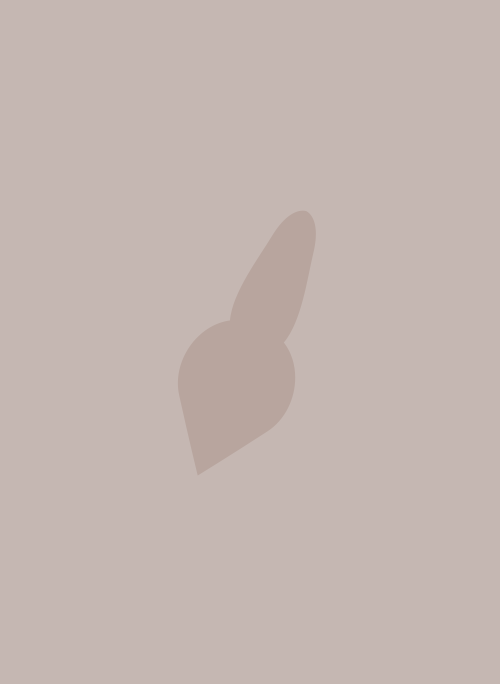──翌朝、スミレが帰ると言ったのはみんなが揃っている朝食の席でのことだった。
俺たちを見送った後で帰ると言われ、顔には出さなかったけど動揺していた。
「もう少し泊まっていけば良いのに。」
珍しくよく喋る父さんは、殆ど話も出来なかったと残念がっていた。
「じゃあ、今度はおじさんが休みの日に来ますね?」
「お!嬉しい事言ってくれるねぇ」
本当に嬉しそうな父さんを見て、友紀ちゃんも嬉しそうだった。
そんな光景を前に俺と秋は黙々と食べていた。
『秋そろそろ行くぞ?』
「あ、おう」
味噌汁を啜る秋を残し、先にリビングを出た。
玄関に出しておいたカバンを肩に掛け、靴を履きながら秋を待った。
『秋ー、置いてくぞ?!』
「ちょっ、待ってって!!」
慌てて靴を履く秋にカバンを渡しながら、友紀ちゃんとスミレを交互に見た。
「友紀ちゃん、今日のご飯も最高にうまかったよ!」
「ありがとう」
友紀ちゃんに親指をたてニッコリ笑う秋は、言い終わると隣に並んだ。
「二人とも気をつけるのよ?」
友紀ちゃんの言葉に手を振り、玄関の扉を開けた。
『行ってきます』
「行って来まーす」
「いってらっしゃい!」
俺たちを見送った後で帰ると言われ、顔には出さなかったけど動揺していた。
「もう少し泊まっていけば良いのに。」
珍しくよく喋る父さんは、殆ど話も出来なかったと残念がっていた。
「じゃあ、今度はおじさんが休みの日に来ますね?」
「お!嬉しい事言ってくれるねぇ」
本当に嬉しそうな父さんを見て、友紀ちゃんも嬉しそうだった。
そんな光景を前に俺と秋は黙々と食べていた。
『秋そろそろ行くぞ?』
「あ、おう」
味噌汁を啜る秋を残し、先にリビングを出た。
玄関に出しておいたカバンを肩に掛け、靴を履きながら秋を待った。
『秋ー、置いてくぞ?!』
「ちょっ、待ってって!!」
慌てて靴を履く秋にカバンを渡しながら、友紀ちゃんとスミレを交互に見た。
「友紀ちゃん、今日のご飯も最高にうまかったよ!」
「ありがとう」
友紀ちゃんに親指をたてニッコリ笑う秋は、言い終わると隣に並んだ。
「二人とも気をつけるのよ?」
友紀ちゃんの言葉に手を振り、玄関の扉を開けた。
『行ってきます』
「行って来まーす」
「いってらっしゃい!」