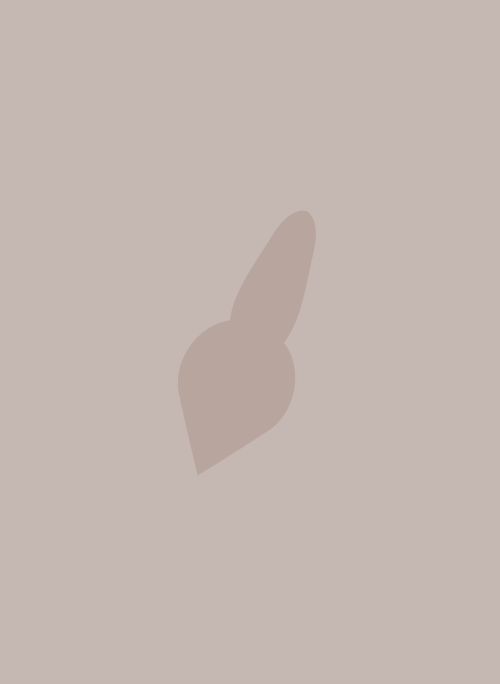──目を開けると、部屋も外も真っ暗だった。目が暗闇になれるまでの間、目を開け横になっていた。
起きたときからの妙な違和感を感じつつも、身体を起こすことはしなかった。何日振りかの雨の音を聞きながら、ようやく気怠い身体を起こした。
『……誰?秋?』
その違和感に言葉を掛けると、パチッという音と共に、眩しい光が視界を塞いだ。反射的に目を閉じると顔を背けた。
「懐かしいなぁ」
その声に目を細め見ると、スミレが椅子に座ってこっちを見ていた。
どうして?いつから?なんで?そんな言葉ばかりが浮かんでは消えた。
「晴斗前より笑わなくなったね?昔はニコニコしてたのに」
『……そうだっけ?』
「そうだよ、あの時はもう少し愛想があった。なに考えてるのか分からなかったけど、ニコッて笑い返してくれてた」
そう言って笑うスミレの視線は、僕の後ろにあった。
『あの頃は、楽しかったんだと思う』
ボソッと呟いた俺の言葉に「今は?」目が合ったスミレの顔に笑顔はなく、何かを必死に汲み取ろうとしてるのを感じた。
『ん?』
「今は、楽しくないの?」
『……どうだろ?』
その言葉をこの先何度聞くんだろう?
その場に胡座を掻き、変な沈黙をやり過ごし、口を開いた。
『顔には出してないけど、多分、つまらなくはないと思う。……ちょっと、変な話してもいいかな?』
「うん、いいよ?」
『本当に変な話だから、適当に聞き流してくれていいから。
……俺、小さい頃から秋が羨ましくてさ』
「なんで?」
『なんでって、……いつもスミレを独り占めしてたから、スミレの隣に座ってても、俺の方みてる時間よりも俺が横顔みてる時間の方が長くて、ずっと秋になりたいって思ってた。……って話し。
なんでこんな事話したんだろ?』
言ってるうちに恥ずかしくなり、頬が熱くなってくのを感じ、居たたまれず部屋をでた。
起きたときからの妙な違和感を感じつつも、身体を起こすことはしなかった。何日振りかの雨の音を聞きながら、ようやく気怠い身体を起こした。
『……誰?秋?』
その違和感に言葉を掛けると、パチッという音と共に、眩しい光が視界を塞いだ。反射的に目を閉じると顔を背けた。
「懐かしいなぁ」
その声に目を細め見ると、スミレが椅子に座ってこっちを見ていた。
どうして?いつから?なんで?そんな言葉ばかりが浮かんでは消えた。
「晴斗前より笑わなくなったね?昔はニコニコしてたのに」
『……そうだっけ?』
「そうだよ、あの時はもう少し愛想があった。なに考えてるのか分からなかったけど、ニコッて笑い返してくれてた」
そう言って笑うスミレの視線は、僕の後ろにあった。
『あの頃は、楽しかったんだと思う』
ボソッと呟いた俺の言葉に「今は?」目が合ったスミレの顔に笑顔はなく、何かを必死に汲み取ろうとしてるのを感じた。
『ん?』
「今は、楽しくないの?」
『……どうだろ?』
その言葉をこの先何度聞くんだろう?
その場に胡座を掻き、変な沈黙をやり過ごし、口を開いた。
『顔には出してないけど、多分、つまらなくはないと思う。……ちょっと、変な話してもいいかな?』
「うん、いいよ?」
『本当に変な話だから、適当に聞き流してくれていいから。
……俺、小さい頃から秋が羨ましくてさ』
「なんで?」
『なんでって、……いつもスミレを独り占めしてたから、スミレの隣に座ってても、俺の方みてる時間よりも俺が横顔みてる時間の方が長くて、ずっと秋になりたいって思ってた。……って話し。
なんでこんな事話したんだろ?』
言ってるうちに恥ずかしくなり、頬が熱くなってくのを感じ、居たたまれず部屋をでた。