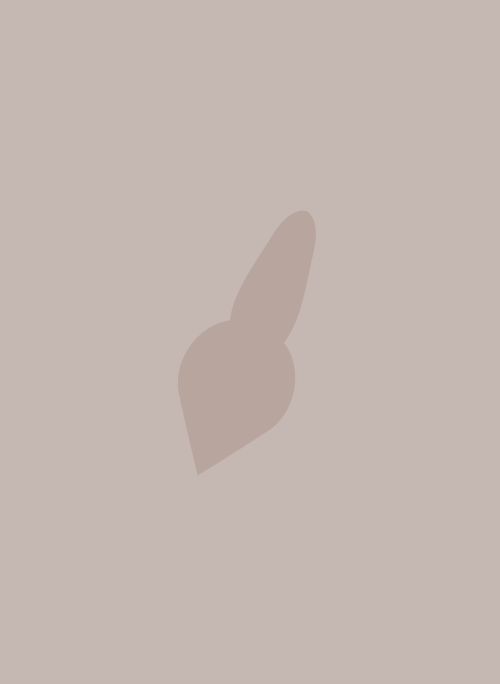「で、その飴どうしたの?」
深呼吸をしてから秋の問いに答えた。
『もらった』
「誰に?」
『女の子』
「女の子?」
『お前も知ってる子だよ、黄色い雨合羽きた、小さな女の子』
飴玉に視線を向けながら説明すると、秋が何かを思い出したような声を出した。
「あ~、あの学校帰りに話してた女の子?」
うんと頷いた。
「雨ん中1人で遊んでた?」
また、うんと頷いた。
「マジか……」
『この飴玉、喰うなよ?』
「誰が食うかよ!!」
『……なあ、俺って、そんなに笑わない?』
「なんだよいきなり。まぁ、そう言われるとあんま見ないかも、晴斗の笑顔」
『そっか。……この飴はさ、俺が笑った回数なんだよ』
「フッ。そういえば、あん時の晴斗いい顔してたもんなぁ……」
遠い目で話す秋は、微かに笑っていた。
ふと窓に目を向けると、雨は止んでいた。音のない空には、ただ白く丸い太陽が、影のようにそこにいた。
「やっと晴れたんだ、夕方だけど。」
『やっと、か……』
1人切ない気持ちになっていると、隣で秋の腹が鳴った。
「今日の晩ご飯なんだろ?」
『手作りハンバーグ』
無言でガッツポーズする姿を見て、まだ秋の両親が帰っていないのを知った。
その日の夜、まだ片づいていないリビングでの夕食になった。
友紀ちゃんは「すぐ片づけるから」なんて言ってたけど、さらに増えた荷物の山が消えるのは、たぶん3日かそれ以上になるだろうと勝手に予想した。
深呼吸をしてから秋の問いに答えた。
『もらった』
「誰に?」
『女の子』
「女の子?」
『お前も知ってる子だよ、黄色い雨合羽きた、小さな女の子』
飴玉に視線を向けながら説明すると、秋が何かを思い出したような声を出した。
「あ~、あの学校帰りに話してた女の子?」
うんと頷いた。
「雨ん中1人で遊んでた?」
また、うんと頷いた。
「マジか……」
『この飴玉、喰うなよ?』
「誰が食うかよ!!」
『……なあ、俺って、そんなに笑わない?』
「なんだよいきなり。まぁ、そう言われるとあんま見ないかも、晴斗の笑顔」
『そっか。……この飴はさ、俺が笑った回数なんだよ』
「フッ。そういえば、あん時の晴斗いい顔してたもんなぁ……」
遠い目で話す秋は、微かに笑っていた。
ふと窓に目を向けると、雨は止んでいた。音のない空には、ただ白く丸い太陽が、影のようにそこにいた。
「やっと晴れたんだ、夕方だけど。」
『やっと、か……』
1人切ない気持ちになっていると、隣で秋の腹が鳴った。
「今日の晩ご飯なんだろ?」
『手作りハンバーグ』
無言でガッツポーズする姿を見て、まだ秋の両親が帰っていないのを知った。
その日の夜、まだ片づいていないリビングでの夕食になった。
友紀ちゃんは「すぐ片づけるから」なんて言ってたけど、さらに増えた荷物の山が消えるのは、たぶん3日かそれ以上になるだろうと勝手に予想した。