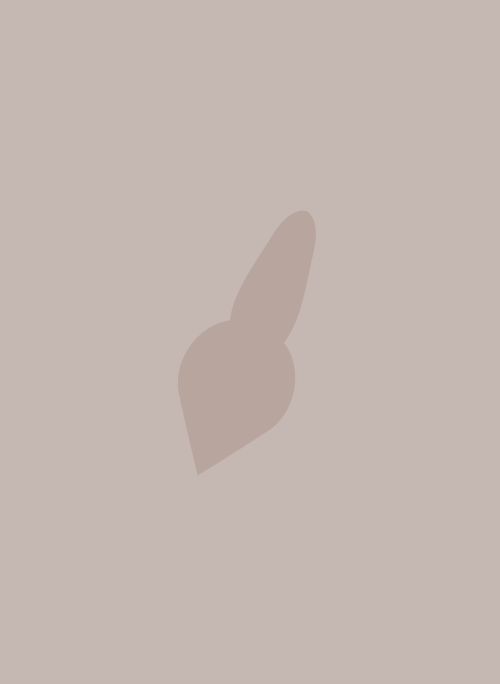『友紀ちゃん、あまってる空き瓶ある?』
家に帰り、リビングのドアを開けると、たくさんの荷物で溢れ返っていた。
『なにこれ……』
「見て分からない? 整理してるの。荷物仕舞おうとしたら、入らなくて……」
捨てればいいのに。と思ったが口には出さなかった。以前にも似たような事があり『捨てればいいのに』と呟いた途端、「いつか使う日がくるかもしれないじゃない!!」と逆ギレされ、もうなにも言うまいと心に決めた。
そんなことを思い出していると、視界の端に転がっている空き瓶を見つけた。
『あの空き瓶もらっていい?』
「ん~良いわよ~、好きなの持ってって」
荷物の隙間と隙間を縫うように歩き、空き瓶がズラリと並んだ台所までくると、パスタを入れておく瓶の隣にちょうど半分の高さの瓶を見つけ、手に取った。
『これなら……。友紀ちゃんこれ貰ってくね?』
「いいわよ~」
見もせず返事をする友紀ちゃんにため息をつき、再び荷物の隙間を抜け廊下に出た。
──部屋に戻るとカバンをベッドに、空き瓶を机に乗せ、蓋に付いてる金具を上げると、ポンッと勢いよく音をがした。ポケットにしまったままの飴玉を2つ、その中に落とし、カランカランッと音を立て落ちた赤と黄色の飴玉はまた少し小さく見えた。
「その飴なに?」
『うわっ!!』
飴に気を取られ過ぎて、後ろに居た秋に気づかなかった。
「あ、悪い」
平謝りの秋に大丈夫と言ったものの、心臓が止まりそうなほど驚いた。
家に帰り、リビングのドアを開けると、たくさんの荷物で溢れ返っていた。
『なにこれ……』
「見て分からない? 整理してるの。荷物仕舞おうとしたら、入らなくて……」
捨てればいいのに。と思ったが口には出さなかった。以前にも似たような事があり『捨てればいいのに』と呟いた途端、「いつか使う日がくるかもしれないじゃない!!」と逆ギレされ、もうなにも言うまいと心に決めた。
そんなことを思い出していると、視界の端に転がっている空き瓶を見つけた。
『あの空き瓶もらっていい?』
「ん~良いわよ~、好きなの持ってって」
荷物の隙間と隙間を縫うように歩き、空き瓶がズラリと並んだ台所までくると、パスタを入れておく瓶の隣にちょうど半分の高さの瓶を見つけ、手に取った。
『これなら……。友紀ちゃんこれ貰ってくね?』
「いいわよ~」
見もせず返事をする友紀ちゃんにため息をつき、再び荷物の隙間を抜け廊下に出た。
──部屋に戻るとカバンをベッドに、空き瓶を机に乗せ、蓋に付いてる金具を上げると、ポンッと勢いよく音をがした。ポケットにしまったままの飴玉を2つ、その中に落とし、カランカランッと音を立て落ちた赤と黄色の飴玉はまた少し小さく見えた。
「その飴なに?」
『うわっ!!』
飴に気を取られ過ぎて、後ろに居た秋に気づかなかった。
「あ、悪い」
平謝りの秋に大丈夫と言ったものの、心臓が止まりそうなほど驚いた。