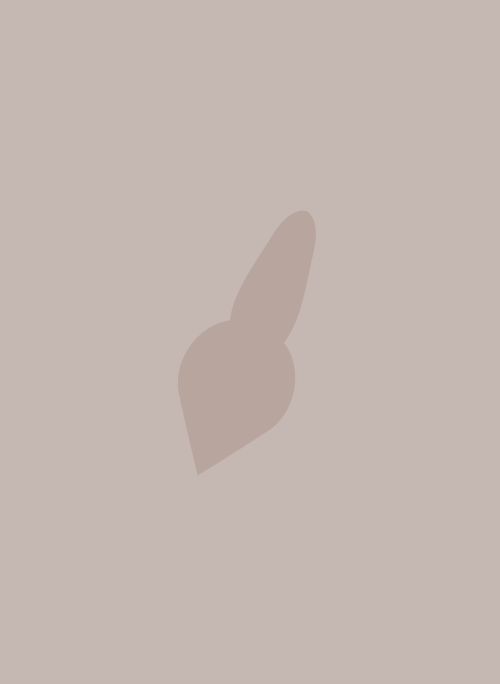「こうなること初めから分かってたのに……」
シャツの胸元をギュッと掴み、必死に笑顔を作る東雲の目からは、次から次へと溢れ堪えきれなくなった涙が、頬を伝い落ちていった。
「あの……こんなことお願いするの変だって分かってるんですけど、……と、友達になってくれませんか?」
『え?』
「図々しいお願いだってことはわかってます、でも……このまま話せなくなるのが嫌だから……だから、友達に」
『……別にいいけど、俺、秋みたいに話す方じゃないけど、それでも良いなら。』
それを聞いた東雲の顔に笑顔が戻った。
そして、また気づかない内に俺の口角はまた少し上がっていた。
東雲は涙を拭い、俺の元に来るといきなり手を差し出し「友達として、よろしくお願いします!」と頭を下げた。
『あ、よろしくお願いされます』
握った東雲の手は、暖かく小さかった。
それから少しお互いについて話した後、また明日と東雲が教室を出て行った。
遠ざかる足音に耳を澄ませ、カバンを取りに席に戻った。何も変わらないと思ったのに、変えないつもりだったのに、なにかが変わってしまった気がした。
『友達、か……』
秋が聞いたらなんて答えるだろう?
驚いて、笑って、ホッとする?
きっと「そっか」って言葉が返ってくるんだろうな。
そもそも、秋って俺のなんなんだろ?
ただの隣人で、幼馴染みで、ただの腐れ縁で『友達……なのかな?』
意識して考えたことなかったし、気づいたら隣にいるのが当たり前な存在に名前なんてあるんだろうか?
『ハァー。疲れた……』
シャツの胸元をギュッと掴み、必死に笑顔を作る東雲の目からは、次から次へと溢れ堪えきれなくなった涙が、頬を伝い落ちていった。
「あの……こんなことお願いするの変だって分かってるんですけど、……と、友達になってくれませんか?」
『え?』
「図々しいお願いだってことはわかってます、でも……このまま話せなくなるのが嫌だから……だから、友達に」
『……別にいいけど、俺、秋みたいに話す方じゃないけど、それでも良いなら。』
それを聞いた東雲の顔に笑顔が戻った。
そして、また気づかない内に俺の口角はまた少し上がっていた。
東雲は涙を拭い、俺の元に来るといきなり手を差し出し「友達として、よろしくお願いします!」と頭を下げた。
『あ、よろしくお願いされます』
握った東雲の手は、暖かく小さかった。
それから少しお互いについて話した後、また明日と東雲が教室を出て行った。
遠ざかる足音に耳を澄ませ、カバンを取りに席に戻った。何も変わらないと思ったのに、変えないつもりだったのに、なにかが変わってしまった気がした。
『友達、か……』
秋が聞いたらなんて答えるだろう?
驚いて、笑って、ホッとする?
きっと「そっか」って言葉が返ってくるんだろうな。
そもそも、秋って俺のなんなんだろ?
ただの隣人で、幼馴染みで、ただの腐れ縁で『友達……なのかな?』
意識して考えたことなかったし、気づいたら隣にいるのが当たり前な存在に名前なんてあるんだろうか?
『ハァー。疲れた……』