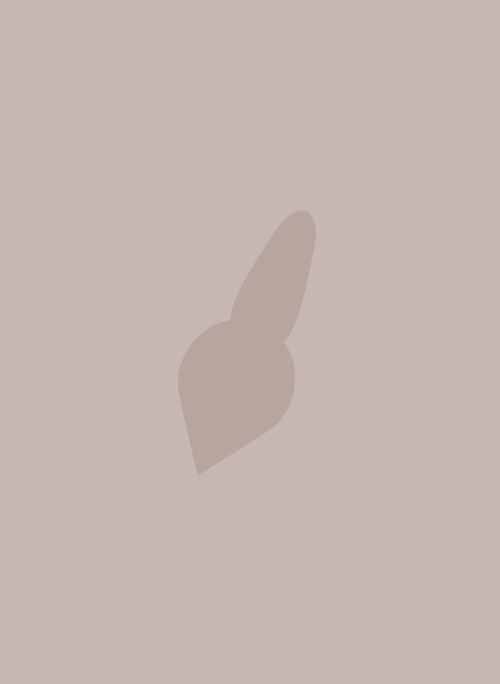花火が終わるのを待ったかのようにスミレが口を開いた。
「前置きが長い」
『ごめん。……その、振られても──』
「バカ。」
『……。』
「嫌いなんて言ってないし、まだ返事してない」
『うん……』
小さな声に自信のなさがにじみ出てるようで、俯いたままスミレの声を待った。
「ハル?」
『ん?』
声だけで返事を返すと、スミレの腕が俺に伸び俺の胸に顔を埋め、ゆっくりと顔をあげた。
不意に目が合い、逸らすと「逸らさないで?」と強い口調で言われ戸惑った。
『……近すぎる』
「いいから、見て?」
ドキドキと心臓が騒ぎだし、スミレを見つめ返すと、ニッコリ笑い
「ハルと同じくらい好きだよ」
と言われ、涙が溢れ目を伏せたら怒られた。
「久し振りに晴斗に会った時、カッコよくなっててビックリした。
……私ずっと晴斗の気持ちに気づいてたよ?でも、一生懸命隠そうとしてたし、私もハルに気持ち知られたくなかったから……」
『全部バレてたんだ。』
「今だから言うけど、晴斗のファーストキスは私だよ?」
『へ?このタイミングで?』
「フフッ」と笑い「私のファーストも晴斗だよ」と悪戯に笑い「晴斗が寝てる時にこっそり……。でも、キスしてる所を秋に見つかっちゃって、すっごい恥ずかしかったけど」
『……なんで今?』
「晴斗がズルいから、仕返し!」
可愛すぎて、嬉しすぎて……ニヤケる。なんだこれ……。
ため息を吐き、スミレの肩に顔を埋め腰に腕を回すと、しばらく動けずにいた。
「晴斗?」
心配そうな声が降ってくる。
スミレからなのか俺からなのか、心臓の音が心地よいリズムを刻み顔をあげると唇が触れそうなくらい近距離にスミレがいた。
スミレのからだがピクリと動き、瞳が動揺していた。
「晴斗……」
吐息がくすぐったい。
『スミレ……キスしたい。ダメかな?』
「いつも勝手にするくせに……こんな時だけズル……んっ!」
待てずに唇を塞ぐと諦めたのか、回された手が俺の服をギュッとつかんだ。
その仕草に押さえていた理性が限界を超えた。
滑り込ませた舌がスミレを捉えると厭らしい声が吐息と共に漏れ出た。
「んぅっ……っん……ぁ……」
唇を重ねながらなんどもなんども好きだと呟いた。
スミレが苦しいと背中を叩くまで、止める事ができなかった。
「っ……はぁ、はぁっ……バカ」
ドキッとするほど色っぽい表情に目を逸らした。
『ごめん……つい』
腰が抜けたのか、俺にしがみつくスミレを座らせ壁にもたれながら、互いに落ち着くまで手を繋ぎ、一人余韻に浸っていた。
『……先生に言われたこと、破っちゃったな?』
「最初から守る気なんてなかったクセに……フフッ」
堰を切ったように笑うスミレにつられ俺も笑った。
おもしろい事なんてひとつもないのに、ホッとしたからかな?
『好きだよ。』
ずっと言えなかった分、たくさん伝えから。一生掛かっても言えそうにないスミレへの気持ち。
だって、やっと堂々と守れる。
彼女だと言える事が嬉しい反面、まだ実感が無い分半信半疑だけど、両想いだ!てっ子供みたいにはしゃげたらスミレは笑うかな?
目が合い照れるスミレを見ながら、顔を寄せるとピクッと肩が動いた。
「私も、好きだよ……」
付き合ってから、2度目のキスで少しだけ実感する。
顔を離したとき、胸元をなにかに叩かれた感触で指輪の存在を思いだした。
『今ならつけても似合うかな?』
ネックレスを外し、指輪を出すと、スミレも同じように浴衣の中から指輪を出した。
『スミレ、手かして』
差し出される手に笑い、左手の薬指にそっと嵌めた。
同じくスミレが俺の指に指輪を嵌めると、知らぬ間に止めていた息を吐き出した。
指輪を眺め嬉しそうに笑う横顔を見つめ頭を撫でた。
「晴斗、帰ろう?」
『うん。』
差し出された手を握り、来た道を戻った。
長い長い廊下と階段を歩きながら、今まで話せなかった分を埋めるようにお互いの事を話した。
──帰る間際に再度職員室に行くと、「まだいたのか!」と驚かれ、「危ないから早く帰れ!」と怒られてしまった。
その会話を、俺の後ろで聞き笑うスミレを引き出し『お疲れ様です』と会釈し扉を閉めた。
「晴斗の意地悪」
ムッとする表情に笑い『俺の彼女ですって紹介したの』と誇らしげに言うと、「バカ……」と照れてるのか怒っているのか、校舎を後にするまで口を聞いてもらえなかった。
会えない時間もあるしこの先何があるか分からないけど、その笑顔の隣で一緒に笑っているのが俺であれと強く願った──
「前置きが長い」
『ごめん。……その、振られても──』
「バカ。」
『……。』
「嫌いなんて言ってないし、まだ返事してない」
『うん……』
小さな声に自信のなさがにじみ出てるようで、俯いたままスミレの声を待った。
「ハル?」
『ん?』
声だけで返事を返すと、スミレの腕が俺に伸び俺の胸に顔を埋め、ゆっくりと顔をあげた。
不意に目が合い、逸らすと「逸らさないで?」と強い口調で言われ戸惑った。
『……近すぎる』
「いいから、見て?」
ドキドキと心臓が騒ぎだし、スミレを見つめ返すと、ニッコリ笑い
「ハルと同じくらい好きだよ」
と言われ、涙が溢れ目を伏せたら怒られた。
「久し振りに晴斗に会った時、カッコよくなっててビックリした。
……私ずっと晴斗の気持ちに気づいてたよ?でも、一生懸命隠そうとしてたし、私もハルに気持ち知られたくなかったから……」
『全部バレてたんだ。』
「今だから言うけど、晴斗のファーストキスは私だよ?」
『へ?このタイミングで?』
「フフッ」と笑い「私のファーストも晴斗だよ」と悪戯に笑い「晴斗が寝てる時にこっそり……。でも、キスしてる所を秋に見つかっちゃって、すっごい恥ずかしかったけど」
『……なんで今?』
「晴斗がズルいから、仕返し!」
可愛すぎて、嬉しすぎて……ニヤケる。なんだこれ……。
ため息を吐き、スミレの肩に顔を埋め腰に腕を回すと、しばらく動けずにいた。
「晴斗?」
心配そうな声が降ってくる。
スミレからなのか俺からなのか、心臓の音が心地よいリズムを刻み顔をあげると唇が触れそうなくらい近距離にスミレがいた。
スミレのからだがピクリと動き、瞳が動揺していた。
「晴斗……」
吐息がくすぐったい。
『スミレ……キスしたい。ダメかな?』
「いつも勝手にするくせに……こんな時だけズル……んっ!」
待てずに唇を塞ぐと諦めたのか、回された手が俺の服をギュッとつかんだ。
その仕草に押さえていた理性が限界を超えた。
滑り込ませた舌がスミレを捉えると厭らしい声が吐息と共に漏れ出た。
「んぅっ……っん……ぁ……」
唇を重ねながらなんどもなんども好きだと呟いた。
スミレが苦しいと背中を叩くまで、止める事ができなかった。
「っ……はぁ、はぁっ……バカ」
ドキッとするほど色っぽい表情に目を逸らした。
『ごめん……つい』
腰が抜けたのか、俺にしがみつくスミレを座らせ壁にもたれながら、互いに落ち着くまで手を繋ぎ、一人余韻に浸っていた。
『……先生に言われたこと、破っちゃったな?』
「最初から守る気なんてなかったクセに……フフッ」
堰を切ったように笑うスミレにつられ俺も笑った。
おもしろい事なんてひとつもないのに、ホッとしたからかな?
『好きだよ。』
ずっと言えなかった分、たくさん伝えから。一生掛かっても言えそうにないスミレへの気持ち。
だって、やっと堂々と守れる。
彼女だと言える事が嬉しい反面、まだ実感が無い分半信半疑だけど、両想いだ!てっ子供みたいにはしゃげたらスミレは笑うかな?
目が合い照れるスミレを見ながら、顔を寄せるとピクッと肩が動いた。
「私も、好きだよ……」
付き合ってから、2度目のキスで少しだけ実感する。
顔を離したとき、胸元をなにかに叩かれた感触で指輪の存在を思いだした。
『今ならつけても似合うかな?』
ネックレスを外し、指輪を出すと、スミレも同じように浴衣の中から指輪を出した。
『スミレ、手かして』
差し出される手に笑い、左手の薬指にそっと嵌めた。
同じくスミレが俺の指に指輪を嵌めると、知らぬ間に止めていた息を吐き出した。
指輪を眺め嬉しそうに笑う横顔を見つめ頭を撫でた。
「晴斗、帰ろう?」
『うん。』
差し出された手を握り、来た道を戻った。
長い長い廊下と階段を歩きながら、今まで話せなかった分を埋めるようにお互いの事を話した。
──帰る間際に再度職員室に行くと、「まだいたのか!」と驚かれ、「危ないから早く帰れ!」と怒られてしまった。
その会話を、俺の後ろで聞き笑うスミレを引き出し『お疲れ様です』と会釈し扉を閉めた。
「晴斗の意地悪」
ムッとする表情に笑い『俺の彼女ですって紹介したの』と誇らしげに言うと、「バカ……」と照れてるのか怒っているのか、校舎を後にするまで口を聞いてもらえなかった。
会えない時間もあるしこの先何があるか分からないけど、その笑顔の隣で一緒に笑っているのが俺であれと強く願った──