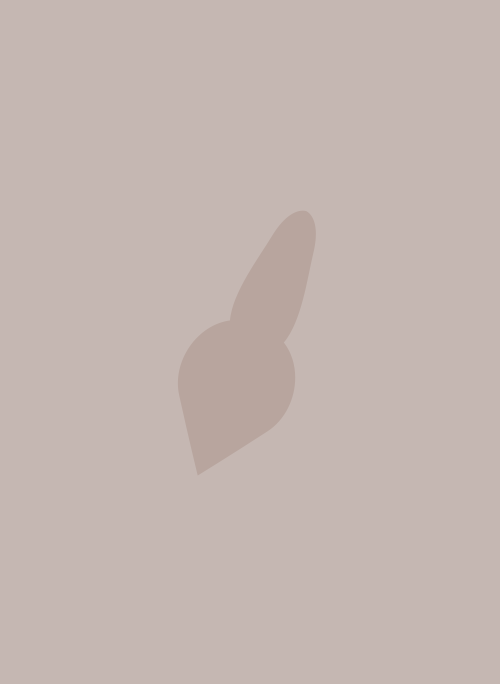街頭と月明かりだけが照らす道を学校へ向かって歩いた。
小さな物音にビクビクしながら歩くスミレが、驚いて俺の肩にぶつかっては離れてを繰り返す度に口許が緩んで仕方なかった。
『怖い?』
「ううん、大丈夫。晴斗が居るから……」
その言葉につい抱き締めてしまった。
「晴斗?」
不安そうな声にまた胸キュンとなる。
『大丈夫。俺がスミレを守るから。
絶対、って言えないほど弱いから、多分コテンパンにやられちゃうと思うけど。
守らせて?』
トントンっと背中を叩き『怖くなくなるおまじない。』そう言って離れた。
『……まだ、怖い?』
「ううん。」
恥ずかしそうに笑うスミレにつられ俺も笑った。髪型が崩れないようにそっと頭を撫で、少し先を手を引き歩いた。
誰もいない通学路を歩くのは初めてで、しかも夜に、なんて思っていたら子供みたいにワクワクしてきた。
そんな事をスミレに話したら、思いきり笑われた。
「男の子だね?」
『でも、こんな感情経験したことないから、くすぐったいかも』
「いつも秋がハシャいでたしね?」
『うん』
昔から秋が先にハシャグから、逆に冷静になってずっとハシャグ事ができなかった。
それは今も変わらなくて、今少しだけ秋の気持ちが分かった気がした。
「晴斗が制服着て歩いてる所見てみたいな……?」
『見てどうするの?』
「んー……哀しくなるのかな?」
遠くを見る瞳が切なくて、そんな顔をさせているのが俺だと思うと嬉しかった。
『制服着てるの見てるのに、哀しくなるの?』
「うん。だって、隣歩けないから。秋も東雲さんも晴斗の隣を歩けるのに、私にはそれができないから。」
『フッ、俺も同じこと考えてた。
スミレと同じ頃に生まれてたら、隣でまではいかないけど、側で見れたのになぁって……』
そしたら、同じ中学行って同じ高校受験したのにって、散々した妄想をスミレの口から聞く日が来るなんて。
「そっか」
『今一緒に歩いてる、じゃ意味ないよな?やっぱ制服着てないと』
「想像するから大丈夫。」
そう言って立ち止まるスミレは目を瞑った。
『スミレ?』
「朝、制服を着た晴斗が小雨が降る中この道を歩いてる。傘を差して、あくびしながら。」
『隣には誰かいる?』
「秋がいる……笑ってる。」
『その場所に、スミレは居る?』
「……居ない」
『「スミレ、置いてくぞ?!」って聞こえなかった?』
「フフッ、聞こえた……」
ニッコリ笑う頬に、涙が流れた。
その涙を拭うと、スミレが目を開けた。
「余計に哀しくなっちゃった……」
『おいで?』
腕を伸ばし微笑むと、コツンと胸に頭をつけるスミレの体を抱き締めた。
「晴斗はズルい……」
『そう?』
「ズルい。」
トントンと背中を叩きながら、二人の世界に浸っていた。
心の中では好きと言えるのに、また言えそうにないと、落ち着きを取り戻した俺の中から離れたスミレを見ながら思った。
『……行くか?』
「うん。」
再び歩き始め、改めて通学路を見渡して、こんなんだったっけ?と思ってしまう。
ただ学校と家を繋ぐ道としか考えてなかったから、改めてみるとこの道であってるのか不安になってしまう。
『初めて自分が通う道ちゃんと見た気がする。』
「あっという間だから、ちゃんと覚えておかないと」
『うん』
『スミレ、寒くない?』
「さっき晴斗に暖めてもらったから、大丈夫」
『あっ……そっか……』
キュンッとなる胸が早くなっていく。
心臓が煩いくらいに鼓動を打ち、煩悩が顔を出す。
それを消すため秋の話で気をそらす事にした。
『そういえば、秋がさ……──』
秋の話しや学校での出来事を話すと、スミレも大学での話をしてくれた。
友達の事、授業の話し、サークルであった事を聞いてる内、決まって出てくるいかにもスミレが好きでワザとふざけてるとしか思えない男の話が多すぎてヤキモチを妬いていると、案の定その男に告白をされたと言われ、『断ったんだろ?』と自分でも驚くような冷めた声に『ごめん』が掠れた。
「断ったよ?好きな人がいるからって言ったんだけど、そのあとも何度か告白された。」
『……』
「全部断ったけど、もう一度告白されたら付き合っちゃうかも?」
『…………だめ。なんて言える立場じゃないから……』
スミレの顔が見れない。
ズキズキ痛む胸が自分の不甲斐なさを笑ってるみたいで、涙がでた。
小さな物音にビクビクしながら歩くスミレが、驚いて俺の肩にぶつかっては離れてを繰り返す度に口許が緩んで仕方なかった。
『怖い?』
「ううん、大丈夫。晴斗が居るから……」
その言葉につい抱き締めてしまった。
「晴斗?」
不安そうな声にまた胸キュンとなる。
『大丈夫。俺がスミレを守るから。
絶対、って言えないほど弱いから、多分コテンパンにやられちゃうと思うけど。
守らせて?』
トントンっと背中を叩き『怖くなくなるおまじない。』そう言って離れた。
『……まだ、怖い?』
「ううん。」
恥ずかしそうに笑うスミレにつられ俺も笑った。髪型が崩れないようにそっと頭を撫で、少し先を手を引き歩いた。
誰もいない通学路を歩くのは初めてで、しかも夜に、なんて思っていたら子供みたいにワクワクしてきた。
そんな事をスミレに話したら、思いきり笑われた。
「男の子だね?」
『でも、こんな感情経験したことないから、くすぐったいかも』
「いつも秋がハシャいでたしね?」
『うん』
昔から秋が先にハシャグから、逆に冷静になってずっとハシャグ事ができなかった。
それは今も変わらなくて、今少しだけ秋の気持ちが分かった気がした。
「晴斗が制服着て歩いてる所見てみたいな……?」
『見てどうするの?』
「んー……哀しくなるのかな?」
遠くを見る瞳が切なくて、そんな顔をさせているのが俺だと思うと嬉しかった。
『制服着てるの見てるのに、哀しくなるの?』
「うん。だって、隣歩けないから。秋も東雲さんも晴斗の隣を歩けるのに、私にはそれができないから。」
『フッ、俺も同じこと考えてた。
スミレと同じ頃に生まれてたら、隣でまではいかないけど、側で見れたのになぁって……』
そしたら、同じ中学行って同じ高校受験したのにって、散々した妄想をスミレの口から聞く日が来るなんて。
「そっか」
『今一緒に歩いてる、じゃ意味ないよな?やっぱ制服着てないと』
「想像するから大丈夫。」
そう言って立ち止まるスミレは目を瞑った。
『スミレ?』
「朝、制服を着た晴斗が小雨が降る中この道を歩いてる。傘を差して、あくびしながら。」
『隣には誰かいる?』
「秋がいる……笑ってる。」
『その場所に、スミレは居る?』
「……居ない」
『「スミレ、置いてくぞ?!」って聞こえなかった?』
「フフッ、聞こえた……」
ニッコリ笑う頬に、涙が流れた。
その涙を拭うと、スミレが目を開けた。
「余計に哀しくなっちゃった……」
『おいで?』
腕を伸ばし微笑むと、コツンと胸に頭をつけるスミレの体を抱き締めた。
「晴斗はズルい……」
『そう?』
「ズルい。」
トントンと背中を叩きながら、二人の世界に浸っていた。
心の中では好きと言えるのに、また言えそうにないと、落ち着きを取り戻した俺の中から離れたスミレを見ながら思った。
『……行くか?』
「うん。」
再び歩き始め、改めて通学路を見渡して、こんなんだったっけ?と思ってしまう。
ただ学校と家を繋ぐ道としか考えてなかったから、改めてみるとこの道であってるのか不安になってしまう。
『初めて自分が通う道ちゃんと見た気がする。』
「あっという間だから、ちゃんと覚えておかないと」
『うん』
『スミレ、寒くない?』
「さっき晴斗に暖めてもらったから、大丈夫」
『あっ……そっか……』
キュンッとなる胸が早くなっていく。
心臓が煩いくらいに鼓動を打ち、煩悩が顔を出す。
それを消すため秋の話で気をそらす事にした。
『そういえば、秋がさ……──』
秋の話しや学校での出来事を話すと、スミレも大学での話をしてくれた。
友達の事、授業の話し、サークルであった事を聞いてる内、決まって出てくるいかにもスミレが好きでワザとふざけてるとしか思えない男の話が多すぎてヤキモチを妬いていると、案の定その男に告白をされたと言われ、『断ったんだろ?』と自分でも驚くような冷めた声に『ごめん』が掠れた。
「断ったよ?好きな人がいるからって言ったんだけど、そのあとも何度か告白された。」
『……』
「全部断ったけど、もう一度告白されたら付き合っちゃうかも?」
『…………だめ。なんて言える立場じゃないから……』
スミレの顔が見れない。
ズキズキ痛む胸が自分の不甲斐なさを笑ってるみたいで、涙がでた。