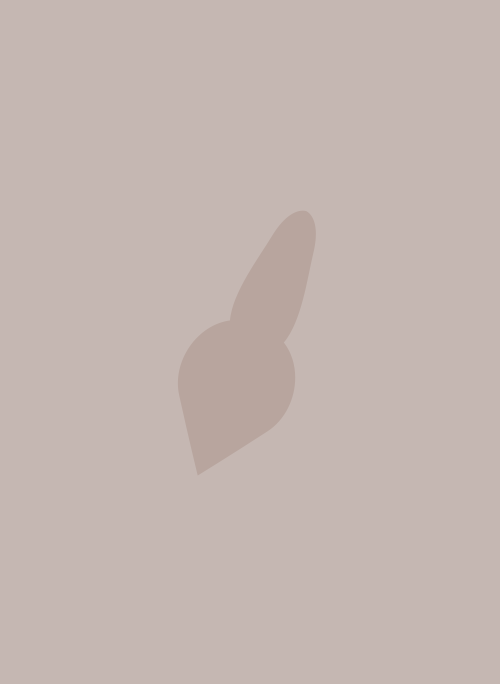着信音で分かる電話の音。
出たくないけど、スミレが早く出ろと胸を叩く。
「切れちゃうよ?」
『はぁー』
しぶしぶ電話に出ると、スミレから離れケータイを耳にあてた。
「もしもしハル? 仕度が間に合いそうだから準備かできたらそっち行くわ!」と言われ、素直に喜べない自分がいた。
『うん。じゃあまた後で……』
電話を切るとため息が漏れた。
東雲に会うのが何となく気まずい、会うのはあの日以来か……。どんな顔でどんな言葉をかけようか考えていると視界の中にスミレがはいった。
嬉しそうに指輪を眺めていいる姿をみた瞬間、何かが吹っ切れた気がした。
『それ、俺の分身だから。』
クスッと笑うと「秋なんて?」と訊いてきた。
『なんで秋だって思うの?』
「んー話し方?それに、晴斗が秋以外の人と話してるの見たことないから。」
にっこり笑うスミレをもう一度引き寄せ、今度は優しく抱き締めた。
『これから来るって……』
「今日の晴斗、なんか変だよ?何かあったの?」
『うん。ありすぎて困るくらい。
……東雲も一緒だって。』
「東雲さん?……あー!秋と一緒にいた?」
黙って頷くと、背中が暖かくなった。
背中を擦りながらの「大丈夫だよ」に少し泣きそうになる。
ドキドキするけど、安心する。
『ありがとう。そろそろ行くか!? こんな所見られたらまた秋に怒られる』
スミレはクスクス笑い「うん」と頷いた。
体を離すと、何度同じことを繰り返していたのか、浴衣の中に指輪を隠すスミレを見ながら微笑んでいると、「どうしたの?」と聞かれた。
『いや?ただ、嬉しいだけ』
──スミレの手を握り部屋を出ると、わざとゆっくり噛み締めるように階段を下りた。
リビングの手前で自然に離れる手を目で追い、友紀ちゃんの元へと駆け寄る後ろ姿を眺めた。
「晴斗、写真撮ろっ?!」
手招きに引き寄せられるようにスミレの隣に並んだ。
友紀ちゃんの「笑って」の声に無表情でいると、スミレが「ハル笑って」と大袈裟に笑って見せた。
それに釣られて笑った所を友紀ちゃんに撮られてしまった。
不思議と怒る気になれなくて、もう少しスミレとこうしてじゃれていたいと思った。
「久しぶりに見た、晴斗が笑ってる所。何十年ぶりしら?」
そう言った友紀ちゃんの目が潤んで見えた。
『……俺ってそんなに笑わないんだ。自分では笑ってるつもりなんだけどな?』
「スミレちゃんに感謝しないと」と笑った友紀ちゃんに、声には出さず“ごめん”と謝った。 知らぬ間に心配をかけていたことに、この時初めて気づいた。
それから程なく家のチャイムが鳴って、友紀ちゃんが玄関に向かう姿を複雑な気持ちで見ていた。
ドキドキと早まる鼓動が、逃げたくて逃げたくてドアを叩く自分のようで苦しくなった。
「大丈夫。深呼吸して?」
友紀ちゃんの「いらっゃい」の声が遠くに聞こえるほど、その言葉は一瞬にして俺を暖かく包んだ。
あれほど早かった鼓動が次第に穏やかになり、嘘のように呼吸が楽になる。
「晴斗は晴斗のままいればいいよ、だから大丈夫」
『ありがとう。』
スミレが背中を優しく叩く。
子供に戻ったみたみたいでなんだか照れ臭い。忘れていた子供の頃の思い出が引き出され、途端に懐かしくなる。
思えばスミレは子供の俺の不安を察知して、こうして宥めてくれていたっけ…?
──友紀ちゃんが戻ってきた後ろには、笑顔の秋と緊張している東雲が顔を出した。
出たくないけど、スミレが早く出ろと胸を叩く。
「切れちゃうよ?」
『はぁー』
しぶしぶ電話に出ると、スミレから離れケータイを耳にあてた。
「もしもしハル? 仕度が間に合いそうだから準備かできたらそっち行くわ!」と言われ、素直に喜べない自分がいた。
『うん。じゃあまた後で……』
電話を切るとため息が漏れた。
東雲に会うのが何となく気まずい、会うのはあの日以来か……。どんな顔でどんな言葉をかけようか考えていると視界の中にスミレがはいった。
嬉しそうに指輪を眺めていいる姿をみた瞬間、何かが吹っ切れた気がした。
『それ、俺の分身だから。』
クスッと笑うと「秋なんて?」と訊いてきた。
『なんで秋だって思うの?』
「んー話し方?それに、晴斗が秋以外の人と話してるの見たことないから。」
にっこり笑うスミレをもう一度引き寄せ、今度は優しく抱き締めた。
『これから来るって……』
「今日の晴斗、なんか変だよ?何かあったの?」
『うん。ありすぎて困るくらい。
……東雲も一緒だって。』
「東雲さん?……あー!秋と一緒にいた?」
黙って頷くと、背中が暖かくなった。
背中を擦りながらの「大丈夫だよ」に少し泣きそうになる。
ドキドキするけど、安心する。
『ありがとう。そろそろ行くか!? こんな所見られたらまた秋に怒られる』
スミレはクスクス笑い「うん」と頷いた。
体を離すと、何度同じことを繰り返していたのか、浴衣の中に指輪を隠すスミレを見ながら微笑んでいると、「どうしたの?」と聞かれた。
『いや?ただ、嬉しいだけ』
──スミレの手を握り部屋を出ると、わざとゆっくり噛み締めるように階段を下りた。
リビングの手前で自然に離れる手を目で追い、友紀ちゃんの元へと駆け寄る後ろ姿を眺めた。
「晴斗、写真撮ろっ?!」
手招きに引き寄せられるようにスミレの隣に並んだ。
友紀ちゃんの「笑って」の声に無表情でいると、スミレが「ハル笑って」と大袈裟に笑って見せた。
それに釣られて笑った所を友紀ちゃんに撮られてしまった。
不思議と怒る気になれなくて、もう少しスミレとこうしてじゃれていたいと思った。
「久しぶりに見た、晴斗が笑ってる所。何十年ぶりしら?」
そう言った友紀ちゃんの目が潤んで見えた。
『……俺ってそんなに笑わないんだ。自分では笑ってるつもりなんだけどな?』
「スミレちゃんに感謝しないと」と笑った友紀ちゃんに、声には出さず“ごめん”と謝った。 知らぬ間に心配をかけていたことに、この時初めて気づいた。
それから程なく家のチャイムが鳴って、友紀ちゃんが玄関に向かう姿を複雑な気持ちで見ていた。
ドキドキと早まる鼓動が、逃げたくて逃げたくてドアを叩く自分のようで苦しくなった。
「大丈夫。深呼吸して?」
友紀ちゃんの「いらっゃい」の声が遠くに聞こえるほど、その言葉は一瞬にして俺を暖かく包んだ。
あれほど早かった鼓動が次第に穏やかになり、嘘のように呼吸が楽になる。
「晴斗は晴斗のままいればいいよ、だから大丈夫」
『ありがとう。』
スミレが背中を優しく叩く。
子供に戻ったみたみたいでなんだか照れ臭い。忘れていた子供の頃の思い出が引き出され、途端に懐かしくなる。
思えばスミレは子供の俺の不安を察知して、こうして宥めてくれていたっけ…?
──友紀ちゃんが戻ってきた後ろには、笑顔の秋と緊張している東雲が顔を出した。