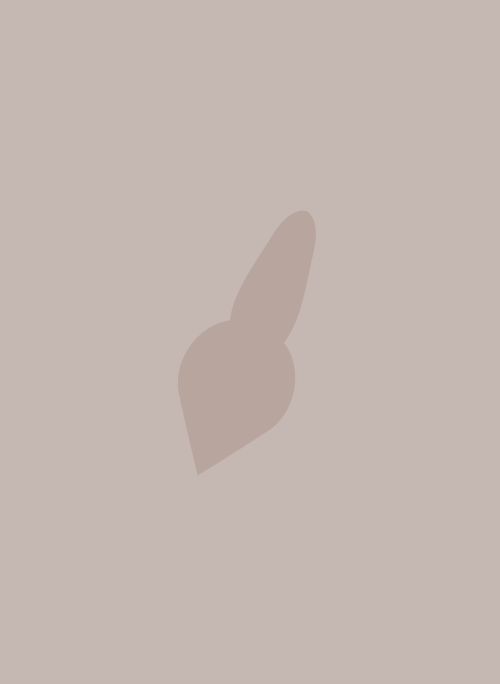──花火大会当日。
街はいつも以上に空気が騒がしく、空は3日前から青空が続いていた。
ベランダの手すりに寄りかかりボーッと空を眺めていると、ノック音が聞こえた。
『はい?』
ドアが開き、顔を出したのは秋だった。
「よっ!!」
軽く手を上げ入ってきた秋は、それだけ言うとベッドに腰かけた。
『どうした?』
ソワソワしてる秋に声を掛けると、「うん……」と言ったあと深く深呼吸をする。
「はぁ~緊張する~」
胸元を擦りながら目を閉じる秋が突然真剣な声で「俺さ……」と切り出した。
「告白しようと思うんだ、東雲に。断られる前提だけど、それでもいいかなって。
告白し続けてたらいつかは叶うかなって?」
『そっか』
秋がベランダに顔をだし眩しそうに空を見上げた。
不意に変わる真剣な横顔と告白の文字が頭の中を一杯にした。
俺もスミレに気持ちを伝えようって考えて勇気がないって逃げてきたけど、秋がするならじゃあ俺も、なんて言えるわけないし。って結局また言い訳してる......
『がんばれよ』なんて言える立場じゃないけど、それ以外の言葉が見つからなかった。
“お前なら大丈夫”とか“絶対オーケーしてくれるって”とか言ってみたいけど、俺の台詞じゃない事くらい分かってる。
「……メールしてても、電話しててもたぶん俺だけなんだ、ドキドキしたり嬉しくなるの。 晴斗の話しに付き合って、東雲が喜んでるならいいかなって思ってたけど、正直もう限界でさ……。
なのにアイツの中にはまだお前がいて、俺が入る隙間なんかないっていうか......
スミレの事で悩んでるお前見てるとイライラする。 重症だな」
そう言って力なく笑って手摺に背中を預けた。
『……。』
「でも、最近東雲が前ほど晴斗晴斗言わなくなってさ?なんか、逆に落ち着かなくて。そんな時に駅前でのコトが合って、二人の姿見つけたときマジで心臓止まるかと思った。
隣見たら東雲も気づいててさ、晴斗だって知って驚いてたけど、こっちが躊躇うほど冷静でさ?
スミレと話してるときが一番怖かった。
何もできない自分と、晴斗の態度にもムカついた。」
『ごめん。でも、曖昧な態度取ってたらお互い進めないし。あの状況じゃ話さない方が不自然だったし
東雲にはスミレの事話した事あるから、多分名前聞いたとき気づいたと思う。』
「そっか……っていうか、普段冷静な顔で俺とスミレが話してるの見てて晴斗は嫉妬しないのかな~?って。
ただ顔に出ないだけにしてもすごいなって。そんな事ばっかり考えてる。
そういや、最近やたらと昔の事思い出すの!んで、そういえばあの時......って事が意外と多くて。
今もそこは変わらないんだなって……ハハハッ」
秋とこんな話をするようになったのも、東雲がきっかけになってるんだと思うと、不思議だけど──
『どんな気持ちか分からないけど、俺は東雲よりも秋の事知らないし、秋より東雲の事知らない。幼馴染みなのに笑えるよな?
でも、東雲は「秋がいたから告白しようって思えた」って言ってたから、東雲の中にお前はいるよ。』
うまく言えないけど、ちゃんと伝わったよな?
「そっか。」
『あと……俺が嫉妬したのは、秋がスミレと話してる時じゃなくて、東雲が俺より秋の事知ってたときだよ。』
「なんだそれ?」
秋の肩がピクリと動き小さく笑った。
東雲の中から俺の存在を消すのは時間が掛かるだろうけど、あの二人なら大丈夫だろ?なんて思えたのは、下に小さな人影が見えたからかもしれない。
『来たみたいだぞ?』
「え?」
『東雲。』
俺の視線の先を辿り、急に焦りだす秋は「じゃあ、帰るわ」と不自然な笑みを残し、足早に部屋を出ていった。
──バタバタと階段を下りる音が消えると今度は「おじゃましました~」の声が玄関を抜け二階の窓にまで届いた。
出てきた秋が俺を見上げ笑顔で手を振った。
街はいつも以上に空気が騒がしく、空は3日前から青空が続いていた。
ベランダの手すりに寄りかかりボーッと空を眺めていると、ノック音が聞こえた。
『はい?』
ドアが開き、顔を出したのは秋だった。
「よっ!!」
軽く手を上げ入ってきた秋は、それだけ言うとベッドに腰かけた。
『どうした?』
ソワソワしてる秋に声を掛けると、「うん……」と言ったあと深く深呼吸をする。
「はぁ~緊張する~」
胸元を擦りながら目を閉じる秋が突然真剣な声で「俺さ……」と切り出した。
「告白しようと思うんだ、東雲に。断られる前提だけど、それでもいいかなって。
告白し続けてたらいつかは叶うかなって?」
『そっか』
秋がベランダに顔をだし眩しそうに空を見上げた。
不意に変わる真剣な横顔と告白の文字が頭の中を一杯にした。
俺もスミレに気持ちを伝えようって考えて勇気がないって逃げてきたけど、秋がするならじゃあ俺も、なんて言えるわけないし。って結局また言い訳してる......
『がんばれよ』なんて言える立場じゃないけど、それ以外の言葉が見つからなかった。
“お前なら大丈夫”とか“絶対オーケーしてくれるって”とか言ってみたいけど、俺の台詞じゃない事くらい分かってる。
「……メールしてても、電話しててもたぶん俺だけなんだ、ドキドキしたり嬉しくなるの。 晴斗の話しに付き合って、東雲が喜んでるならいいかなって思ってたけど、正直もう限界でさ……。
なのにアイツの中にはまだお前がいて、俺が入る隙間なんかないっていうか......
スミレの事で悩んでるお前見てるとイライラする。 重症だな」
そう言って力なく笑って手摺に背中を預けた。
『……。』
「でも、最近東雲が前ほど晴斗晴斗言わなくなってさ?なんか、逆に落ち着かなくて。そんな時に駅前でのコトが合って、二人の姿見つけたときマジで心臓止まるかと思った。
隣見たら東雲も気づいててさ、晴斗だって知って驚いてたけど、こっちが躊躇うほど冷静でさ?
スミレと話してるときが一番怖かった。
何もできない自分と、晴斗の態度にもムカついた。」
『ごめん。でも、曖昧な態度取ってたらお互い進めないし。あの状況じゃ話さない方が不自然だったし
東雲にはスミレの事話した事あるから、多分名前聞いたとき気づいたと思う。』
「そっか……っていうか、普段冷静な顔で俺とスミレが話してるの見てて晴斗は嫉妬しないのかな~?って。
ただ顔に出ないだけにしてもすごいなって。そんな事ばっかり考えてる。
そういや、最近やたらと昔の事思い出すの!んで、そういえばあの時......って事が意外と多くて。
今もそこは変わらないんだなって……ハハハッ」
秋とこんな話をするようになったのも、東雲がきっかけになってるんだと思うと、不思議だけど──
『どんな気持ちか分からないけど、俺は東雲よりも秋の事知らないし、秋より東雲の事知らない。幼馴染みなのに笑えるよな?
でも、東雲は「秋がいたから告白しようって思えた」って言ってたから、東雲の中にお前はいるよ。』
うまく言えないけど、ちゃんと伝わったよな?
「そっか。」
『あと……俺が嫉妬したのは、秋がスミレと話してる時じゃなくて、東雲が俺より秋の事知ってたときだよ。』
「なんだそれ?」
秋の肩がピクリと動き小さく笑った。
東雲の中から俺の存在を消すのは時間が掛かるだろうけど、あの二人なら大丈夫だろ?なんて思えたのは、下に小さな人影が見えたからかもしれない。
『来たみたいだぞ?』
「え?」
『東雲。』
俺の視線の先を辿り、急に焦りだす秋は「じゃあ、帰るわ」と不自然な笑みを残し、足早に部屋を出ていった。
──バタバタと階段を下りる音が消えると今度は「おじゃましました~」の声が玄関を抜け二階の窓にまで届いた。
出てきた秋が俺を見上げ笑顔で手を振った。