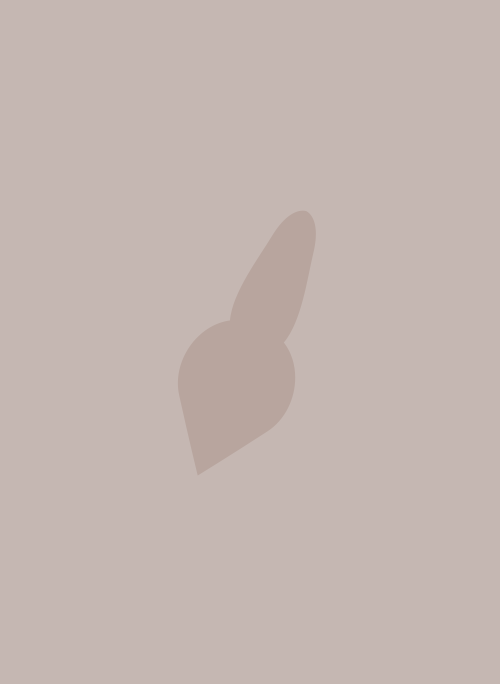ため息の後雨の中に傘を開くと、スミレは嬉しそうに傘に入った。
『もう少しこっち。濡れるから。』
「うん」
何気ない会話を繰り返し、またスミレの事を知っていく。何が好きで、何が嫌いか。
子供の頃と変わらない食の好みも、大人になって少しだけ変わっていた。
改めてな事ばかりを質問しされながら、バス停までゆっくり歩いた。
穏やかだった雨は次第に激しくなり、傘に落ちる雨音がウルサいくらいに大きくなった。
『……雨の匂い』
濡れたアスファルトなのか、土の匂いなのか。舞い上がる風に乗って鼻先へ届く匂いが昔から好きで。昔、雨の匂いは虹の匂いだと聞かされてから、今でも嘘を信じてたりする。
「虹の匂い。」
その嘘を教えてくれたのがスミレじゃなかったら、嫌いになっていたかもしれない。
「本格的に降って来ちゃったね?!」
『だな』
無意識に聞こえるようにと互いに耳元に顔を寄せ話してるせいか、いつもよりスミレを近く感じた。
歩みを早め、バス停までスミレが濡れないよう傘を傾け歩く。
「晴斗、肩濡れてる」
そう言ってまた近くなるスミレの身体がぶつかる度、肩が熱くなるのを感じた。
『俺は濡れても大丈夫だから』
「ハルが風邪引いたら私が困る」
『……俺は、嬉しいかも』
「どうして?!」
『スミレがずっと側にいてくれるなら、風邪引きたいなって』
スミレは顔を赤らめ俯いてしまう。
その横顔を何度見てきただろう?
浅く息を吐き、濡れた靴先を見つめた。
『もう少しこっち。濡れるから。』
「うん」
何気ない会話を繰り返し、またスミレの事を知っていく。何が好きで、何が嫌いか。
子供の頃と変わらない食の好みも、大人になって少しだけ変わっていた。
改めてな事ばかりを質問しされながら、バス停までゆっくり歩いた。
穏やかだった雨は次第に激しくなり、傘に落ちる雨音がウルサいくらいに大きくなった。
『……雨の匂い』
濡れたアスファルトなのか、土の匂いなのか。舞い上がる風に乗って鼻先へ届く匂いが昔から好きで。昔、雨の匂いは虹の匂いだと聞かされてから、今でも嘘を信じてたりする。
「虹の匂い。」
その嘘を教えてくれたのがスミレじゃなかったら、嫌いになっていたかもしれない。
「本格的に降って来ちゃったね?!」
『だな』
無意識に聞こえるようにと互いに耳元に顔を寄せ話してるせいか、いつもよりスミレを近く感じた。
歩みを早め、バス停までスミレが濡れないよう傘を傾け歩く。
「晴斗、肩濡れてる」
そう言ってまた近くなるスミレの身体がぶつかる度、肩が熱くなるのを感じた。
『俺は濡れても大丈夫だから』
「ハルが風邪引いたら私が困る」
『……俺は、嬉しいかも』
「どうして?!」
『スミレがずっと側にいてくれるなら、風邪引きたいなって』
スミレは顔を赤らめ俯いてしまう。
その横顔を何度見てきただろう?
浅く息を吐き、濡れた靴先を見つめた。