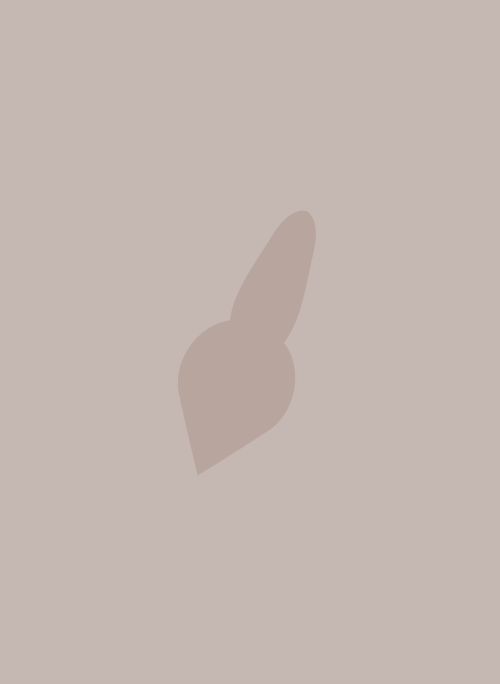放課後、人もまばらな教室を出た時、「途中まで送れよ」と言う秋に付き合い歩いていると、「無理すんなよ?」と声を掛けられた。
『うん』
「ハァー俺関係ねーのに、何でこんなドキドキすんだろ」
不安そうな表情を浮かべ胸元をさする秋に、なんて言えばいいのか分からず、秋には関係の無いことまで話していた。
『東雲にちゃんと返事しようと思って、放課後残って欲しいってメモ渡したんだ……お前がいないときに』
「なに、今更後悔?」
『……少しだけ。秋が手紙すり替えなかったら、こんなに気になったりしなかったのに。』
「もしかして……好きになったとか?」
『それはねぇよ。お前が変な小細工するから、無駄に悩む羽目になったんだよ』
「ああでもしない限り手紙読んでくれないと思ったから、東雲の気持ち、お前にはちゃんと知ってて欲しくて……」
『伝わってるよ、痛いほど』
相手の傷つく顔を見るために、俺はまた来た道を戻らなければならないのかと思うと、足が重い。
「じゃ、頑張れよ!」
そう言った顔に笑顔は無く、真剣な瞳がまっすぐに俺を捉えていた。
『ごめんな』
俺は今から、お前が好きな子を傷つけに行く。頑張れの言葉がこんなに重たいなんて思わなかった。
──秋の姿が見えなくなるまで見送ると、ゆっくり来た道を戻った。
『うん』
「ハァー俺関係ねーのに、何でこんなドキドキすんだろ」
不安そうな表情を浮かべ胸元をさする秋に、なんて言えばいいのか分からず、秋には関係の無いことまで話していた。
『東雲にちゃんと返事しようと思って、放課後残って欲しいってメモ渡したんだ……お前がいないときに』
「なに、今更後悔?」
『……少しだけ。秋が手紙すり替えなかったら、こんなに気になったりしなかったのに。』
「もしかして……好きになったとか?」
『それはねぇよ。お前が変な小細工するから、無駄に悩む羽目になったんだよ』
「ああでもしない限り手紙読んでくれないと思ったから、東雲の気持ち、お前にはちゃんと知ってて欲しくて……」
『伝わってるよ、痛いほど』
相手の傷つく顔を見るために、俺はまた来た道を戻らなければならないのかと思うと、足が重い。
「じゃ、頑張れよ!」
そう言った顔に笑顔は無く、真剣な瞳がまっすぐに俺を捉えていた。
『ごめんな』
俺は今から、お前が好きな子を傷つけに行く。頑張れの言葉がこんなに重たいなんて思わなかった。
──秋の姿が見えなくなるまで見送ると、ゆっくり来た道を戻った。