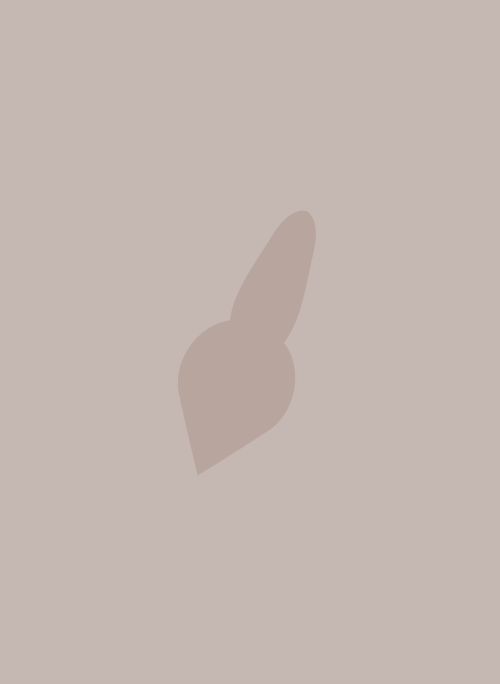「私は大丈夫だから、気にしないで食べて?」
『いや、俺が大丈夫じゃないし。……食べ終わるまであっちで待っててくれない?』
ソファーを指差し言うと、「邪魔してないのに……」と言いながらも素直に従うスミレが可愛くて、緩んだ顔を背中に向けた。
──その後、背後からの視線を感じながら、漸く食べ終えると、食器を片付けながらスミレに声を掛けた。
『終わったよ?』
「遅い!」
何故か怒られ、苦笑した。
『まだ時間あるし、そんな急がなくても』
時計を見ながら言うと「今、めんどくさいって思ったでしょ!?」と唐突に言われ目が点になりそうだった。
『ハァー……』
俯き拗ねるスミレに近づき、つむじを眺めながら(可愛すぎだ、バカ……)と心の中で呟いた。
顔を上げたスミレの瞳はまっすぐに俺だけを映し、小さな唇が俺の名前を呼ぶ。
『うっ……可愛すぎる』
触れたい、キスしたい、抱きしめたい。
そんな衝動に駆られながら、呟いた声はハッキリと伝わってしまい
「えっ?!」
動揺する目が泳ぎ、顔も耳も首も見る間に赤く染まっていった。
『っ・・・ごめん。
俺やっぱ、スミレとは出掛けたくないかも』
「え?」
不安になる目に涙が溜まり、零れる前に今想ってる事を素直に伝えた。
『だって……俺以外の奴がスミレの事見るの耐えられないし。
ワガママなのも身勝手なのもわかってるけど。そんな事想像しただけで、この辺がモヤモヤする……』
胸をさすりながら、自分の言動にまるで告白みたいだと苦笑した。
『冷静でいるのも大変なんだよ……』
告白めいたことを言ってしまったと気づいたのは、言い終えて妙な沈黙ができた時だった。
ワザとらしくタメ息を吐き、視線を逸らすと、恥ずかしさをごまかす為背を向け、出掛ける準備をするよう言い残しリビングを出た。
『いや、俺が大丈夫じゃないし。……食べ終わるまであっちで待っててくれない?』
ソファーを指差し言うと、「邪魔してないのに……」と言いながらも素直に従うスミレが可愛くて、緩んだ顔を背中に向けた。
──その後、背後からの視線を感じながら、漸く食べ終えると、食器を片付けながらスミレに声を掛けた。
『終わったよ?』
「遅い!」
何故か怒られ、苦笑した。
『まだ時間あるし、そんな急がなくても』
時計を見ながら言うと「今、めんどくさいって思ったでしょ!?」と唐突に言われ目が点になりそうだった。
『ハァー……』
俯き拗ねるスミレに近づき、つむじを眺めながら(可愛すぎだ、バカ……)と心の中で呟いた。
顔を上げたスミレの瞳はまっすぐに俺だけを映し、小さな唇が俺の名前を呼ぶ。
『うっ……可愛すぎる』
触れたい、キスしたい、抱きしめたい。
そんな衝動に駆られながら、呟いた声はハッキリと伝わってしまい
「えっ?!」
動揺する目が泳ぎ、顔も耳も首も見る間に赤く染まっていった。
『っ・・・ごめん。
俺やっぱ、スミレとは出掛けたくないかも』
「え?」
不安になる目に涙が溜まり、零れる前に今想ってる事を素直に伝えた。
『だって……俺以外の奴がスミレの事見るの耐えられないし。
ワガママなのも身勝手なのもわかってるけど。そんな事想像しただけで、この辺がモヤモヤする……』
胸をさすりながら、自分の言動にまるで告白みたいだと苦笑した。
『冷静でいるのも大変なんだよ……』
告白めいたことを言ってしまったと気づいたのは、言い終えて妙な沈黙ができた時だった。
ワザとらしくタメ息を吐き、視線を逸らすと、恥ずかしさをごまかす為背を向け、出掛ける準備をするよう言い残しリビングを出た。