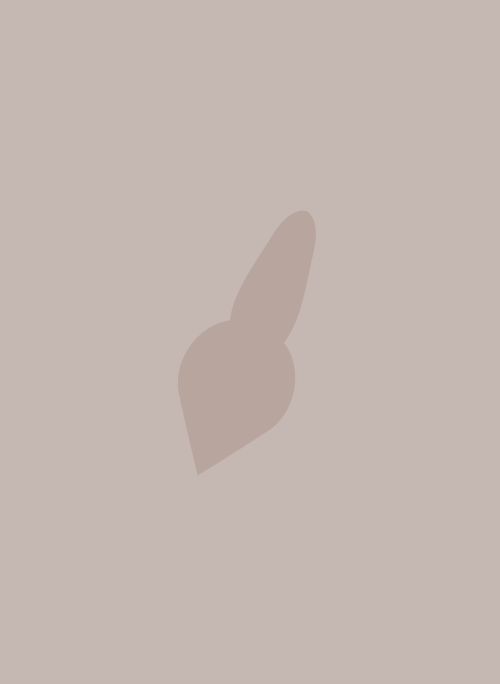『ハァ……分かったよ』
タオルケットを持ち上げ、ニコニコしてるスミレの頬にはまだ涙の跡が残っていた。
『もう少しそっち寄って』
壁際にそれるスミレとの間を開け、自分の腕を枕代わりに頭の下に敷くと、仰向けのまま目を閉じた。
「呆れた?」
『なんで?』
「子供たいなこと言うから」
俺には嬉しい事だって、スミレには黙っておこう。言ったら二度と見せてくれないだろうから
『呆れてるように見える?』
「暗くて分かんない」
『そっか、よかった』
なんとなく目を開けると、また服の裾をつかまれた気がした。
『眠れないか?』
スミレの方に寝返りを打つと、「うん」と声がした。
『……手繋ぐ?』
「手じゃなくて、もう少し近くにいちゃ駄目?」
『どのくらい近く?』
「腕の中に入る距離……?」
『キスするかも』
「……」
『嫌だろ、だから手で我慢して?』
「嫌じゃないから、近くがいい」
珍しくワガママを言うスミレに根負けした俺は、『わかった』と布団を持ち上げた。素直に近寄ってくるスミレが俺の胸に頭を寄せ背中に腕を回した。
『……近すぎる』
「安心する」
俺は全然安心出来ない。
消し去った煩悩が俺のなかで顔を覗かせる。
俺の理性、いつまで保つかな?っつうか今も結構、危なかったりして……
『って、寝てるし。』
考え事をしてる間に眠ってしまったスミレの寝息を聞きながら、髪を撫でているうち、ゆっくりと眠気に誘われ気が薄れる前に『おやすみ……』と声をかけた。
タオルケットを持ち上げ、ニコニコしてるスミレの頬にはまだ涙の跡が残っていた。
『もう少しそっち寄って』
壁際にそれるスミレとの間を開け、自分の腕を枕代わりに頭の下に敷くと、仰向けのまま目を閉じた。
「呆れた?」
『なんで?』
「子供たいなこと言うから」
俺には嬉しい事だって、スミレには黙っておこう。言ったら二度と見せてくれないだろうから
『呆れてるように見える?』
「暗くて分かんない」
『そっか、よかった』
なんとなく目を開けると、また服の裾をつかまれた気がした。
『眠れないか?』
スミレの方に寝返りを打つと、「うん」と声がした。
『……手繋ぐ?』
「手じゃなくて、もう少し近くにいちゃ駄目?」
『どのくらい近く?』
「腕の中に入る距離……?」
『キスするかも』
「……」
『嫌だろ、だから手で我慢して?』
「嫌じゃないから、近くがいい」
珍しくワガママを言うスミレに根負けした俺は、『わかった』と布団を持ち上げた。素直に近寄ってくるスミレが俺の胸に頭を寄せ背中に腕を回した。
『……近すぎる』
「安心する」
俺は全然安心出来ない。
消し去った煩悩が俺のなかで顔を覗かせる。
俺の理性、いつまで保つかな?っつうか今も結構、危なかったりして……
『って、寝てるし。』
考え事をしてる間に眠ってしまったスミレの寝息を聞きながら、髪を撫でているうち、ゆっくりと眠気に誘われ気が薄れる前に『おやすみ……』と声をかけた。