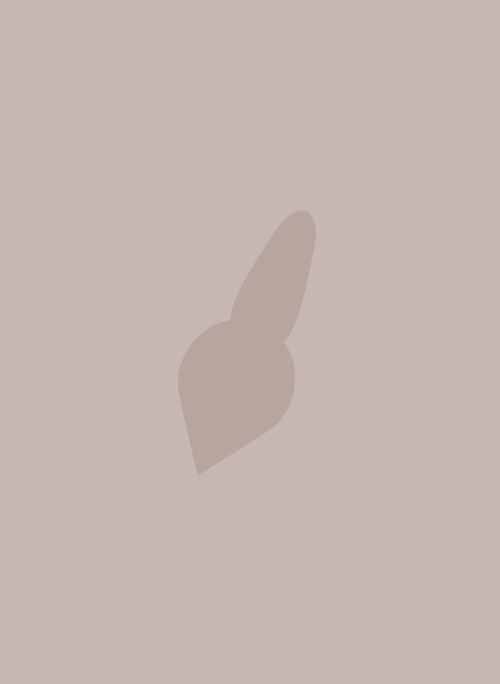「気に入った?」
『……はい。』
「それはよかった。」
『一人だと入りづらいですけど……。』
「外観があれだから、男の人は特に入り辛いかもね?
じゃあ、慣れるまで私が一緒に来てあげる。」
『おまけ、がほしいからですか?』
「あたり~」
ニコニコと嬉しそうに笑う顔がスミレに似ていて、やり取りを思い出して胸が切なくなった。
「お待たせ致しました。」
そう言って目の前に出されたのは、真っ白なカップの中で堂々としているブラックコーヒーだった。
隣を見ると、冷えたカフェオレのグラスがうっすらと汗をかき始めている。
『いただきます。』
湯気立つコーヒーの香りに惹かれるように、そっと飲み口を唇にあてた。
少し口に含んだだけでおいしいと出かかったのは初めてだった。
苦いのに甘い……
「いかがですか?」
自信ありげに笑みを浮かべるマスターに素直に『おいしいです』と答えた。
『苦いのに甘くて……すごく美味しいです。』
素直に思ったことを伝えると、マスターは微笑んだ。
「それはよかった。」
それだけ言うと、僕たちに背を向け手際よく材料を切っていく。
「ここのが一番おいしいから」
と頬杖を付きマスターの背中を見つめている先生は楽しそうに見えた。
『先生……楽しいですか?』
なぜかそんなことを聞いていた。
「楽しいわよ?それなりに。
大変なこともあるけど、それ含めての仕事だし。」
突然の質問に驚く事なく淡々と話すとコーヒーを飲み「君は?」と振り向いた。
『僕ですか?』
「楽しい?」
その言葉と聞くと、飴を思い出す。
思い出す度に頭の中で答えてきたけど、今は、わからない。
楽しいのか、つまらないのか。
答えがその2択しかないのなら、どちらでもない答えを示すだろう。
『苦しい……ですかね。
学校は前より楽しいです』
「苦しい、か……そうだよね。じゃなかったら、雨の中傘も差さず突っ立てたりしないものねぇ」
『……先生、雨って好きですか?』
「雨って、降ってくる雨?」
コクりと頷く。
「日によって違うから、どう言ったらいいのか。でも、嫌いじゃないかも。」
『そうですか。僕は、今日の雨が一番好きです。泣きやすいから。
……笑いたいなら笑ってください。』
「私も泣きたい時散歩したりするから、気持ちわかるな。」
『……よかった。』
先生はフフッと笑って、マスターの背中を眺め「拓海がここに来たがらない理由教えてあげようか?」といった。
『聞いてほしいなら、聞きますけど。』
先生はまたフフッと笑って、「私がマスターと仲がいいから。焼き餅じゃないけど、マスター大人だから自分が子供に見えたのかなって。
喧嘩する度マスターが出てくるし……私が好きなのはマスターじゃないのにね?」
瞼を伏せ、力なく笑う先生に『ちゃんと言ってあげないからですよ。』と自分に言い聞かせるように言った。
「厳しいんだね?」
急にマスターの声がし顔を向けると、にっこり笑い目の前にオムライスを置いた。
「陽向と拓海くんの事はある程度知っていたけど、俺の存在がふたりの中を引き離してまっているんだとしたら、悪いことをしたね?」
「マスターのせいじゃないよ。」
そう言ってオムライスを食べ始める。
『これでも深刻なんですよ?』
「拓海、なんか言ってた?」
『なにも。でも、見てればわかります。
これでも、友達なので……。』
「そっか……やっぱり、おいしい」
「冷めないうちに召し上がれ」
マスターの声に頷きスプーンを手にした。
『いただきます……』
「君はおもしろい子だね」
『僕ですか?』
「そう、きみ。
あんな外装で入り辛いかもしれないけど、また来てくれるかな?」
マスターは優しく微笑み、僕の目を真っ直ぐ見た。
『あ、はい……。』
「次は君の食べたいものを作ってあげるよ」
『は、はい。考えておきます。』
またドキッとしてしまった。
大人の色気なのか、余裕の笑みが男から見てもカッコいい。
その後、オムライスを食べながらマスターや先生の話を聞いていた。
『──ごちそうさまでした。』
店を出たのは夜だった。
友紀ちゃんに電話をかけ、先生に途中まで見送られ家に帰ると、スミレが玄関の外でに立っていた。
『……はい。』
「それはよかった。」
『一人だと入りづらいですけど……。』
「外観があれだから、男の人は特に入り辛いかもね?
じゃあ、慣れるまで私が一緒に来てあげる。」
『おまけ、がほしいからですか?』
「あたり~」
ニコニコと嬉しそうに笑う顔がスミレに似ていて、やり取りを思い出して胸が切なくなった。
「お待たせ致しました。」
そう言って目の前に出されたのは、真っ白なカップの中で堂々としているブラックコーヒーだった。
隣を見ると、冷えたカフェオレのグラスがうっすらと汗をかき始めている。
『いただきます。』
湯気立つコーヒーの香りに惹かれるように、そっと飲み口を唇にあてた。
少し口に含んだだけでおいしいと出かかったのは初めてだった。
苦いのに甘い……
「いかがですか?」
自信ありげに笑みを浮かべるマスターに素直に『おいしいです』と答えた。
『苦いのに甘くて……すごく美味しいです。』
素直に思ったことを伝えると、マスターは微笑んだ。
「それはよかった。」
それだけ言うと、僕たちに背を向け手際よく材料を切っていく。
「ここのが一番おいしいから」
と頬杖を付きマスターの背中を見つめている先生は楽しそうに見えた。
『先生……楽しいですか?』
なぜかそんなことを聞いていた。
「楽しいわよ?それなりに。
大変なこともあるけど、それ含めての仕事だし。」
突然の質問に驚く事なく淡々と話すとコーヒーを飲み「君は?」と振り向いた。
『僕ですか?』
「楽しい?」
その言葉と聞くと、飴を思い出す。
思い出す度に頭の中で答えてきたけど、今は、わからない。
楽しいのか、つまらないのか。
答えがその2択しかないのなら、どちらでもない答えを示すだろう。
『苦しい……ですかね。
学校は前より楽しいです』
「苦しい、か……そうだよね。じゃなかったら、雨の中傘も差さず突っ立てたりしないものねぇ」
『……先生、雨って好きですか?』
「雨って、降ってくる雨?」
コクりと頷く。
「日によって違うから、どう言ったらいいのか。でも、嫌いじゃないかも。」
『そうですか。僕は、今日の雨が一番好きです。泣きやすいから。
……笑いたいなら笑ってください。』
「私も泣きたい時散歩したりするから、気持ちわかるな。」
『……よかった。』
先生はフフッと笑って、マスターの背中を眺め「拓海がここに来たがらない理由教えてあげようか?」といった。
『聞いてほしいなら、聞きますけど。』
先生はまたフフッと笑って、「私がマスターと仲がいいから。焼き餅じゃないけど、マスター大人だから自分が子供に見えたのかなって。
喧嘩する度マスターが出てくるし……私が好きなのはマスターじゃないのにね?」
瞼を伏せ、力なく笑う先生に『ちゃんと言ってあげないからですよ。』と自分に言い聞かせるように言った。
「厳しいんだね?」
急にマスターの声がし顔を向けると、にっこり笑い目の前にオムライスを置いた。
「陽向と拓海くんの事はある程度知っていたけど、俺の存在がふたりの中を引き離してまっているんだとしたら、悪いことをしたね?」
「マスターのせいじゃないよ。」
そう言ってオムライスを食べ始める。
『これでも深刻なんですよ?』
「拓海、なんか言ってた?」
『なにも。でも、見てればわかります。
これでも、友達なので……。』
「そっか……やっぱり、おいしい」
「冷めないうちに召し上がれ」
マスターの声に頷きスプーンを手にした。
『いただきます……』
「君はおもしろい子だね」
『僕ですか?』
「そう、きみ。
あんな外装で入り辛いかもしれないけど、また来てくれるかな?」
マスターは優しく微笑み、僕の目を真っ直ぐ見た。
『あ、はい……。』
「次は君の食べたいものを作ってあげるよ」
『は、はい。考えておきます。』
またドキッとしてしまった。
大人の色気なのか、余裕の笑みが男から見てもカッコいい。
その後、オムライスを食べながらマスターや先生の話を聞いていた。
『──ごちそうさまでした。』
店を出たのは夜だった。
友紀ちゃんに電話をかけ、先生に途中まで見送られ家に帰ると、スミレが玄関の外でに立っていた。