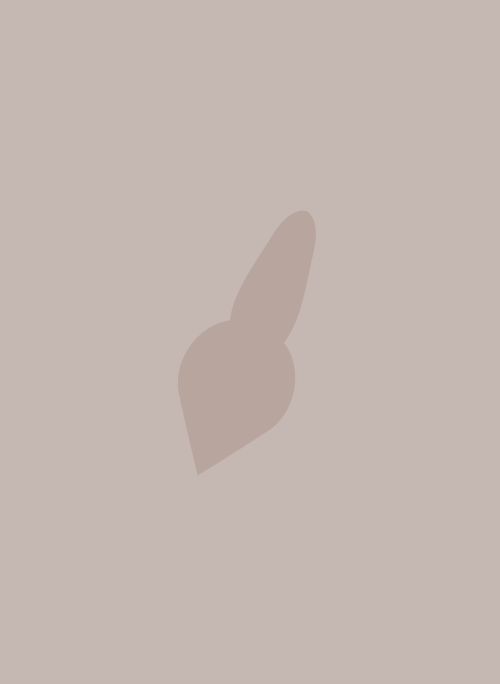「俺から聞いてみようか?」
『何を?』
「避けてる理由」
『……いいよ。』
「迷惑かけたくないって思ってるなら間違いだからな?」
『そうじゃなくて、本人の口から直接聞くまで待とうかなって?
いつか話してくれるかもしれないし。』
「ハル……それ花火に間に合わないと思う」
苦笑しながらも心配してるのが伝わってくるから、弱った涙腺から涙が出そうだった。
『確かに。フッ……』
「やっと笑った」
『ごめん』
ごめんって言わないようにしようって決めたのに、こんな簡単に破れちゃうんだ……。
「あっ!ケータイは?
メールなら答えてれくるんじゃね?」
『……メールは無視された。試しに送ってみたけど、まだ返って来てない。』
「そっか。晴斗さ、スミレになにしたの?
ずっと気になってたんだけど……」
『言わなきゃダメ?』
「話したくないならこれ以上は聞かないけどさ、原因がわからないから。
晴斗のとった事でなのか、スミレ自身の問題なのか……やっぱり話してみないと」
『なにか話すキッカケがあればいいんだけど……』
秋の言う通りだとしたらやっぱり話さないと。
「きっかけか……」
そう呟き黙ってしまった。
『始めはまだよくて「おはよう」とか「おやすみ」以外にも話してくれてたんだけど、だんだん話してくれなくなって、スミレの顔見るのが辛くて……。
夕食の時間が憂鬱で』
「そっか。」
『こんな話聞きに来たんじゃないのに、付き合わせてごめん。』
「いいよ別に。話したら少しは楽になると思うし。」
『ありがとう。』
秋はニッコリ笑って窓に視線を移した。
なにかを考えてる秋は、時折難しそうな顔をしてタメ息を吐いたり、首を左右に振っていた。
『おまえに甘えすぎだな?』
「え?なんか言った?」
『ううん。』
沈黙のなか誰かがドアをノックした。
躊躇うように二回。
それに返事をせずにいると、俺の変わりに秋が返事をした。
ゆっくりと扉が開き、スミレが遠慮がちに入ってきた。
『何を?』
「避けてる理由」
『……いいよ。』
「迷惑かけたくないって思ってるなら間違いだからな?」
『そうじゃなくて、本人の口から直接聞くまで待とうかなって?
いつか話してくれるかもしれないし。』
「ハル……それ花火に間に合わないと思う」
苦笑しながらも心配してるのが伝わってくるから、弱った涙腺から涙が出そうだった。
『確かに。フッ……』
「やっと笑った」
『ごめん』
ごめんって言わないようにしようって決めたのに、こんな簡単に破れちゃうんだ……。
「あっ!ケータイは?
メールなら答えてれくるんじゃね?」
『……メールは無視された。試しに送ってみたけど、まだ返って来てない。』
「そっか。晴斗さ、スミレになにしたの?
ずっと気になってたんだけど……」
『言わなきゃダメ?』
「話したくないならこれ以上は聞かないけどさ、原因がわからないから。
晴斗のとった事でなのか、スミレ自身の問題なのか……やっぱり話してみないと」
『なにか話すキッカケがあればいいんだけど……』
秋の言う通りだとしたらやっぱり話さないと。
「きっかけか……」
そう呟き黙ってしまった。
『始めはまだよくて「おはよう」とか「おやすみ」以外にも話してくれてたんだけど、だんだん話してくれなくなって、スミレの顔見るのが辛くて……。
夕食の時間が憂鬱で』
「そっか。」
『こんな話聞きに来たんじゃないのに、付き合わせてごめん。』
「いいよ別に。話したら少しは楽になると思うし。」
『ありがとう。』
秋はニッコリ笑って窓に視線を移した。
なにかを考えてる秋は、時折難しそうな顔をしてタメ息を吐いたり、首を左右に振っていた。
『おまえに甘えすぎだな?』
「え?なんか言った?」
『ううん。』
沈黙のなか誰かがドアをノックした。
躊躇うように二回。
それに返事をせずにいると、俺の変わりに秋が返事をした。
ゆっくりと扉が開き、スミレが遠慮がちに入ってきた。