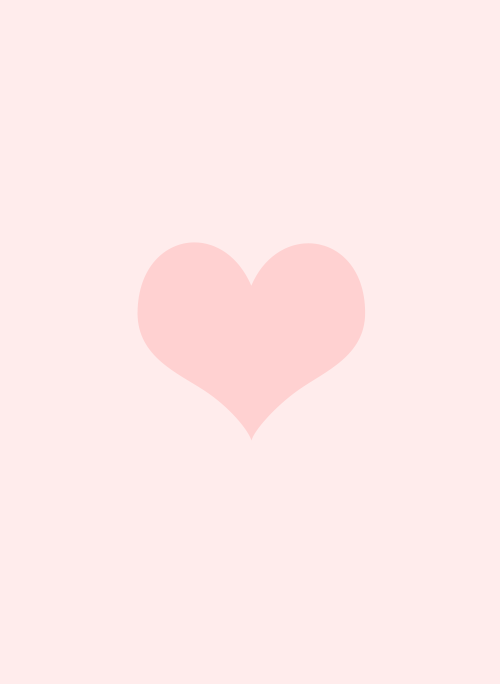――その日の夜。
なぜか私の実家の玄関の先で頭を抱える稜君に、私は思わず噴き出してしまった。
「何かもー、本当にすみません……」
「平気だから! お父さんもお母さんも待ってるから、早く入ろ!」
「こんな事になるなら、我慢すればよかった」
意外に古風な考えを持つらしい稜君は、私とイチャイチャしたそのすぐ後に、私の両親と会う事に心を痛めているそうで。
「もういいからっ!! そもそも、無理矢理呼んだのはお母さんなんだからー」
「はぁ……。ホントにごめんなさい」
それでも、うなだれたままの稜君は、誰にかもわからない謝罪の言葉を、まだ口にしている。
――事の発端は、稜君の家から私の実家にかけた電話だった。
「何か気まずいから、せめて服着てっ!!」
そう言われて、稜君に無理矢理着せられたシャツに袖を通しながらかけた電話。
“稜君の家に布団がないから、布団貸して!”
それは、そんな内容のものだった。
私の彼氏が稜君だと聞いて、お母さんが会いたがっていた事は知ってたけれど。
「じゃー、今日はうちに泊まってもらいなさいよ~!」
なんて事を言い出すとは、さすがの私も思っていなかった。
お母さんの、電話から洩れる大きな声に、一瞬目を大きくした稜君。
私は稜君とゆっくりしたかったから、断ろうと思ったのに……。
稜君はそんな私の手から、ひょいっと携帯を取って、自分の耳にそれを当てた。
「もしもし。川崎です」
目をパチクリさせる私に視線を落とした稜君は、ちょっと笑いながら私の頭を撫でる。
「はい……はい。ありがとうございます。ご迷惑でなければ、是非」
その一言に、私は目を大きくした。
だってそれって。
「はい。もう少ししたら、伺います」
そういう事だよね?