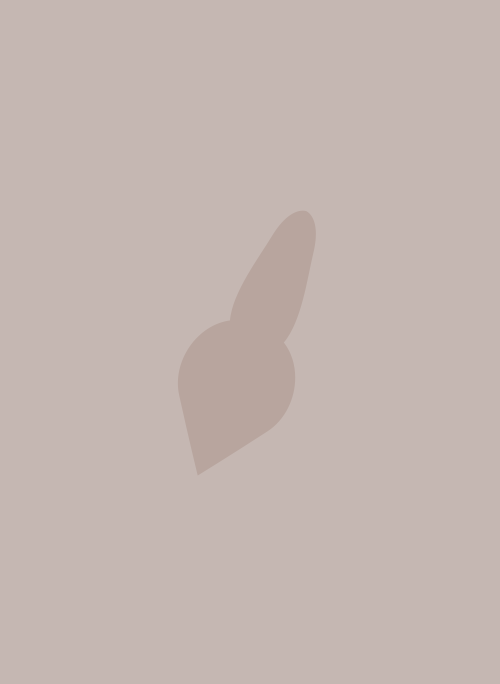「コーヒーで良いですか?」
チェンバーへの呼び出しが2時間ほどで終わった後、鳶色のさらさら髪の綺麗な顔立ちの少年の誘いを断りきれず、彼の部屋におじゃまする事になった。
「あ、どうも。」
俺の部屋と全く同じ間取りだが2週間の生活の違いがこれでもかと言うほど良く現れている室内。
作り付けの机の上にはブックエンドに挟まれて几帳面に並んだ大量の分厚い本。
ホテルの備品のポットの置かれた壁際の棚には彼の私物なのかドリッパーとミルがあり、香ばしい豆の香りを振りまいている。
「いえいえ、どういたしまして。
無理を言って僕がお呼びたてしたのですし、お気になさらずに。」
こちらが怖じ気づくほど綺麗に笑って見せながら、手慣れた様子でコーヒーを入れる少年。
顔はまさに王子様と言った感じなのに、動きは優秀な執事さながらに良く気を使い細やかだ。
「それで?
俺に何か用でも?」
部屋にまで誘われたと言う事は何事か用事があるのだろうが、部屋に満ちるこの優等生オーラが俺には落ち着かなくてすごくいずらい
他に用事があるわけではないけど、できれば早く帰りたかった。
チェンバーへの呼び出しが2時間ほどで終わった後、鳶色のさらさら髪の綺麗な顔立ちの少年の誘いを断りきれず、彼の部屋におじゃまする事になった。
「あ、どうも。」
俺の部屋と全く同じ間取りだが2週間の生活の違いがこれでもかと言うほど良く現れている室内。
作り付けの机の上にはブックエンドに挟まれて几帳面に並んだ大量の分厚い本。
ホテルの備品のポットの置かれた壁際の棚には彼の私物なのかドリッパーとミルがあり、香ばしい豆の香りを振りまいている。
「いえいえ、どういたしまして。
無理を言って僕がお呼びたてしたのですし、お気になさらずに。」
こちらが怖じ気づくほど綺麗に笑って見せながら、手慣れた様子でコーヒーを入れる少年。
顔はまさに王子様と言った感じなのに、動きは優秀な執事さながらに良く気を使い細やかだ。
「それで?
俺に何か用でも?」
部屋にまで誘われたと言う事は何事か用事があるのだろうが、部屋に満ちるこの優等生オーラが俺には落ち着かなくてすごくいずらい
他に用事があるわけではないけど、できれば早く帰りたかった。