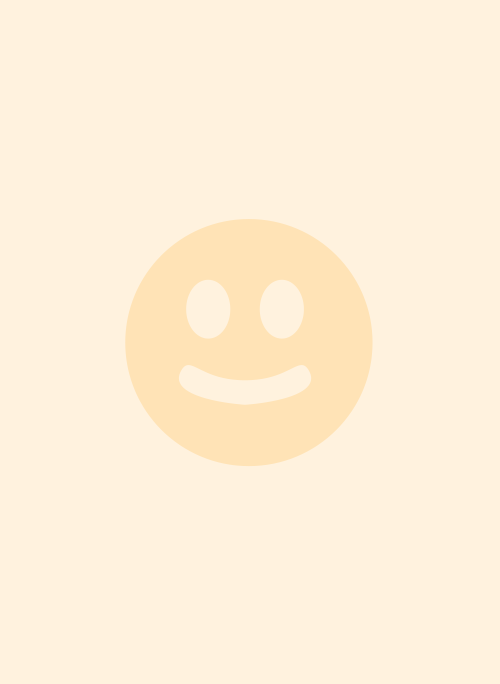「…何で“すっげー嫌”なの?」
「ん?
そんなもん決まってるだろ?
俺は響花が好きだから」
「……………え?」
何か意外な返答に驚いてしまった。
いや、そう意味じゃない事はわかっているけれど、こういう状態でこんな人の居ない場面で言われたら……さすがの私でも意識してしまう。
「あ、いやっ!
それはっ……あ、そう!お父さん!」
私の態度に慌てて驚き身体を離す郁。
「お父さん?」
「いや、ほら、何か娘が結婚式をあげるときの父親の気持ちみたいな?
響花が巣立って寂しいなーみたいな?
だ、だから、恋愛感情とかじゃ、ないから…」
よほど勘違いされたくないんだろう。
郁の言葉が珍しくしどろもどろになっている。
郁にとったら私は幼なじみで特別で。
でも、それは少女マンガのような小説のような甘酸っぱさはない。
ただ、本当に特別なだけ。
さっき郁が言った家族的な意味だ。
「そっか…
まぁ、分かってたけどちょっと焦ったよ」
「え?」
「予想外すぎてびっくりしたから」
「そっちかよ…」
――――まただ…
あの頃から、いつも郁はこうして悲しい表情を時々浮かべる。
この顔を見る度に私の胸が何故か締め付けられてしまう。
でも郁は無意識にしている。…余計にそれが私は嫌なんだ。