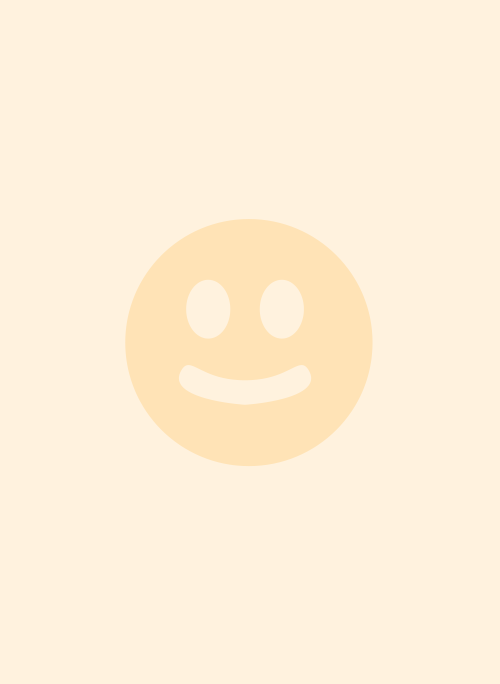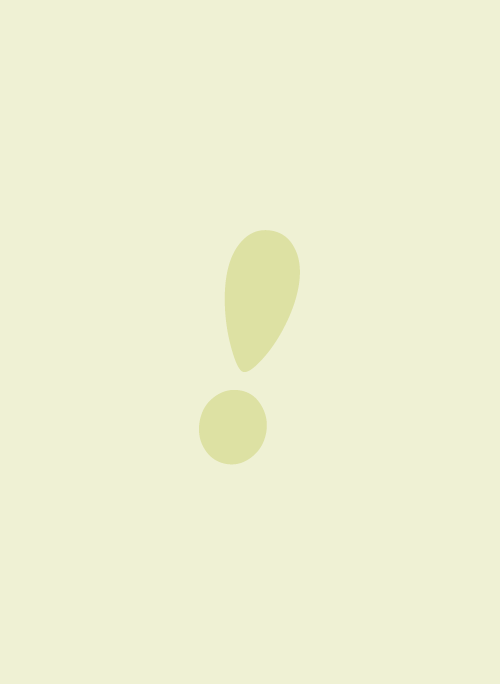次の日、
有喜は
何度も日記帳を
見直した。
『純一の気持ち、
素直に
嬉しかった。
でも、
私には
子供育てる自信ないし、
時間もない…。
自分の寿命くらい
なんとなく分かる。
時々、
私の頭の中が
おかしくなってる事も
分かってる。
でも、
ボーっとする時間が
多くて…。
字が書けるのも
時々だし、
言葉も最近出てこないことが
よくある。
そんなんじゃぁ、
子供に示しが
つかないよ…。
私が死んだら
純一は
一人で子育てしないといけない。
そんなの
無理に決まってる。
気持ちだけで
十分だよ…。』
有喜の日記は
とても力がない
文だった。
字は
ガタガタで、
今にも
消えそうだった。
日記のページが
シワシワになり、
涙の跡を
思わせた。
純一は
有喜の精一杯の気持ちが
とても嬉しかった。
まだ、
正気な有喜も
残っていると言う事も
嬉しかった。
純一は
ここまで書けるなら、
子供を授かったとしても、
やっていける
自身があった。
周囲の人からは
絶対に反対されることは
分かっていたので、
純一はあえて
医師にも相談するのは
やめた。
これは
二人の問題…。
そう割り切っていた。
有喜は
何度も日記帳を
見直した。
『純一の気持ち、
素直に
嬉しかった。
でも、
私には
子供育てる自信ないし、
時間もない…。
自分の寿命くらい
なんとなく分かる。
時々、
私の頭の中が
おかしくなってる事も
分かってる。
でも、
ボーっとする時間が
多くて…。
字が書けるのも
時々だし、
言葉も最近出てこないことが
よくある。
そんなんじゃぁ、
子供に示しが
つかないよ…。
私が死んだら
純一は
一人で子育てしないといけない。
そんなの
無理に決まってる。
気持ちだけで
十分だよ…。』
有喜の日記は
とても力がない
文だった。
字は
ガタガタで、
今にも
消えそうだった。
日記のページが
シワシワになり、
涙の跡を
思わせた。
純一は
有喜の精一杯の気持ちが
とても嬉しかった。
まだ、
正気な有喜も
残っていると言う事も
嬉しかった。
純一は
ここまで書けるなら、
子供を授かったとしても、
やっていける
自身があった。
周囲の人からは
絶対に反対されることは
分かっていたので、
純一はあえて
医師にも相談するのは
やめた。
これは
二人の問題…。
そう割り切っていた。