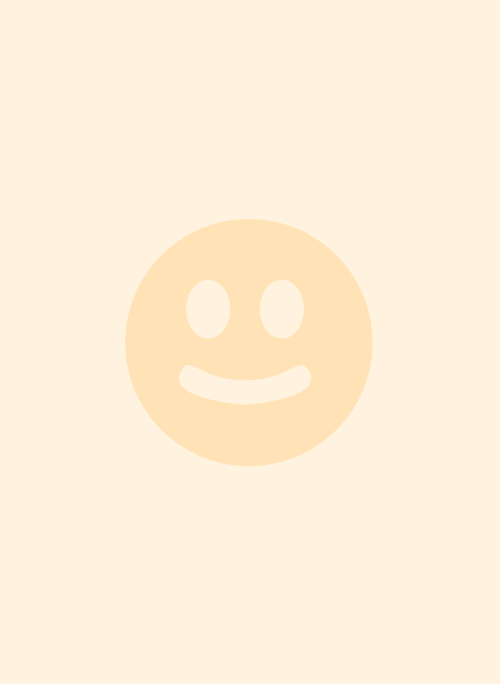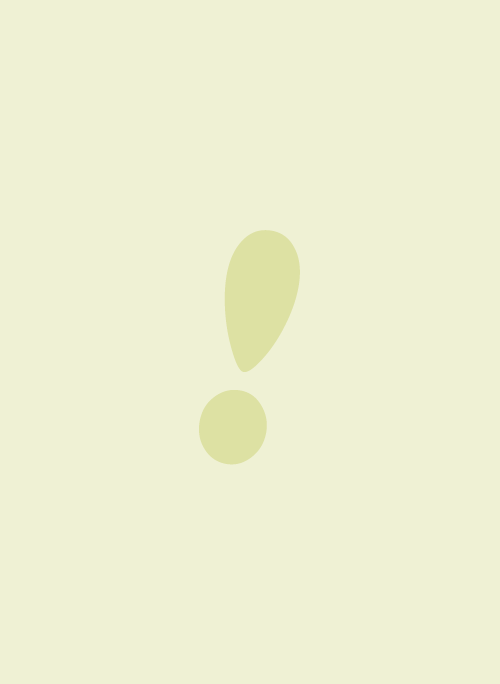何週間ぶりだろうか。
純一が有喜に
電話をよこした。
「今時間が少しあるんだ。
今からそっちに行くよ。
いい?」
有喜は、
「良いよ。
待っとくね。」
と言ったが、
有喜の声には喜びが感じられない。
純一は嫌な予感がした。
もしかして…
“終わり”
という3文字が頭の中をよぎった。
純一は車を飛ばし、
有喜の家へ向かった。
家に着くと、
有喜は部屋の隅に座っていた。
純一は自分の目を疑うかのように
二度見した。
部屋の中にはゴミが散乱しており、
今までの有喜とは明らかに違う。
気迫をどこかに忘れてきたかのように、
活気がない。
「有喜!
どうした?
寂しい思いさせて悪かったよ。
ごめんな。」
純一はギュッと有喜を抱きしめる。
「そんな事ないよ。
寂しかったけど大丈夫。
今日だって会えたじゃない。
私凄く嬉しいよ。」
と言う言葉は何故か冷たく、
表情は全くない。
純一が有喜に
電話をよこした。
「今時間が少しあるんだ。
今からそっちに行くよ。
いい?」
有喜は、
「良いよ。
待っとくね。」
と言ったが、
有喜の声には喜びが感じられない。
純一は嫌な予感がした。
もしかして…
“終わり”
という3文字が頭の中をよぎった。
純一は車を飛ばし、
有喜の家へ向かった。
家に着くと、
有喜は部屋の隅に座っていた。
純一は自分の目を疑うかのように
二度見した。
部屋の中にはゴミが散乱しており、
今までの有喜とは明らかに違う。
気迫をどこかに忘れてきたかのように、
活気がない。
「有喜!
どうした?
寂しい思いさせて悪かったよ。
ごめんな。」
純一はギュッと有喜を抱きしめる。
「そんな事ないよ。
寂しかったけど大丈夫。
今日だって会えたじゃない。
私凄く嬉しいよ。」
と言う言葉は何故か冷たく、
表情は全くない。