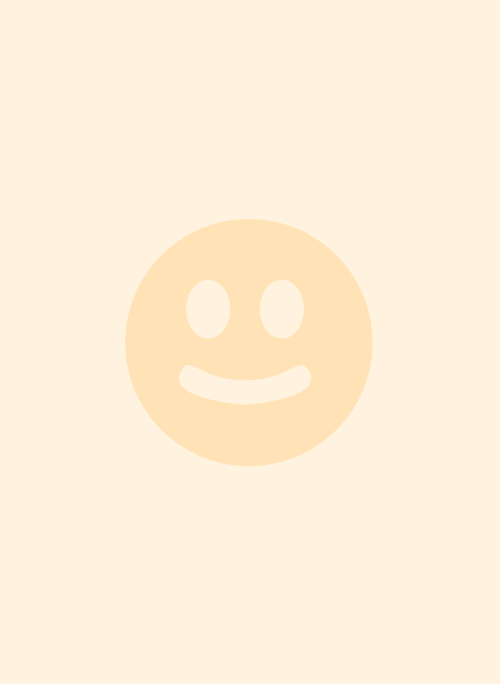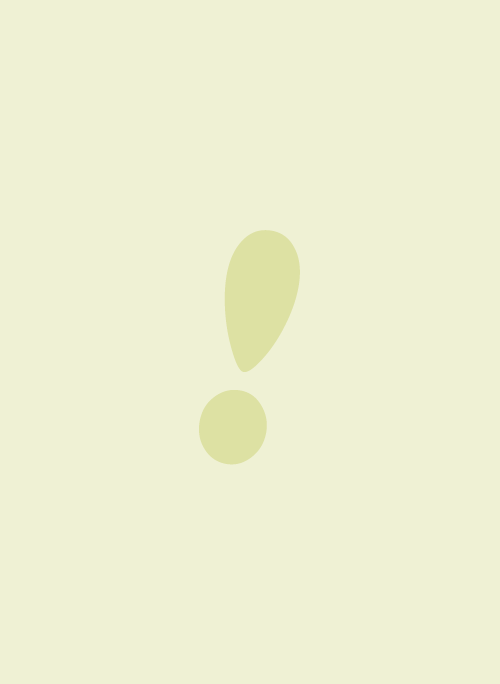その日
純一は
家に帰って
泣いた。
有喜と過ごせる日々を
大切にしたいと、
心からそう思った。
純一は悩んだ結果、
勇気の側にいることにした。
職場に
介護休暇の申請をし、
純一は
この日から
毎日
有喜と向き合って
話した。
たいした話は出来ないが、
同じ時を刻んでいる
それだけで、
純一は
満足だった。
有喜の記憶には
純一のことなど
ほとんどなくなっていた。
今ある記憶は
遠い過去の
幼い頃だけだった。
有喜は
食事摂取量も
徐々に減り、
見る見るうちに
痩せていった。
「お兄ちゃん
何で
ここに
いるの?」
「お兄ちゃん
絵本
読んで。」
そんな会話ばかりだった。
純一は
家に帰って
泣いた。
有喜と過ごせる日々を
大切にしたいと、
心からそう思った。
純一は悩んだ結果、
勇気の側にいることにした。
職場に
介護休暇の申請をし、
純一は
この日から
毎日
有喜と向き合って
話した。
たいした話は出来ないが、
同じ時を刻んでいる
それだけで、
純一は
満足だった。
有喜の記憶には
純一のことなど
ほとんどなくなっていた。
今ある記憶は
遠い過去の
幼い頃だけだった。
有喜は
食事摂取量も
徐々に減り、
見る見るうちに
痩せていった。
「お兄ちゃん
何で
ここに
いるの?」
「お兄ちゃん
絵本
読んで。」
そんな会話ばかりだった。