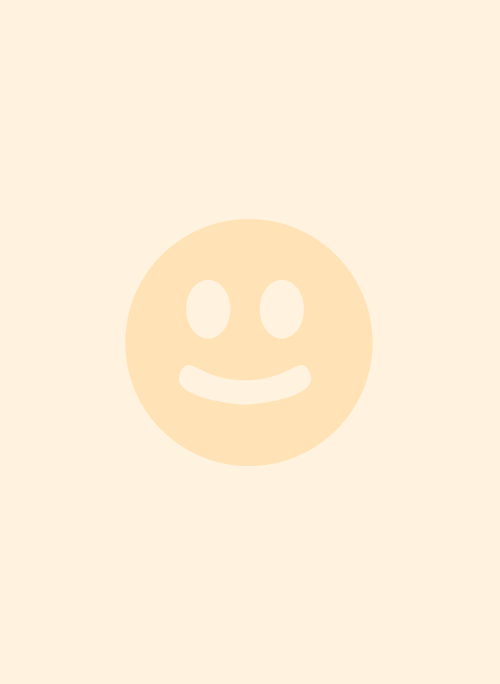振り返ったらきっと侑がまた掴みかかってくる。私は部屋を飛び出すと、廊下を走った。
「冬馬さんっ」
私が走っていく先に、大輝さんが立っていた。心配そうに立っているように見えたのは私の錯覚かもしれないけれど。
「大輝さん」と、私は彼の胸に飛び込んだ。
抱きしめてくれる温かい手に、ほっとする。
怖かった。昔、付き合っていた男とは言え、いきなり暗い室内に連れ込まれて、抑えつけられたのは怖い。
まるで寒さに凍える身体のようにブルブルと筋肉が震えている。
「大丈夫ですか?」
大輝さんがポンポンと背中を優しく叩いてくれる。
心臓の鼓動と同じリズムで叩かれて、心がどんどんと落ちついていくのがわかる。
「すみません。少し驚いてしまって」
私は落ちてきた髪を耳にかけると、喉を鳴らした。
「冬馬さんっ」
私が走っていく先に、大輝さんが立っていた。心配そうに立っているように見えたのは私の錯覚かもしれないけれど。
「大輝さん」と、私は彼の胸に飛び込んだ。
抱きしめてくれる温かい手に、ほっとする。
怖かった。昔、付き合っていた男とは言え、いきなり暗い室内に連れ込まれて、抑えつけられたのは怖い。
まるで寒さに凍える身体のようにブルブルと筋肉が震えている。
「大丈夫ですか?」
大輝さんがポンポンと背中を優しく叩いてくれる。
心臓の鼓動と同じリズムで叩かれて、心がどんどんと落ちついていくのがわかる。
「すみません。少し驚いてしまって」
私は落ちてきた髪を耳にかけると、喉を鳴らした。