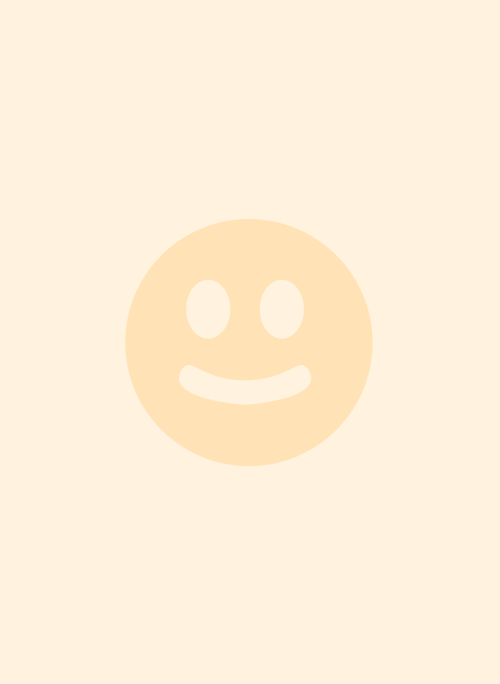「でも、ソイツ鈍感だから俺がどれだけアピールしても言わないと気づいてくれない奴だった…」
「うん」
――…私に何の関係があるんだろう?
風上君は私に何を伝えようとしているの?
私に関係ないなら、ここから一刻も早く出たいのに……
いくら風上君が居てくれるからって、やっぱりこんな暗い場所は嫌いだ。
1人じゃないのは良いけど、落ち着かない。いつもいじめられていた倉庫の風景とここは雰囲気がよく似ているから。
お弁当なんてとてもじゃないけど食べられなかったかも…
…まぁ、今となっては全部嘘だったし、鍵がかかってるから出られもしないんだけど。
「だから、どうにかして伝えたくて…俺は本を書いた。
賞とかそんなの取る気はなくて、ただ入選されて雑誌や新聞に名前が載れば彼女が気づいてくれるかもしれない……って考えた」
しかし、意外な彼の意見に少し気がまぎれる。
「そっか…」
風上君でもこんなことあるんだ。
恋愛に関しては何の努力も必要無さそうなのに…
「俺はまず本の著者名に好きな奴の名前を入れて名字を俺にした。……彼女が本に興味を示すために」
―――…成る程。