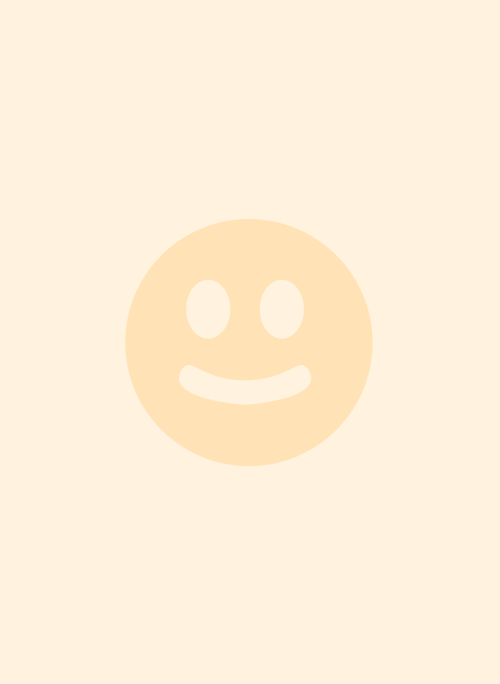期日まで明日という日が訪れた。
私の原稿用紙は依然白紙のままだった。
―――…もう、皆に嘘だって言うしかない。
また、あの、皆から知らんぷりされる生活に戻るだけだ。
この約1ヶ月はあいさつとかしてくれる人ができていた。
この何気ない幸せが無くなるのは嫌だけど、どうせ虚構の上で成り立っている出来事だと考えれば辛くない。それに罪悪感もないわけではなかった。
だってあの著者の本人が目の前に居るのだ。風上君はきっとわたしのためを思って自分が本当の作者だと言わないのだろう。…本当にこんな勝手で酷い事ばかりしている奴に一体彼はどこまで優しいんだろう…
「お母さん、行ってきます」
家族にいじめのことは話していなかった。
だから私は笑顔でいってきますの挨拶を告げる。
表情とは裏腹に重い足取りで学校へ行こうと玄関を出ると家のポストに茶色い封筒が入っているのが見えた。
私は何となく気になってそれを手に取る。
誰からだろう?
しかし表にも裏にも、どこにも差出人は書かれていなかった。