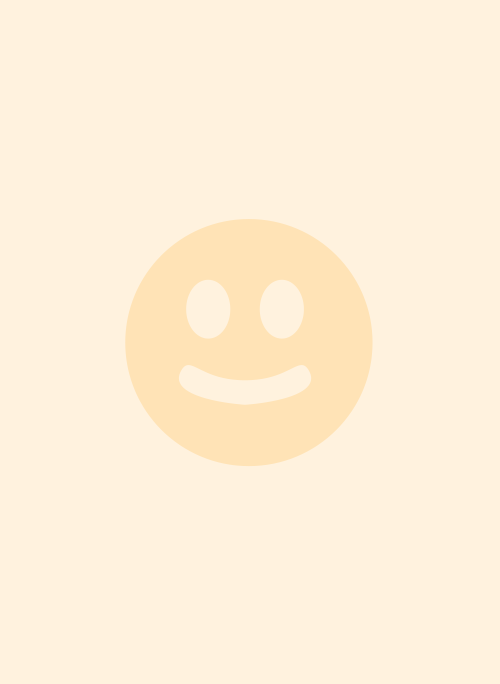「あと少しで手に入るってのに、横から掻っ攫われてたまるか」
「え?」
信じられないほど低く通る男性の声が聞こえた気がした。
驚いて周りを見回しても、きょとんとした双子の姉の姿しかなく、幻聴だったのかと思わせる。
「どうしたの? 神妃?」
「さっき……」
――男の人の声がしなかった?
そう聞きたくても、なぜか創星に尋ねる事は出来なかった。
神妃は気のせいだと切り替え「なんでもない」と創星へと続けた。
「変な神妃。さ、早く帰ろうよ! 今日は特別な日なんだからね」
「創星、そんなに急がなくても……特別な日って言ったって、家族だけで誕生日会するだけなのに」
苦笑交じりに、先ほどからずっと家へと急かす創星を見る。
「きっと今年も一緒だよ? ケーキ食べてお父さんたちからバースデープレゼントもらって……」
「今年は違うの! 一六歳になるんだからね!!」
「そ、そうだね」
息巻く創星の勢いにのまれ神妃は思わず頷いてしまう。
「だからね!? 早く早く!!」
「わっ ちょっと創星! いきなり早足にならないで!!」
加速した創星の足についていけず、神妃はつんのめる。
そんな神妃を振り返り「仕方がないなぁ」と、神妃の手を右手を左手で握りしめる。
自然に恋人つなぎしてきた創星に、神妃はたまらず眉間に皺を寄せる。
「ちょっと、何この手は」
「うふふ、恋人みたいじゃない?」
「やめてよ同じ顔でそんなこと言わないで」
「同じ顔じゃなきゃいいんだ?」
至極真面目に返され、神妃は言葉を失う。
「……同じ顔じゃなく、血縁でもなく、異性であればいいよ」
「ふ~ん、そう」
創星はその返答に満足げに「そっかそっか」と笑いながら、神妃を引っ張って歩いていく。その創星の後姿を神妃は訝しげに見つめ引かれるままに歩みを進める。
「ねぇ、もうすぐ下駄箱だし、もう手を放してよ」
「嫌だ。いいじゃない姉妹なんだもん。仲良く手を繋いでいたっておかしなことなんてないよ?」
「……」
「え?」
信じられないほど低く通る男性の声が聞こえた気がした。
驚いて周りを見回しても、きょとんとした双子の姉の姿しかなく、幻聴だったのかと思わせる。
「どうしたの? 神妃?」
「さっき……」
――男の人の声がしなかった?
そう聞きたくても、なぜか創星に尋ねる事は出来なかった。
神妃は気のせいだと切り替え「なんでもない」と創星へと続けた。
「変な神妃。さ、早く帰ろうよ! 今日は特別な日なんだからね」
「創星、そんなに急がなくても……特別な日って言ったって、家族だけで誕生日会するだけなのに」
苦笑交じりに、先ほどからずっと家へと急かす創星を見る。
「きっと今年も一緒だよ? ケーキ食べてお父さんたちからバースデープレゼントもらって……」
「今年は違うの! 一六歳になるんだからね!!」
「そ、そうだね」
息巻く創星の勢いにのまれ神妃は思わず頷いてしまう。
「だからね!? 早く早く!!」
「わっ ちょっと創星! いきなり早足にならないで!!」
加速した創星の足についていけず、神妃はつんのめる。
そんな神妃を振り返り「仕方がないなぁ」と、神妃の手を右手を左手で握りしめる。
自然に恋人つなぎしてきた創星に、神妃はたまらず眉間に皺を寄せる。
「ちょっと、何この手は」
「うふふ、恋人みたいじゃない?」
「やめてよ同じ顔でそんなこと言わないで」
「同じ顔じゃなきゃいいんだ?」
至極真面目に返され、神妃は言葉を失う。
「……同じ顔じゃなく、血縁でもなく、異性であればいいよ」
「ふ~ん、そう」
創星はその返答に満足げに「そっかそっか」と笑いながら、神妃を引っ張って歩いていく。その創星の後姿を神妃は訝しげに見つめ引かれるままに歩みを進める。
「ねぇ、もうすぐ下駄箱だし、もう手を放してよ」
「嫌だ。いいじゃない姉妹なんだもん。仲良く手を繋いでいたっておかしなことなんてないよ?」
「……」