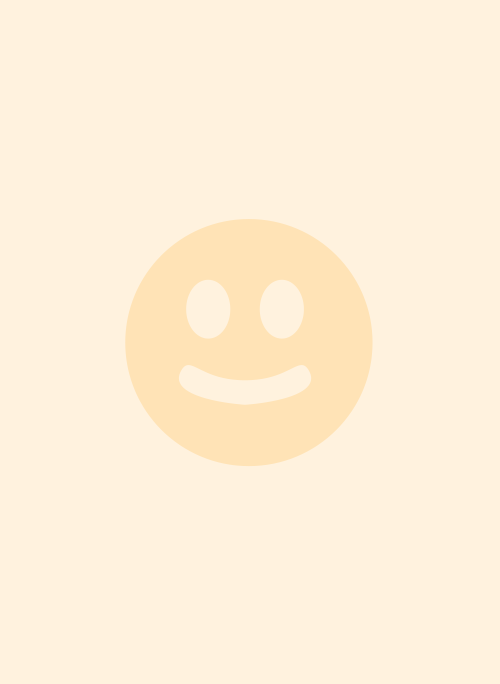「同じ顔なんだから、私にも男子からの告白とか来ても良いはずなのに……」
思わず神妃の口から嘆きがこぼれる。
それを聞いて、創星はくりっと丸く目を見開いて、
「呼び出しされてるじゃない、女の子に」
と返された。
「女の子じゃなく、男の子!」
創星へ返し神妃は少し泣きたくなる。女の子に好かれる事に対して嫌だと思う事はない。むしろ、嬉しいくらいだ。
しかし、度合いや系統が違う。部活で尊敬される先輩や、理想や目標とする人物などであればいい。
それが恋愛感情となると異なる。神妃にはその気持ちに応える事が出来ないため、ただただ申し訳なくなるのだ。
「本当。なんでこんな根性曲りが人気あるの……」
「あ、神妃それ傷つく」
「傷つけ、私の傷心はもっと深いんだから」
「ふ~ん、ねぇ、神妃。神妃は好きでもない人から告白されて嬉しいの? 男だったら告白されれば簡単に付き合っちゃうの?」
「そんなこと言ってない」
どこか非難じみた創星の言葉に、神妃はわずかにたじろいだ。
「ただ……言われてみたいのよ、一度も告白されことがない身としては、憧れもあるし」
「そんな憧れ帰ったら家のトイレに流しちゃいなよ」
「そこまで言う」
「言うよ、神妃くだらないことに拘りすぎ」
くだらない……その言葉が神妃の気に触れた。
癇癪持ちの子供の様に、神妃は今までため込んでいた不服が口からあふれ出す。
「くだらないって何!? なんであんたにそこまで言われなくちゃならないの!? 私の気持ち知っててそんな風に言うあんたなんて大っ嫌い!!」
「私は好きよ」
「っ」
「私は、神妃の事が何よりも大事。とっても大好き。だから、無暗に変な男につかまって欲しくないの」
吐き出した言葉に、まっすぐ言葉を返してくる創星に神妃は押し黙る。
「もし変な男捕まえてきたら、私、許さない」
「そ……ら?」
創星のぞくりと背を虫が這い上がるような不気味な雰囲気に、神妃はたまらず動かしていた足を止める。そのことに気が付いてなのか、創星からは先ほど見えた雰囲気は払拭され、見慣れた笑顔が戻っていた。
「神妃は大切な妹だもん! ね?」
「あ、……うん」
「てことで、この話はやめ! 早くお家に帰ろう~」
「ああ、ちょっと引っ張らないでよ!!」
――さっきのは、気のせい……だよね。
神妃は言いようのない不安が胸の中に溢れていくような気がしたが、気づかないふりをして、腕を絡めて歩く創星の後を追いかけた。
思わず神妃の口から嘆きがこぼれる。
それを聞いて、創星はくりっと丸く目を見開いて、
「呼び出しされてるじゃない、女の子に」
と返された。
「女の子じゃなく、男の子!」
創星へ返し神妃は少し泣きたくなる。女の子に好かれる事に対して嫌だと思う事はない。むしろ、嬉しいくらいだ。
しかし、度合いや系統が違う。部活で尊敬される先輩や、理想や目標とする人物などであればいい。
それが恋愛感情となると異なる。神妃にはその気持ちに応える事が出来ないため、ただただ申し訳なくなるのだ。
「本当。なんでこんな根性曲りが人気あるの……」
「あ、神妃それ傷つく」
「傷つけ、私の傷心はもっと深いんだから」
「ふ~ん、ねぇ、神妃。神妃は好きでもない人から告白されて嬉しいの? 男だったら告白されれば簡単に付き合っちゃうの?」
「そんなこと言ってない」
どこか非難じみた創星の言葉に、神妃はわずかにたじろいだ。
「ただ……言われてみたいのよ、一度も告白されことがない身としては、憧れもあるし」
「そんな憧れ帰ったら家のトイレに流しちゃいなよ」
「そこまで言う」
「言うよ、神妃くだらないことに拘りすぎ」
くだらない……その言葉が神妃の気に触れた。
癇癪持ちの子供の様に、神妃は今までため込んでいた不服が口からあふれ出す。
「くだらないって何!? なんであんたにそこまで言われなくちゃならないの!? 私の気持ち知っててそんな風に言うあんたなんて大っ嫌い!!」
「私は好きよ」
「っ」
「私は、神妃の事が何よりも大事。とっても大好き。だから、無暗に変な男につかまって欲しくないの」
吐き出した言葉に、まっすぐ言葉を返してくる創星に神妃は押し黙る。
「もし変な男捕まえてきたら、私、許さない」
「そ……ら?」
創星のぞくりと背を虫が這い上がるような不気味な雰囲気に、神妃はたまらず動かしていた足を止める。そのことに気が付いてなのか、創星からは先ほど見えた雰囲気は払拭され、見慣れた笑顔が戻っていた。
「神妃は大切な妹だもん! ね?」
「あ、……うん」
「てことで、この話はやめ! 早くお家に帰ろう~」
「ああ、ちょっと引っ張らないでよ!!」
――さっきのは、気のせい……だよね。
神妃は言いようのない不安が胸の中に溢れていくような気がしたが、気づかないふりをして、腕を絡めて歩く創星の後を追いかけた。