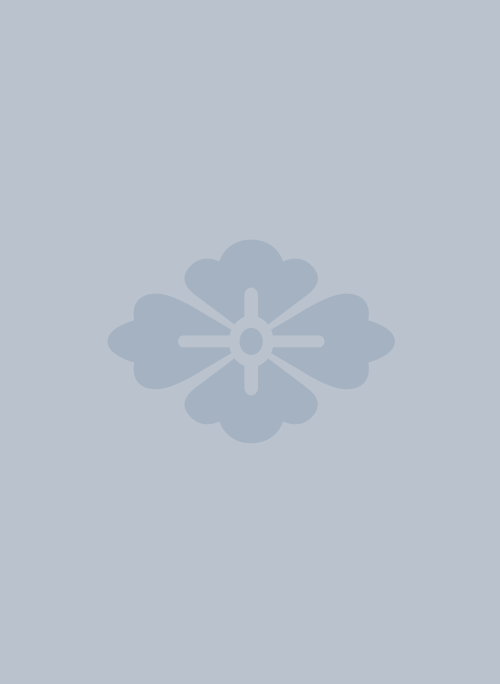けれど先輩は知らない。
全然わかってない。
私が、どれだけあの子に嫉妬したのか。
どれほど羨ましかったのか。
「…私だって、マネージャーが羨ましかったです」
そう小さく呟けば、先輩は驚いたように目を見開いた。
そんな先輩から視線を下に逸らして言葉を続ける。
「部活頑張ってる先輩をいつも傍で応援できて、名前で呼ばれてて…」
羨ましくて仕方なかった。
なんの躊躇いもなくすぐ傍で応援できること。
落ち込んでる先輩に手を差し伸べられること。
名前を呼んでもらえること。
何一つ私には遠くて。
何度一人で泣いたかわからない。
「…なんか、俺ら似た者同士みたいだな」