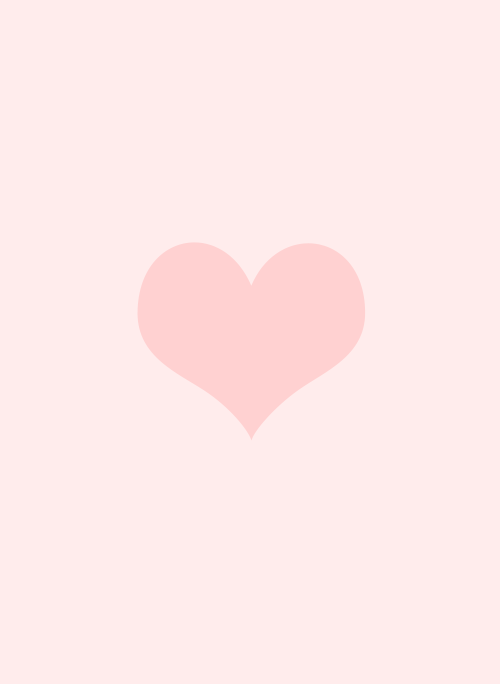おめでとう、と都夕希は笑った。
慈愛に満ちた瞳でお腹に触れながら、しかしティアは複雑だった。
トゥインとの子を授かったのは、嬉しい。
自由のきかない身ではあるけれど、どんなことがあろうと愛し子を守り通す覚悟はとうに決まっていた。
もう子供が産めないと気落ちしていた都夕希は既に立ち直り、体調も回復していたが、彼女にこの報告をすることに罪悪感を覚えてしまう。
とは言っても、報告を怠ればどうして教えてくれなかったのかと頬を膨らませるのが目に見えているから仕方のないことではあるのだけれど。
『ティア、アミルダはどうだったか知らないのだけれど、この国では乳母をつけるの。身分にもよるけれど』
都夕希は視線を伏せながら、言い出した。
その口元は笑っているはずなのにどこか哀しそうだった。
それを気にしながら、ティアは正直に答える。
『アミルダの城でも、生まれた子は乳母に任せていました。私も長期間仕事を休めるわけではないので、誰か探そうと思うのですが……』
乳母は大抵、同時期に妊娠した女性にお願いするのが常だった。
母が忙しいと母乳をあげられないからだ。
しかし、そんな贅沢も言っていられないときは信頼のおける女官に頼むこともある。
加えて、アミルダの子である。
引き受けられる人は限られているだろう。
だから、信頼のおけるリィンに頼もうかと考えていた。
戦力が減るのはできれば避けたいが、仕方がない。
そう腹積もりをしていたので、彼女の言葉には驚いた。
『あなたたちの子、玲香に任せてもいいかしら』
思わず見開いた瞳でティアが見つめると、都夕希は微笑んだ。
眉尻を下げて。
その顔に、ティアはすべてを飲み込み、ただ一つ、静かに問うた。
『恨みは、しないのですか』
『ティア。
あの者が、子に名乗りを上げることはないでしょう。__あの子の母は、私です。
私が母を放棄したら、あの子は愛を知らない子になってしまう。それは、あまりに哀しい話ではありませんか』
顔を上げて、しっかりと前を見据えて都夕希は声にする。
その心を推し量ることはできない。
『ツユキさま…』
『王子として育てる以上、私の子です。生みの母が私ではないと悟らせてはなりません。あの子まで苦しめることはなりません。
…玲香も辛いのですから責めてはなりません。その荷を背負わせたのは、私なのですから…』
ツユキさま、と呼ぶ声は、もう音にならなかった。
慈愛に満ちた瞳でお腹に触れながら、しかしティアは複雑だった。
トゥインとの子を授かったのは、嬉しい。
自由のきかない身ではあるけれど、どんなことがあろうと愛し子を守り通す覚悟はとうに決まっていた。
もう子供が産めないと気落ちしていた都夕希は既に立ち直り、体調も回復していたが、彼女にこの報告をすることに罪悪感を覚えてしまう。
とは言っても、報告を怠ればどうして教えてくれなかったのかと頬を膨らませるのが目に見えているから仕方のないことではあるのだけれど。
『ティア、アミルダはどうだったか知らないのだけれど、この国では乳母をつけるの。身分にもよるけれど』
都夕希は視線を伏せながら、言い出した。
その口元は笑っているはずなのにどこか哀しそうだった。
それを気にしながら、ティアは正直に答える。
『アミルダの城でも、生まれた子は乳母に任せていました。私も長期間仕事を休めるわけではないので、誰か探そうと思うのですが……』
乳母は大抵、同時期に妊娠した女性にお願いするのが常だった。
母が忙しいと母乳をあげられないからだ。
しかし、そんな贅沢も言っていられないときは信頼のおける女官に頼むこともある。
加えて、アミルダの子である。
引き受けられる人は限られているだろう。
だから、信頼のおけるリィンに頼もうかと考えていた。
戦力が減るのはできれば避けたいが、仕方がない。
そう腹積もりをしていたので、彼女の言葉には驚いた。
『あなたたちの子、玲香に任せてもいいかしら』
思わず見開いた瞳でティアが見つめると、都夕希は微笑んだ。
眉尻を下げて。
その顔に、ティアはすべてを飲み込み、ただ一つ、静かに問うた。
『恨みは、しないのですか』
『ティア。
あの者が、子に名乗りを上げることはないでしょう。__あの子の母は、私です。
私が母を放棄したら、あの子は愛を知らない子になってしまう。それは、あまりに哀しい話ではありませんか』
顔を上げて、しっかりと前を見据えて都夕希は声にする。
その心を推し量ることはできない。
『ツユキさま…』
『王子として育てる以上、私の子です。生みの母が私ではないと悟らせてはなりません。あの子まで苦しめることはなりません。
…玲香も辛いのですから責めてはなりません。その荷を背負わせたのは、私なのですから…』
ツユキさま、と呼ぶ声は、もう音にならなかった。