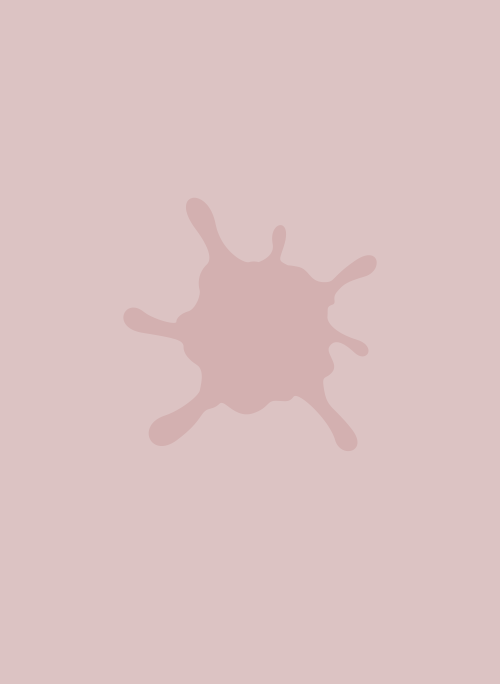「…っ、ああぁ!」
思い出したくないのに。
名も知らぬ彼女はそれを許してはくれない。
(…斬り込むんだ!これは幻で夢なんだから)
僕は大きく声を張り上げて、竹刀を高く振り上げた。
迷いを振り切るように。
でも、
「胴ぉー!」
身体に衝撃が走ったのは、僕の方だった。
相手の竹刀が身体に食い込んで、駆け抜けていく。
「勝負あり!」
審判が、手を挙げて試合を制した。
僕はゆっくりと相手へと視線を向ける。
でもすでに、そこに彼女の面影はなかった。
「礼!」
試合終了の合図に、僕は想像以上に疲労した身体で、軽く礼を返す。
その僕の耳元には、今はすでに居ない、彼女の微かな笑い声が残されていた。
End.
思い出したくないのに。
名も知らぬ彼女はそれを許してはくれない。
(…斬り込むんだ!これは幻で夢なんだから)
僕は大きく声を張り上げて、竹刀を高く振り上げた。
迷いを振り切るように。
でも、
「胴ぉー!」
身体に衝撃が走ったのは、僕の方だった。
相手の竹刀が身体に食い込んで、駆け抜けていく。
「勝負あり!」
審判が、手を挙げて試合を制した。
僕はゆっくりと相手へと視線を向ける。
でもすでに、そこに彼女の面影はなかった。
「礼!」
試合終了の合図に、僕は想像以上に疲労した身体で、軽く礼を返す。
その僕の耳元には、今はすでに居ない、彼女の微かな笑い声が残されていた。
End.