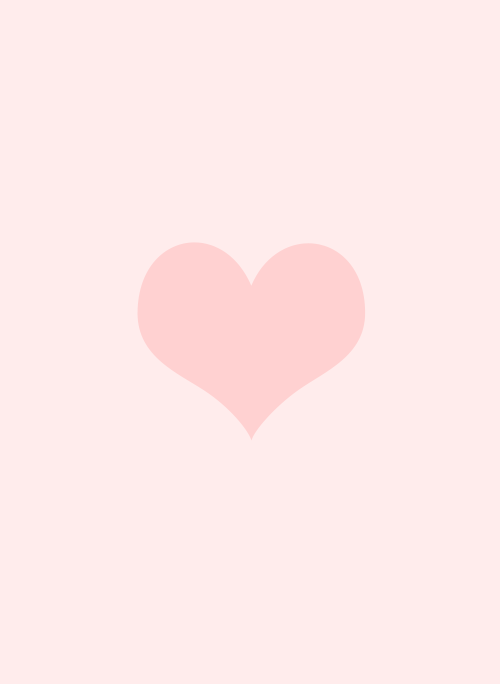☆…―――――――
―――――――
近藤君はさすがファッションを学ぶ服飾コースの生徒なだけあるなと、私は勝手に惚れ直していた。
柊みたいな落ち着いた紅色のセーターは細身なんだけど、お尻の辺でたっぷりしたラインが小意気だし、
ざらついた見た目の夜空みたいな黒シャツにはツリーみたいな緑のステッチが可愛いし、
ソックスの裏にすべりどめでお星様がついていて笑えるし、
トータルでクリスマスを隠したコーディネートは計算高くで、
印が無い良い品のチェーン店で筆記用具を買ってそうな爽やかな顔立ちに似合って、まとまりが良い。
「ごちそさま」
「ごちそーさまでしたって言えよ」
これが果たしてパーティーなのかは、正直よく分からなかった。
クラッカーも鳴らしていないし、サンタ帽も被っていないし、
ツイスターゲームもしてないし、キャンドルもたかないし、
海外のハイスクールっぽいことをしていないなら、これはパーティーじゃないのかもしれない。
二時間かけて二人で料理を作って、少し照明を落としてツリーの点灯が味わえるようにして、
近藤君の友達の市井が用意してくれていたクリスマスソングのオルゴールCDをかけっぱなしにして、
二人でテーブルを囲って、ご飯を食べた。
愛美あたりに『ただの食事会じゃん』と、突っ込まれたら、私も彼氏も頷くしかできない上に、
里緒菜あたりに『そこはDJしなよ』と、からかわれると思う。
ただ、お昼を抜きだったからと弁解しようが、晩ご飯を食べ終わったのが五時という早さは、
深い甘い清い意味を持つ。
そう、これから食べるホールケーキやプレゼント交換がメインじゃないことくらい馬鹿じゃないから知っている。
―――――――
近藤君はさすがファッションを学ぶ服飾コースの生徒なだけあるなと、私は勝手に惚れ直していた。
柊みたいな落ち着いた紅色のセーターは細身なんだけど、お尻の辺でたっぷりしたラインが小意気だし、
ざらついた見た目の夜空みたいな黒シャツにはツリーみたいな緑のステッチが可愛いし、
ソックスの裏にすべりどめでお星様がついていて笑えるし、
トータルでクリスマスを隠したコーディネートは計算高くで、
印が無い良い品のチェーン店で筆記用具を買ってそうな爽やかな顔立ちに似合って、まとまりが良い。
「ごちそさま」
「ごちそーさまでしたって言えよ」
これが果たしてパーティーなのかは、正直よく分からなかった。
クラッカーも鳴らしていないし、サンタ帽も被っていないし、
ツイスターゲームもしてないし、キャンドルもたかないし、
海外のハイスクールっぽいことをしていないなら、これはパーティーじゃないのかもしれない。
二時間かけて二人で料理を作って、少し照明を落としてツリーの点灯が味わえるようにして、
近藤君の友達の市井が用意してくれていたクリスマスソングのオルゴールCDをかけっぱなしにして、
二人でテーブルを囲って、ご飯を食べた。
愛美あたりに『ただの食事会じゃん』と、突っ込まれたら、私も彼氏も頷くしかできない上に、
里緒菜あたりに『そこはDJしなよ』と、からかわれると思う。
ただ、お昼を抜きだったからと弁解しようが、晩ご飯を食べ終わったのが五時という早さは、
深い甘い清い意味を持つ。
そう、これから食べるホールケーキやプレゼント交換がメインじゃないことくらい馬鹿じゃないから知っている。