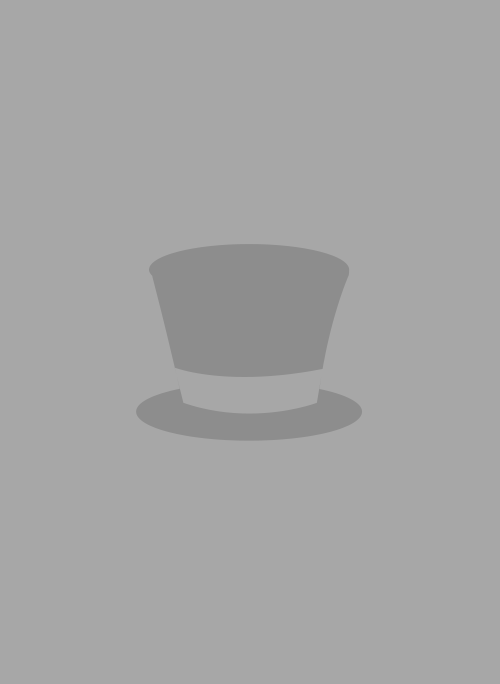執事が「こほん」と咳払いして姿勢を正すと、いつもの優雅な動作を取り戻す。
カップに吸い込まれるような紅茶。
立ち上がる柔らかな湯気。
そして、綺麗な瞳から刺すような冷たい視線。
照れちゃってるのね。
「お嬢様をこの椅子に縛りつけ、嫌いなオニオンスライスを食べさせる役目なら、今すぐに喜んで引き受けますが、いかがでしょう?」
「はぁ……けっこうよ」
そんなんじゃモテないわよ? 柏原
どうしてそんな性悪サイボーグに戻っちゃうのよ。
優しかったり
意地悪だったり
暖かったり
冷たかったり
本当に掴み所のない執事ね。
「ねぇ、お給料を増やすから優しいだけの執事になってくれない?」
良い香りの紅茶が目の前に静かに置かれた。
「お断りいたします。お嬢様の為にはならないでしょう。さあ、学校の時間です。今日は、何が何でも学校に行っていただきます」
柏原は、懐から取り出した懐中時計を細目で確認すると、時計を大切そうにしまいながら朗かな笑みを浮かべた。
「それこそ、縛り付けてでも……」
その表情と、台詞があまりにも不釣り合いで恐い。
そういう時こそ冷たく睨みつけるものじゃないのかしら。
更に本当にやりそうな所がもっと恐い。