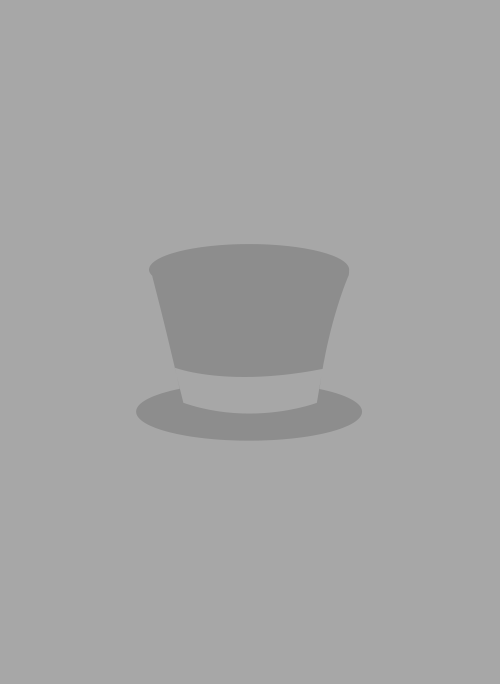「────お迎えにあがりました。茉莉果お嬢様」
両足を揃え背筋を伸ばし、ゆっくりとした美しいお辞儀は敬愛と尊敬を示し、胸の前に右手をおいた斜め四十五度は最敬礼を意味する。
そして皺のない漆黒の燕尾服は、屋敷からの支給品だけど彼はそれを誰よりも着こなしている。
芸術作品のような綺麗な顔にかかる黒髪。そこから覗く二つの瞳は、私に視線を合わせると柔らかく細められた。
磨きあげられた黒い車の後部座席のドアを姿勢を崩さずに開く彼。
車に乗る前に、カシミヤのコートを脱がせ通学カバンを受け取ると再度伏せ目がちに微笑む。
総皮張りの車内は温かく快適な温度。彼が作りだしてくれる空間。
「お嬢様、本日はすぐに屋敷戻ります。よろしいでしょうか?」
私の執事、柏原。
彼は遠慮がちに私の機嫌を伺う。けれども、その態度とは裏腹に答えを待たず車を発進させるのだ。
「もう走り出してるじゃない柏原。それで、今日の予定は?」
「本日は十七時より、ウィーンよりいらしたセルマン先生によります、ヴァイオリンのレッスンを予定しております」
柏原はチラッとルームミラーを覗き、また私の顔色を伺う。
私がヴァイオリンのレッスンと聞いて何か逃避策を練らないかが心配なのだろう。
セルマン先生は初老の男性だ。世界的に有名なヴァイオリニストであり父の友人でもある。
私はヴァイオリンのレッスンは嫌い。高い指導料を払うなら、せめてイケメンの先生を雇ってくれれば嫌いなヴァイオリンも大好きになれるかもしれないのにね。