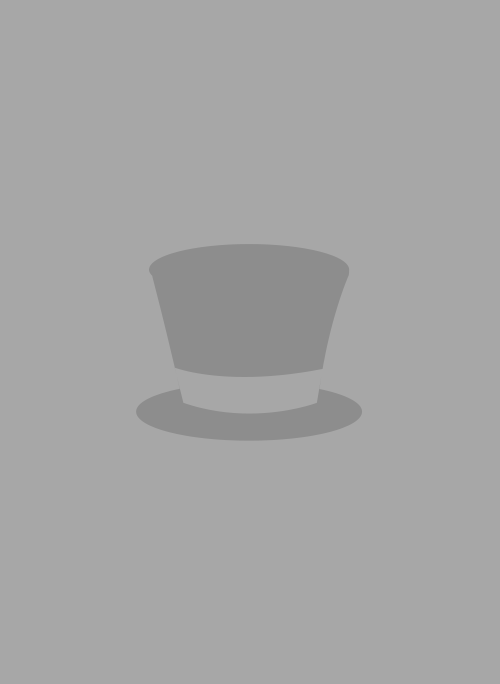背筋が凍りつくほど冷たい視線が、私に向けられる。
「だって、柏原! この前私を『欲しい』って言ってたじゃない! だから私が柏原を買えばずっと一緒でしょ!」
「貴女を一度くらいなら私のものにしてもいいが、私を差し出すとは言っていない」
こんなに冷たい視線をさらす柏原は見たことがない。
「孤独に苦しむ貴女は美しいな……そうやって、もっと、もがき苦しめばいい」
給仕用の白い手袋が、床に落ちた。
柏原の指が私の頬をなぞる。
鳥肌がたった。背筋がぞくぞくする。
「うんといたぶって捨ててやろうか? その時の貴女はきっと最高だろう」
「なっ……」
パシンッ! と大きな音を立てて柏原の右手を払う。
「そう、その傷付いた瞳と強気な態度。悲痛な孤独の中にいるからこそ魅力的だ。誰かのものになってしまわれては貴女は貴女らしくなくなってしまう」
「ふざけないで! 私にずっと一人でいろって言うの!」
冷酷で無慈悲な執事。
今にはじまったことじゃないけど、こんなに酷い柏原はじめてよ!
怒りで涙も出てこないじゃない!
勢いよく立ち上がり椅子が、ダンと激しく倒れる。
「お嬢様、食事中に席を立つことはマナー違反でございます」
そして私の執事は、優しく微笑んだ。