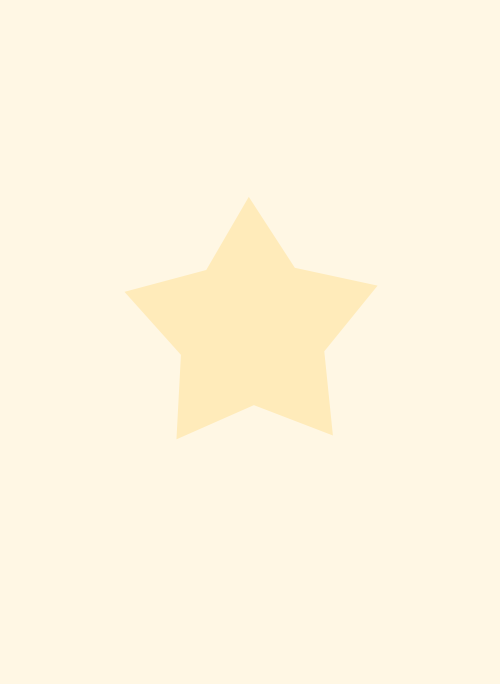「泣かないで」
いつのまにかはだけていたシャツ。その胸の谷間に、顔をこすりつけて大きく息を吐いた。
「やっぱり俺、マザコンなのかな」
「どうしてですか」
「なんかね、こうしてると安心するんだもん」
悲しい別れ方をしたからなのかもと言いかけて、口を噤んだ。
「いいですよ。お母さんって呼んでも」
あの時の冗談を思い出した。お母さんといいながら、猫のようにじゃれてきたこと。
「……ヤダ」
いつもの口癖。
「ね、マナ」
「はい」
「手、出して」
凌平さんが、ゆっくりと体を離して背中を向けた。
「こう、かな」
手のひらを上にして出して、大人しくしてた。
振り返った凌平さんが、「なんでそうなるのかな」と呆れつつ、手の甲を上にした。
「……ふぅ」
大きく深呼吸をして、すこし俯いて。なにかあるのかと身構えていると、あたしの手を取った。
「マナに聞きたいことがある」
「あ、はい」
どうしよう。こういう空気って苦手だ。
「ハッキリ聞くけど、好きな人いるの?」
そういわれて、目の前に気になってる人がいますと言っていいのか迷う。
凌平さんがあたしに好きだと言ってくれたのを、ずべて鵜呑みに出来ないままだし。
さっきからくれている、あたしが特別という想い。それもまだ信じきれない。
それに、その言葉に浮かれてあたしもですなんて言っても、からかってたとか言われないだろうか。
「う……ん、はい」
悩みに悩んで、かろうじてそう返す。
「それじゃ、これあげる」
右手の薬指。前に教えてくれた、好きな人がいるときに指輪をはめる指だ。
「好きな人がいますって証し。それでさ、誰なのか。俺には知る権利……ない?」
真っすぐに射抜かれそうな視線で見つめられる。
「権利って、その」
シンがこの場にいたらよかった。わからないことが聞けるのに。
(凌平さんって、あたしのことホントのホントで好きなのかな)
迷ったままで、あやふやなことも言いにくい。
「じゃあ、やっぱり誰とでも流されてしまえばキスするの?出来ちゃうの?」
指輪をはめた手を取り、その指輪の上から小さくキスを落とす。
その仕草が艶めかしくて、正視できない。やっぱり凌平さんは大人の男の人だ。
(あたしみたいな子供じゃ役不足だよ)
自分の幼さや知識のなさを痛感するたびに、やっぱりダメだと歯止めしたくなる。
「じゃあ、質問変えるよ。……俺、いなくなろうかと思って」
「……え」
また聞き間違い?
「マナから離れようかなって」